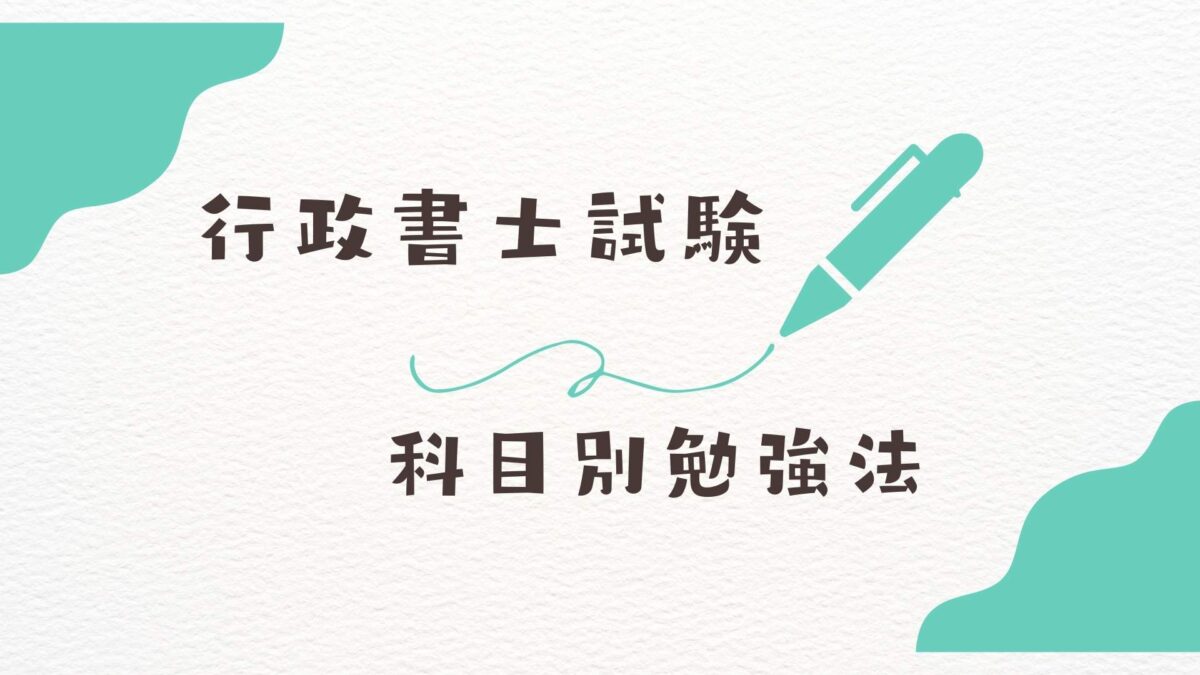独学で「会社法の沼」に沈んだ2年間——その苦い経験が伝える教訓
「行政書士になって、新しいキャリアを切り拓きたい」
仕事と子育てに追われる日々の中、私がそう決意したのは数年前のことでした。試験範囲の広さに圧倒されながらも、「すべての科目を均等に、完璧にマスターしなければならない」と思い込んでいた私は、分厚いテキストに気圧されながらも、商法・会社法の勉強に真っ向から取り組みました。
そして、私は見事に「会社法の沼」に足を取られました。
条文の細部、例外規定の枝葉末節まで理解しようと、土日のほとんどを会社法の学習に費やす毎日。しかしその努力は、行政法や民法といった得点源となる科目の学習時間を削る結果となり、模試では得点が伸び悩むばかり。最終的には、合格に必要な戦略を完全に見誤っていたことに気づきました。
膨大な時間を費やして得た教訓は、「努力の方向を間違えることは、努力しないことよりも恐ろしい」ということです。
この記事をご覧のあなたも、かつての私のように、仕事や家庭と勉強の両立に悩みながら、限られた時間で効率的な学習方法を模索しているかもしれません。だからこそ私は、この失敗と後悔の経験を、あなたの“合格への近道”としてお伝えしたいのです。
本稿では、私が2年間の非効率な独学生活を経てたどり着いた、行政書士試験における「商法・会社法の本当の攻略法」を詳しくご紹介します。目指すのは満点ではなく、最小限の努力で1~2問(4~8点)を確実に拾う、いわば「コスパ重視」の学習戦略です。
読み終えるころには、商法・会社法を恐れることなく、合理的かつ戦略的に向き合う術が、あなたの中にしっかりと根づいているはずです。
私の遠回りが、あなたの最短ルートになりますように。
第1章 商法・会社法は“脇役”である——試験全体における正しい位置づけを知る
1.1 商法・会社法の出題数と配点を正しく理解する
まず押さえておきたいのは、行政書士試験の配点構造です。試験は全体で300点満点。そのうち180点以上を獲得すれば合格となる絶対評価制が採用されています。
ただし、単純な合計点ではなく、「法令等科目で122点以上」「基礎知識科目で24点以上」という足切り基準が設定されており、それをクリアする必要があります。
では、商法・会社法がその300点の中でどれほどのウェイトを占めているかというと、出題は以下の通りです。
- 出題数:全60問中5問(すべて択一式)
- 配点:1問4点 × 5問 = 計20点
- 試験全体に占める割合:約6.7%(20点 / 300点)
内訳は例年、商法が1問、会社法が4問という構成が通例です。
1.2 「主役」と「脇役」を見極めることが戦略の出発点
下記は主要科目の配点を一覧にした表です。商法・会社法がどれだけ“脇役”であるかが一目で分かるはずです。
| 科目名 | 出題形式 | 問題数 | 配点 | 試験全体に占める割合 |
|---|---|---|---|---|
| 行政法 | 択一・多肢・記述 | 22問 | 112点 | 約37.3% |
| 民法 | 択一・記述 | 11問 | 76点 | 約25.3% |
| 憲法 | 択一・多肢 | 6問 | 28点 | 約9.3% |
| 商法・会社法 | 択一のみ | 5問 | 20点 | 約6.7% |
| 基礎法学 | 択一のみ | 2問 | 8点 | 約2.7% |
| 一般知識 | 択一のみ | 14問 | 56点 | 約18.7% |
これらの数字から分かるように、行政法・民法は合否に直結する“主役”です。一方、商法・会社法は、確かに無視できないものの、試験全体から見ればあくまで“サブ”的な位置づけです。
つまりこの科目は、「深追いして満点を狙う科目」ではなく、「最低限の労力で2~3問を確実に取りに行く」ための“戦略科目”と捉えるべきなのです。
この立ち位置を正しく理解しているかどうかで、学習計画全体のバランスが大きく変わります。努力の優先順位を誤れば、合格に必要な“本丸”に裂くべき時間を浪費することにもなりかねません。
この章での結論は明確です。
商法・会社法は重要だが、“主役ではない”。
完璧主義ではなく、得点効率を最優先に考えるべき科目である。
この冷静な認識こそが、効率的な合格戦略の第一歩となります。
第2章 なぜ商法・会社法は「捨て科目」と呼ばれるのか?
2.1 労力に見合わない…“コスパ最悪”の科目である理由
多くの受験生や講師が、商法・会社法を「捨て科目」と位置づける最大の理由。それは、学習に必要な時間や労力(コスト)に対して、得られる得点(リターン)があまりにも少ないという、極端な「費用対効果の悪さ」にあります。
まず条文のボリュームを見てみましょう。商法と会社法を合わせた条文数は、およそ2,000条。これは民法(約1,050条)のほぼ2倍に相当します。しかし、配点は民法(76点)の3分の1以下しかない20点。この数字だけでも、商法・会社法の“非効率さ”が際立ちます。
つまり、「これだけ勉強してもたった5問しか出ない」というのが、この科目の本質的な問題点なのです。
2.2 初学者泣かせの条文構造と“非日常”なテーマ
商法・会社法が厄介なのは、条文数だけではありません。その内容も、行政書士試験科目の中でも特に難解です。
理由は大きく2つあります。
(1)条文が複雑で読みにくい
手続規定や準用規定が多く、他の条文を参照しながら読み進める必要があります。これは、条文構造に慣れていない初学者にとっては非常に高いハードルです。
(2)テーマが“生活実感”から離れている
例えば民法なら、売買や相続、契約といった私たちの身近なテーマが中心です。一方、会社法では「機関設計」「株式発行」「取締役の義務」など、日常とはかけ離れた法人運営の話が多く、具体的なイメージを持ちにくいのが現実です。
これらの特性により、商法・会社法は“法律初心者にとって最も親しみにくい科目”といっても過言ではありません。
2.3 情報が多すぎて判断不能——独学者が陥る“完璧主義”の罠
この科目が特に独学者泣かせなのは、「何を学ぶべきか、どこを捨てるべきか」という判断基準が非常に見えにくい点にあります。
市販テキストには、すべての論点が網羅されています。しかし、独学者は「この論点は試験に出る/出ない」といった選別基準を持っていないため、書かれている内容をすべて等しく重要だと受け取ってしまいます。
その結果、出題可能性の低いマイナー分野に膨大な時間をかけてしまい、肝心の行政法や民法といった“得点源”の対策時間を圧迫してしまう。これこそが、商法・会社法が“戦略上の落とし穴”とされる最大の理由です。
完璧を目指すあまり、合格から遠ざかる——
商法・会社法では、この皮肉な構図が非常に起きやすいのです。
この章では、“難しいから失敗する”のではなく、“取捨選択できないから失敗する”という構造を理解していただくことが、何より重要なポイントです。
第3章 深追いは禁物!合格ラインに届くための「捨てる判断」と「拾う技術」
3.1 点が取れるところだけ狙う!頻出テーマに絞った“拾い方”
商法・会社法で合格点を確保するために最も重要なのは、「すべてを学ぼうとしない」ことです。
満点は必要ありません。狙うべきは、5問中2~3問(8~12点)を確実に取りに行くこと。
そのためには、「どの分野が出やすいのか」を知ることが何よりも重要です。
大手予備校(伊藤塾・アガルート・LEC・TAC・フォーサイトなど)のカリキュラムを比較すると、頻出分野はほぼ一致しており、これはもはや“業界の共通見解”といってもよいレベルです。
以下が、各予備校や専門家が口をそろえて重要だとする“必修論点”です。
【保存版】商法・会社法の「超」頻出テーマ一覧表
| 分野 | 具体的テーマ | 出題傾向・理由 |
|---|---|---|
| 【会社法】 | 設立 | 出題頻度トップ。条文構造が比較的明快で、初学者にも取り組みやすい。 |
| 株式 | 株主の権利・種類株式など、会社の「所有構造」に関する基本論点が頻出。 | |
| 機関 | 「株主総会」「取締役(会)」が中心。会社運営に関わる主要機関に関する知識が問われる。 | |
| 【商法】 | 商行為 | 商人による取引行為のルール。出題割合が高く、商法分野では最重要テーマ。 |
| 商法総則・商人 | 「商人とは何か」「営業とは何か」など、基本用語や定義の理解が鍵。 |
【会社法】(4問中2~3問がここから出題)
- 設立:株式会社がどのように生まれるか。条文構造も比較的シンプルで初学者にもおすすめ。
- 株式:会社の所有者(株主)に関するルール。権利・義務・種類株式などが頻出。
- 機関:会社を動かす主体に関する規定。とくに「株主総会」「取締役(会)」の権限と役割は頻出中の頻出。
【商法】(例年1問出題)
- 商行為:商人の取引に関する基本的なルール。商法の中でも特に出題頻度が高い。
- 商法総則・商人:商人の定義や営業的範囲など。基礎知識として押さえておきたい範囲。
これらの論点は、過去問の出題実績・出題趣旨分析の両面からも繰り返し問われており、「拾うべき問題を確実に取る」ための最重要分野です。
3.2 迷わず切る!“深追いすべきでない”分野を見極める
一方で、出題可能性が低く、しかも内容が難解な“沼”分野も存在します。これらに時間をかけることは、商法・会社法の学習において最大の非効率となります。
中でも“要注意”なのが以下の分野です。
- 組織再編(合併・会社分割・株式交換など)
手続きが複雑で、理解するには高度な知識が求められます。出題頻度も低く、受験レベルでは“深入り厳禁”とされています。 - 持分会社(合同会社・合資会社・合名会社)
株式会社に比べて出題率が非常に低く、条文構造もやや特殊です。 - 計算・会計に関する規定
純資産の部や計算書類の作成など、内容が専門的でかつ抽象的。得点につながりにくく、深追い無用です。
これらのテーマは、実務上は重要であっても、行政書士試験で問われることは非常に稀です。むしろ、ここに時間を使うことで学習のバランスを崩す危険性があります。
行政書士試験が本当に求めているのは、会社の基本的な構造に関する知識です。つまり、
- 「会社はどうやって作られるのか?」(設立)
- 「誰が会社を所有しているのか?」(株式)
- 「誰が会社を動かすのか?」(機関)
という、ビジネスの根幹をなす基本的な法的理解です。
高度な専門性ではなく、基礎的な知識を“確実に押さえる力”——
これこそが、商法・会社法における合格の本質です。
戦略的に「拾い」、迷わず「捨てる」。
このメリハリが、限られた時間で最大の効果を発揮する鍵になります。
第4章 商法・会社法を効率よく攻略する“絞り込み学習”の実践法
4.1 テキストと過去問——学習ツールはこの2つで十分
商法・会社法の学習においては、教材選びに迷う必要はありません。
基本となるのは、以下の2つだけです。
- 市販のテキスト(どの出版社のものでも構いません)
- 過去問題集(できれば肢別形式)
この2つに絞って、「繰り返し・深掘り・統合」する。それが合格に直結する王道ルートです。
複数のテキストや問題集に手を出すと、情報が分散し、理解も定着もしにくくなります。特に商法・会社法のように「捨てる勇気」が求められる科目では、“教材の断捨離”も戦略の一部と心得てください。
4.2 頻出論点だけ抜き出して“自分だけのテキスト”を作る
基本テキストを使う際は、最初から最後まで通読する必要はありません。
まず読むべきは、「設立」「株式」「機関」「商行為」など、頻出分野に該当する章だけ。その他のページは思い切って“飛ばす勇気”を持ちましょう。
目的は「知識を網羅すること」ではなく、「出るところだけを正確に理解すること」です。
さらに重要なのは、過去問演習や調べた知識を、すべてこのテキストに集約することです。
- 解説で得た補足情報
- 間違えた問題の選択肢とその理由
- 関連する条文番号
- 覚えづらいポイントの図解やメモ
こうした情報を、テキストの余白や付箋にどんどん書き込んでいきます。
こうすることで、テキストが“自分専用の参考書”へと進化していきます。
※「まとめノート」は不要です。すべての情報を一元化することで、復習の効率が飛躍的に高まります。
4.3 正解肢より“誤り肢”が宝の山!過去問の使い方を根本から変える
過去問演習では、「正解を出せたかどうか」だけに注目してはいけません。
本当に学力を伸ばすには、“なぜ他の選択肢は誤りなのか”を説明できる力が必要です。
このプロセスを通じて、条文の趣旨や表現の違い、制度の全体像が深く理解できるようになります。
特におすすめなのは、次の2つの方法です。
- 誤り肢を「正しい内容に書き直す」練習をする
- その根拠条文を調べ、テキストにメモとして反映させる
このように、過去問は「演習ツール」ではなく「学習素材」として使うのが、独学者にとって最大の武器になります。
また、過去問は最低でも3周は繰り返しましょう。
目的は「正解を覚える」ことではなく、「正解にたどり着ける理由を理解し、再現できるようにする」ことです。
テキストと過去問、この2つを徹底的に使い倒せば、商法・会社法は必ず“得点源”になります。
ポイントは、「深く狭く、そして繰り返す」こと。それだけです。
第5章 独学者が陥りやすい“失敗パターン”とその克服法
5.1 「匿名組合」に1日?リターンを無視した“自己満足の学習”
かつての私もそうでしたが、完璧主義に陥ると、出題可能性の低いテーマに無意識のうちに多くの時間を費やしてしまいます。
その典型が、「匿名組合」などのマイナー論点です。
ある週末、私はその制度の趣旨・判例・条文構造を理解しようと丸1日をかけました。ところが、こうした論点が本試験で出題される確率は限りなく低く、時間と労力はほとんど“空振り”に終わったのです。
「テキストに載っている=重要」という思い込み。
これが、独学者の最大の落とし穴です。
限られた時間で合格を狙うなら、「出る可能性のある論点」だけを厳選し、そこに集中投下する判断力が不可欠です。
5.2 地図のない旅――「とりあえず読む」型の迷走学習
戦略のない学習は、方向感覚を失った船と同じです。
独学者がやってしまいがちなのが、
「まずはテキストを1周読もう」「流し読みでもいいから前に進もう」といった、“手段が目的化した学習”。
こうした学び方では、理解も記憶も定着せず、最も重要な論点に時間を割けないまま、全体像もつかめず終わってしまいます。
行政書士試験においては、「読むこと」ではなく「得点に結びつけること」が目的であることを、常に意識してください。
5.3 点が取れない=自信が削られる「負のループ」
最も深刻なのは、努力が点数につながらない状況が続くことで、
やる気・自信・継続意欲がすり減っていくことです。
- 「こんなに勉強しているのに、なぜ得点できない?」
- 「周りはもっと順調なのでは?」
- 「やっぱり自分には向いてないのかも…」
このような思考に支配されると、モチベーションが低下し、学習の継続そのものが困難になります。
これは、やり方を間違えていただけであって、あなたの能力が劣っているわけではありません。
むしろ、誤った学習法から抜け出し、戦略的に取り組み直すことができれば、誰でも「点につながる実感」を得られるようになります。
「努力の方向」を正しく定めることこそが、
合格への最短ルートであり、学習を継続する力の源になります。
第6章 予備校・通信講座は“最短ルート”を示してくれる戦略的パートナー
6.1 合格への近道を知っている——専門家による「出題予測」と「学習の断捨離」
独学で最も難しいのは、「どこまで学べば十分なのか」という判断です。
試験範囲が膨大な商法・会社法では、出題される可能性の低い論点まで網羅しようとして、時間と労力を浪費するケースが後を絶ちません。
一方、予備校や通信講座では、試験傾向を熟知した講師陣が、長年の出題分析をもとに「頻出論点だけに絞った効率的なカリキュラム」を提供しています。
たとえば──
- アガルートの「速習カリキュラム」では、商法・会社法など優先度の低い科目は講義時間を短縮し、学習のメリハリを重視
- 伊藤塾の「4時間で商法8点」講座は、得点効率を最大化するために設計された集中講義
- LECの「商法・会社法特訓講座」は、短期間で頻出分野だけを攻略する構成に特化
つまり、彼らが提供しているのは単なる講義や教材ではなく、「合格に必要なことだけを、最短で学ぶための“戦略地図”」なのです。
6.2 難解な条文を“翻訳”してくれるプロ講師の存在
会社法の条文は、抽象的で長文が多く、他の条文を参照しなければ理解できない箇所も少なくありません。独学では、こうした条文を読むだけで何時間も費やしてしまうことも。
しかし、プロ講師による講義では、こうした複雑な条文をわかりやすく“翻訳”してくれます。
たとえば──
- 図解によって制度の構造を視覚的に理解できる
- 実務例や身近な例を通して、抽象概念に具体的なイメージを持てる
- 語呂合わせや記憶の工夫で、自然と定着しやすくなる
アガルートの豊村講師のようなカリスマ講師は、こうした“理解のショートカット”を数多く提供してくれます。
独学で10回読んでもピンとこなかった内容が、たった1回の講義でスッと腑に落ちることもあるのです。
この“翻訳力”は、独学者にとって代えがたい価値です。
6.3 限られた時間と集中力を守る“リスク最小化”の仕組み
行政書士試験を目指す社会人や子育て世代にとって、何よりも貴重なのが「時間」です。
独学では、間違った方向に進んでしまっても、誰も止めてくれません。その結果、半年〜1年という長期間を無駄にしてしまう可能性すらあります。
予備校・通信講座は、その“時間の損失”という最大のリスクを回避してくれます。
- 出題傾向に沿った設計で、遠回りを防ぐ
- 学習スケジュールが管理されているため、迷わず進める
- 法改正や最新の出題動向にも即応できる
- 質問制度やコミュニティで学習の孤独を和らげられる
これらは、すべて「合格の確率を高めるための仕組み」です。
講座費用は決して安くありませんが、それは「時間と失敗のリスクを買い戻すための投資」ともいえるのです。
独学で迷いながら遠回りするか。
専門家の指導で、一直線に合格を目指すか。
あなたの時間と労力をどう使うかが、最大の戦略です。
第7章 独学でも合格を狙える!商法・会社法おすすめ教材&使い方ガイド
7.1 初学者は“特化型テキスト”でスタートダッシュを切ろう
商法・会社法をこれから学ぶ初学者にとっては、「この科目だけに特化したコンパクトなテキスト」から入るのが最も効率的です。
おすすめは、以下のような一冊完結型の講義系テキストです。
- TAC出版『行政書士 しっかりわかる講義生中継 商法・会社法』
人気講師の講義形式で進むため、理解がしやすく、メリハリも明快。
初学者でも重要論点に絞って学習を始めやすい構成になっています。
こうしたテキストを使うことで、分厚い基本書に圧倒されることなく、
「まずは出るところだけ」「理解しやすい順に進める」という理想的なスタートが切れます。
7.2 総合テキスト派には“王道シリーズ+問題集の組合せ”を推奨
もし、他の科目との一貫性を重視して総合シリーズで揃えたい場合は、
以下のような“王道テキスト+問題集”の組み合わせが安定しています。
定番の市販テキストシリーズ
- TAC出版『合格革命』『みんなが欲しかった!』シリーズ
- 伊藤塾×日経BP『うかる!行政書士』シリーズ
- LEC『出る順行政書士』シリーズ
問題集のおすすめ
- 『合格革命 行政書士 肢別過去問集』(TAC出版)
- 『行政書士 トレーニング問題集』(資格の大原)
重要なのは、1つのシリーズに絞って繰り返すことです。
複数シリーズをまたぐと出題方針や説明の仕方が異なり、混乱の元になります。
「相棒」と決めたシリーズを信じて、反復する方が遥かに効率的です。
7.3 六法は“通読するもの”ではなく“辞書のように引くもの”
商法・会社法の学習において、六法の使い方には注意が必要です。
条文数が膨大なため、最初から読もうとするとすぐに挫折してしまいます。
この科目では、六法はあくまでも「必要なときに引くための道具」です。
活用法のポイント
- 過去問やテキストで出てきた条文を、自分の目で“原文”で確認する
- 条文の正確な要件や構造を把握するために利用する
- 不正解の肢の根拠を調べるときに、すぐに該当条文にアクセスする
推奨される六法のタイプ
- 判例なし・小型で軽量な“ポケット六法”タイプ
→ 必要な条文にすぐアクセスできる。
→ 持ち運びやすく、机上にも置きやすい。
大判・判例付きの六法は情報量が多すぎて、試験対策の観点では効率が下がります。
合格のための“実用性”を最優先に考えましょう。
商法・会社法に必要なのは、教材の数ではなく「使い倒す工夫」。
絞り込みと反復が、独学者にとって最強の武器になります。
まとめ:商法・会社法は“得点効率”で考えるべき戦略科目
ここまで、行政書士試験における商法・会社法の攻略法について、
「学習範囲の絞り込み」と「時間対効果の最適化」という視点から解説してきました。
この章でお伝えしたい要点を、あらためて整理します。
✅ 商法・会社法は“主役”ではなく“脇役”
全300点中わずか20点の出題範囲。合否を分けるのは行政法・民法であり、商法・会社法は「得点を拾いにいく」科目です。
✅ 狙うべきは5問中2〜3問の確保
満点を目指す必要はありません。出題頻度の高い「設立」「株式」「機関」「商行為」だけに集中することで、必要十分な点数を獲得できます。
✅ 学習範囲と教材は“徹底的に絞る”
基本テキスト+過去問だけで十分。情報はテキストに一元化し、「正解以外からも学ぶ」ことで知識が深まります。
✅ 予備校・通信講座は“時間の保険”
出題予測・講義による理解促進・法改正対応など、独学ではカバーできない要素を効率的に補える選択肢です。
私自身、会社法の沼にハマって2年間合格を逃した苦い経験があります。
今、同じように迷いながら独学を続けている方がいるなら、その方にはぜひ「最短で合格するための戦略的な視点」を持っていただきたいと願っています。
商法・会社法は、すべてを学ぶ科目ではなく、必要な知識だけを拾いにいく“戦略科目”です。
賢く、冷静に付き合うことで、限られた時間を合格に直結させましょう。

行政書士試験徹底解説
行政書士試験の完全攻略ガイド|ゼロから始める社会人のための難易度・勉強法・合格ロードマップ