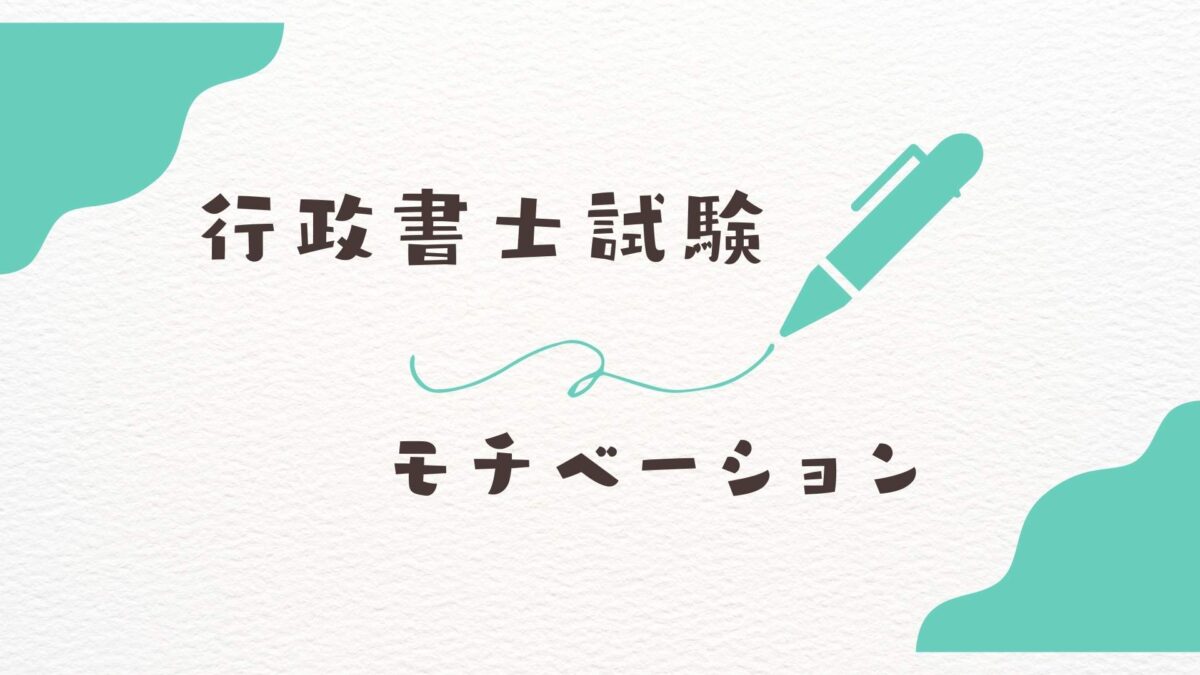仕事・子育て・資格勉強——三重苦の中で挑み続けるあなたへ
行政書士試験の受験勉強。それは、時間的にも精神的にも決して軽い挑戦ではありません。
特に、仕事・子育て・資格学習という三つの責任を同時に抱える方にとっては、まさに「人生をかけたマラソン」とも言える道のりです。
日中は仕事に追われ、家では子どもの世話に奔走し、ようやく確保した深夜や早朝のわずかな時間にテキストを開く──
その努力の積み重ねが、どれほど過酷で、時に報われないように感じられるか、私は痛いほど理解しています。
「もう無理かもしれない」「なぜ自分はここまで頑張っているのだろう」
そんな思いが心をよぎる瞬間があっても、それはあなたが弱いからではありません。
同じような境遇で行政書士を目指す多くの方が、誰にも言えない孤独と葛藤の中で、同じような苦しみを抱えています。
本稿では、単なる精神論ではなく、心理学・行動科学・神経科学などの知見をもとに、モチベーションを「仕組みとして整える」ための具体策をお届けします。
根性に頼るのではなく、科学的に「意欲のしくみ」を理解し、合理的に管理していく——それが、本記事でご紹介する「モチベーション処方箋」の核心です。
子育て世代の受験生であるあなたが、最後まで挑戦を続け、自信と誇りをもって行政書士という資格を手にするために、
この一編が、静かに寄り添い、支え続ける“伴走者”となることを願ってやみません。
第1部|なぜ続かない?やる気を奪う“見えない仕組み”を科学的に解明する
日々の仕事、家庭、学習という三重のタスクを抱えながら、やる気を維持するのは至難の業です。
「勉強しなきゃ」と思っていても、なぜか手が進まない。気持ちが続かない。
その背景には、私たちの脳や心の“構造的なしくみ”が深く関わっています。
この章では、行政書士試験の学習者が陥りやすいモチベーション低下の原因を、心理学・行動科学・神経科学の視点から掘り下げていきます。
1.1 意志力は「使えば減る」リソースである:自我消耗の正体とは?
一日に使える意志力は、筋肉のように“有限”です。
朝は元気でも、夕方には気力が尽きて「もう今日は無理…」となる。これは意志力が消耗している状態です。
この現象は「自我消耗(エゴ・ディプリーション)」と呼ばれ、心理学でも広く研究されています。
勉強を始める前に仕事や育児、複雑な意思決定を繰り返していると、脳はすでにエネルギーを使い果たし、学習に回す“意志力の残量”が残っていないのです。
「やる気がない」のではなく、「脳が頑張れない状態にある」——これを理解するだけでも、自己否定から抜け出す第一歩になります。
1.2 選択が多すぎると人は動けなくなる:「決定疲れ」と先延ばしの関係
学習時間になっても「何からやろう…」と迷っているうちに、時間が過ぎてしまった経験はありませんか?
実はこれも、心理学で説明できます。
私たちは1日に平均で35,000回もの選択をしていると言われており、そのたびに意志力を消耗しています。
この「決定疲れ(Decision Fatigue)」に陥ると、脳はあえて“何もしない”という選択を取りがちです。
結果として、勉強が後回しになり、罪悪感だけが積もる——という悪循環に陥ります。
学習メニューや時間割をあらかじめ「自動化」しておくことが、決定疲れの予防策になります。
1.3 頑張っているのに報われない…それは「目標の設計ミス」かもしれない
毎日ちゃんと机に向かっているのに、「成長実感」がなくて焦りを感じる——
それは、努力の質が低いのではなく、「目標設定の構造」に原因があるかもしれません。
たとえば、「行政法をマスターする!」という曖昧な目標は、達成感が得られず、脳が報酬を感じられません。
一方で、「行政法のAランク論点3つを、今日中に要点だけ整理する」といった“小さな達成可能な目標”であれば、進捗が明確になり、やる気も回復します。
人間の脳は、進んでいる実感があるとドーパミン(やる気ホルモン)を分泌します。
頑張り方より「目標の設計」こそが、モチベーション維持の鍵なのです。
1.4 「親だから我慢すべき」…その“罪悪感”がやる気を奪っていく
子育て中の受験生に特有なのが、「自分のために時間を使うこと」への罪悪感です。
「子どもがいるのに勉強なんて…」「もっと家族に尽くすべきなのに」——
こうした思考は、学習の前向きなエネルギーを根こそぎ奪います。
この心理は、社会的役割からくる“役割期待”と“内面化された規範”によって引き起こされます。
しかし、自己犠牲だけでは長くは続きません。あなたがあなたらしく生きる姿を見せることは、子どもにとっても大きな学びになります。
罪悪感は、「誰の期待に応えようとしているか」を見直すチャンスでもあります。
学ぶあなたの背中を、あなたの家族も必ず見ています。
第2部|やる気を取り戻す!科学的に実証されたモチベーション再生法
第1部で見たように、やる気が出ないのは意志が弱いからではなく、脳や心のしくみによる“自然な現象”です。
それならば、同じく科学的な視点から、そのエネルギーを回復し、再び前へ進む仕組みを整えていくことが可能です。
ここでは、心理学・神経科学に基づく「再びやる気を取り戻すための実践テクニック」を紹介します。
無理に気合いで乗り切るのではなく、脳のしくみを活かした「仕組み化された継続戦略」で、合格まで走り抜けましょう。
2.1 脳の報酬回路を刺激する:「スモールウィン」でやる気を引き出す
「ドーパミン」という脳内物質は、“やる気”と深く関係しています。
このドーパミンは、目標を達成したときに放出され、快感とともに「また頑張ろう」という意欲を生み出します。
ここで重要なのが、“達成すること”そのものが報酬になるという点です。
つまり、大きな目標よりも、「毎日の小さな達成」を積み重ねる方が、モチベーションは継続しやすいのです。
実践例:
- 「過去問を1ページ解く」
- 「テキストを5分読む」
- 「10個の重要語句を暗記する」
これらのような“達成可能なミニ目標”を設定し、毎回「チェックマーク」などで可視化しましょう。
この「スモールウィン(小さな勝利)」の積み重ねが、やる気のエンジンを回し続けてくれます。
2.2 意志力に頼らず行動する:「習慣化」の2大テクニック
日々の勉強を“気合い”に頼って継続しようとすると、長続きしません。
目指すべきは、意志に頼らず自然に行動できる「習慣化」です。ここでは科学的に効果が実証されている2つの手法を紹介します。
If-Thenプランニング(実行意図)
「もし◯◯したら、××する」とあらかじめ行動を結びつけておく方法です。
たとえば…
- 「もし夜9時に子どもが寝たら、そのときは机に向かって過去問を解く」
- 「もしスマホを触りたくなったら、そのときは深呼吸してページに目を戻す」
この事前のルール化により、迷いなく学習行動に移れるようになります。
ハビット・スタッキング(習慣の連結)
既に身についている習慣の後に、新しい行動を“つなげる”方法です。
- 「コーヒーを淹れたら、その間に単語帳を10個チェック」
- 「歯を磨いたら、そのまま10分だけテキストを読む」
毎日のルーティンに勉強を組み込むことで、負荷なく継続できる仕組みが作れます。
2.3 自分に優しくする力:「セルフ・コンパッション」のすすめ
「もっとやらなきゃ…」「自分はダメだ…」——
そうやって自分を責め続けると、やる気はさらに低下していきます。
そこで大切なのが、「セルフ・コンパッション(自己への思いやり)」という考え方です。
これは、失敗やスランプのときに“自分を責める”のではなく、
“親しい友人に接するように、自分に優しく接する”という態度です。
3つの実践要素:
- 自分への優しさ:「また頑張ればいい」「よくここまでやってるよ」と自分を励ます
- 共通の人間性:「誰だってうまくいかないときはある」と認識する
- マインドフルネス:今の苦しみを否定せず、そのまま受け入れる
落ち込んだときにこそ、自分へのまなざしを優しくすることが、再び前を向く力になります。
2.4 勉強効率を高める“戦略的な休憩”:脳を活性化させる休み方とは
「もっとやらなきゃ」と思っても、集中力が落ちてきたと感じたら、いったん“休む”のが正解です。
ただし、それは“ダラける”こととは違います。
ここでは、科学的に集中力と記憶定着を高める「戦略的な休憩」の取り方を紹介します。
ポモドーロ・テクニック(集中×休憩のサイクル)
- 「25分集中→5分休憩」を1セットとし、4セットごとに長めの休憩を取る
- 集中力の持続と時間管理力の向上に有効
アクティブ・レスト(積極的休養)
- 軽いストレッチや散歩、入浴など、身体を動かすことで脳がリフレッシュ
- 血流と酸素供給が改善し、再び高い集中力が戻ります
「休む=サボる」ではなく、「休む=集中力を充電する行為」です。
メリハリのある勉強が、結果的に一番早く合格へ近づけてくれます。
第3部|家族は障害ではなく味方になる:“応援チーム化”のための実践戦略
行政書士試験の学習は、本人の努力だけでなく、家族との関係性も大きく影響します。
特に子育て世代の場合、家族の理解と協力があるかどうかで、勉強時間の確保や精神的安定に大きな差が生まれます。
この章では、家庭内での対立を最小限に抑えつつ、むしろ家族を「目標達成を支えるチーム」に変えるための具体的な工夫をご紹介します。
3.1 理解されない孤独をなくす:ファミリー・ハドル(作戦会議)のすすめ
受験期間中、「どうして分かってくれないのか…」という孤独感に悩むことは少なくありません。
ですが、それは単に“共有が足りていない”だけかもしれません。
そこでおすすめなのが、「家族全員で話す時間=ファミリー・ハドル」です。
これは、ビジネスにおける“キックオフミーティング”のようなもの。家庭というプロジェクトチームで、戦略を共有する時間です。
話し合うべき3つの要素:
- なぜ学ぶのか(目的の共有):行政書士資格の取得が、自分だけでなく家族の未来にどうつながるのかを、熱意をもって伝えましょう。
- 何が変わるのか(制約の共有):学習期間中は時間や体力に制限が生まれることを、正直に伝えておくことでトラブルを防げます。
- どう乗り切るか(協力体制の設計):一方的なお願いではなく、家族と一緒に「どう支え合うか」を考えることで、自然な協力関係が築けます。
この時、「協力してほしい」よりも「応援してくれると嬉しい」という伝え方が、心理的ハードルを下げる効果もあります。
3.2 見えない努力を「見える成果」に変える:進捗共有の力
勉強は基本的に一人で行うものですが、それゆえに「何をしているのか」が家族に伝わりづらく、摩擦の原因になることもあります。
この「見えにくさ」を解消するために有効なのが、「進捗の見える化」です。
実践アイデア:
- 共有カレンダーの活用:GoogleカレンダーやTimeTreeで勉強時間を事前に“予約”しておくと、家族の予定との衝突を防げます。
- 成果の共有:「今日はこの章を終えたよ」「模試で○点取れたよ」といった報告は、家族の共感と応援を生みます。
こうした取り組みにより、家族は「勉強の邪魔をしないようにしてあげる」から、「一緒に挑戦を支える仲間」へと意識が変わります。
3.3 限られた時間でも心はつながる:家族時間の“質”を最大化する方法
試験勉強を優先すると、どうしても家族との“時間の量”は減ってしまいます。
だからこそ、意識すべきなのは「時間の質」を高めることです。
戦略1:100%集中の“没入型”家族時間
30分だけでも、スマホや学習のことを完全に遮断して、子どもと遊ぶ・配偶者と会話する。
この“全力で一緒にいる時間”は、家族の満足感を大きく高めます。
戦略2:親子で学ぶ“スタディ・バディ”化
子どもが宿題をする時間に、自分も一緒にテーブルで勉強する——
「共に学ぶ空間」を作ることで、家庭内に学習文化が生まれます。
戦略3:完璧を手放すマインドセット
食事や家事が少し手抜きになっても、「今は学習を優先する期間」と割り切る。
この思考の切り替えは、自分を責めすぎず、前に進む力を保つ助けになります。
“家族の理解”は待っているだけでは得られません。
こちらから誠実に伝え、共有し、信頼を積み重ねていくことで、家庭はあなたの最強の応援団になります。
第4部|長丁場に耐え抜く“心の筋力”:レジリエンスとマインドセットを鍛える
行政書士試験は、数ヶ月〜年単位に及ぶ長期戦。
一時的なやる気やテクニックだけでは、途中で燃え尽きてしまうこともあります。
本章では、逆境を乗り越える「レジリエンス(精神的回復力)」と、成長を信じる思考習慣「マインドセット」に焦点を当て、
継続力と自己肯定感を支える“心の土台”をどのように築くかを探っていきます。
4.1 合格後の自分を“リアルに”感じる:ビジュアライゼーションの活用法
遠い未来の目標ほど、モチベーションが維持しづらい。
これは、「時間的距離」が生む“現実感の薄さ”が原因です。
この壁を乗り越える有効な方法が「ビジュアライゼーション(視覚化)」です。
脳は“強くイメージされた出来事”を“現実のように”認識する性質を持っており、
成功した自分の姿を具体的に描くことで、現在の行動に対する意欲が高まります。
実践例:
- 資格取得後の未来像を描く:事務所の看板、顧客対応、子どもとの余裕ある時間
- 具体的な生活の変化を想像する:年収アップ、時間の自由、独立開業のビジョン
- 1日5分、五感を使ってイメージ:映像として、音・手触り・空気感まで含めて“思い描く”
これは単なる「夢」ではなく、「行動の方向性を定める設計図」として非常に効果的です。
4.2 「やめとけ論」に打ち勝つ力:成長マインドセットという思考の盾
「今さら無理だよ」「子育て中なんて受かるわけない」——
そうした“否定的な言葉”や、自分自身の中に湧き上がる「自信のなさ」に負けそうになる時、必要なのは“思考の柔軟性”です。
スタンフォード大学のキャロル・ドゥエック教授が提唱する「成長マインドセット」は、
能力を“固定されたもの”ではなく、“努力によって伸ばせるもの”と捉える考え方です。
2つのマインドセットの違い:
- 固定マインドセット:「自分には向いていない」「才能がないから無理」
- 成長マインドセット:「まだできないだけ」「失敗は伸びるチャンス」
模試の不調も、壁にぶつかる瞬間も、「自分が成長している証拠だ」と捉え直す習慣が、長期的な継続力を育てます。
4.3 つまずいても“立ち直れる”人になる:レジリエンス(心理的回復力)の鍛え方
レジリエンスとは、「打たれ強さ」ではなく、「打たれた後に立ち直る力」のことです。
これは生まれつきの性格ではなく、習慣や環境によって後天的に育てることができます。
鍛えるための3つの視点:
- コントロール可能なことに集中する:他人の評価ではなく、自分の行動に意識を向ける。
- 失敗を“データ”として扱う:「落ち込む」のではなく、「改善点が見えた」と分析する。
- 一人で抱え込まない:信頼できる学習仲間・家族・講師などに、早めに相談する。
また、視覚化(4.1)とマインドセット(4.2)とレジリエンスは相互に作用します。
理想の未来像が「折れそうな時の支え」となり、失敗を前向きにとらえる習慣が「回復力」を高めます。
これらを意識的に育てることで、学習そのものが「自分自身を鍛える過程」となり、
資格取得後の実務にも通じる“折れない軸”が形成されていきます。
第5部|“一人で頑張らない”という戦略:外部リソースを賢く使う方法
行政書士試験の学習は、長期戦かつ高難度。
「独学で合格したい」「自分の力でやり切りたい」と思う気持ちは尊いものですが、
それが“孤立”や“行き詰まり”につながってしまっては本末転倒です。
この章では、学習の継続と効率化を支える外部リソースの活用法を、合理的かつ実践的に解説します。
5.1 “全部ひとりで”は危険信号:「質問できる環境」が学習を支える
「わからないところを調べながら独学で進める」——一見すると効率的に見えますが、
時間と精神的エネルギーを大量に消費する危うさがあります。
特に、法令や判例の理解においては、少しの読み違いが全体理解を歪めてしまうことも。
その結果、次第に不安が募り、やる気を失っていくケースも少なくありません。
なぜ“質問環境”が必要か?
- わからない箇所をすぐに解決できることで、学習の流れが止まらない
- 専門的な見解が得られることで、自信を持って次に進める
- 不安や孤立感を和らげることで、学習モチベーションの維持につながる
通信講座やオンラインスクールが提供する「質問対応機能」は、単なるオプションではなく、
“知識の詰まり”をほぐし、モチベーションの断絶を防ぐ「命綱」として位置づけるべき機能です。
5.2 仲間の存在が継続力を生む:学習コミュニティがもたらす心理的効果
勉強は基本的に一人で行うものですが、ずっと一人でいると「自分だけが辛い」と感じやすくなります。
この孤独感が、継続の大きな妨げになるのです。
そこで有効なのが、「学習コミュニティへの参加」です。オンライン/オフラインを問わず、
同じ目標に向かう仲間とつながることで、心理的な安心感と継続力が生まれます。
学習仲間がもたらす3つのメリット:
- “悩みの共有”による安心感:他人も同じように悩んでいると知ることで、自分を責めすぎなくなる
- “行動の可視化”によるやる気向上:「みんな頑張ってるから自分もやろう」という健全な刺激
- “気軽に質問できる空気感”:チャットや掲示板などで、初歩的な質問も気兼ねなくできる
独学でもモチベーションを維持できる人は稀です。
他者との適度なつながりを持つことは、“気合い”ではなく“仕組み”で継続するための現実的な対策と言えるでしょう。
仕事も子育ても勉強もあきらめないあなたへ──合格まで伴走する“希望の処方箋”
行政書士試験に挑戦するという決断は、それだけで尊いものです。
ましてや、仕事と家庭を抱えながらの挑戦であれば、その努力は言葉にできないほど価値あるものです。
このレポートでは、「なぜモチベーションが続かないのか」「どうすれば回復・維持できるのか」
その背景にある“心と脳のメカニズム”を紐解きながら、再現性ある「処方箋」をご紹介してきました。
あらためて、5つの柱を振り返ります。
- 見えない疲労を正しく理解する
自我消耗・決定疲れ・罪悪感──これらは個人の根性ではどうにもならない「自然な現象」です。 - 行動を仕組み化して回復させる
スモールウィン、習慣化、セルフ・コンパッション、戦略的休憩という科学的手法で、やる気を再生します。 - 家族を“チーム”に変える
対立構造ではなく、目標を共有する仲間として家族と向き合うことで、強力なサポート体制が築けます。 - 強くしなやかな“心の土台”を育てる
ビジュアライゼーション、成長マインドセット、レジリエンスは、長期戦を走り抜くための精神的フレームです。 - 一人で抱え込まず、賢く支援を使う
質問環境や学習コミュニティといった“外部リソース”の活用は、合理的で効率的な戦略です。
この試験の道のりは、決して楽なものではありません。
しかし、あなたがこの過程で身につける「問題を構造的に理解し、解決策を実行する力」は、
行政書士という国家資格にふさわしい専門性であり、
そして人生をより自律的に生き抜くための“本当の力”でもあります。
このレポートが、あなたの努力に寄り添い、
不安な夜や迷う瞬間に、そっと背中を押せる存在であることを願っています。
あなたの挑戦に、心から敬意を込めて──。