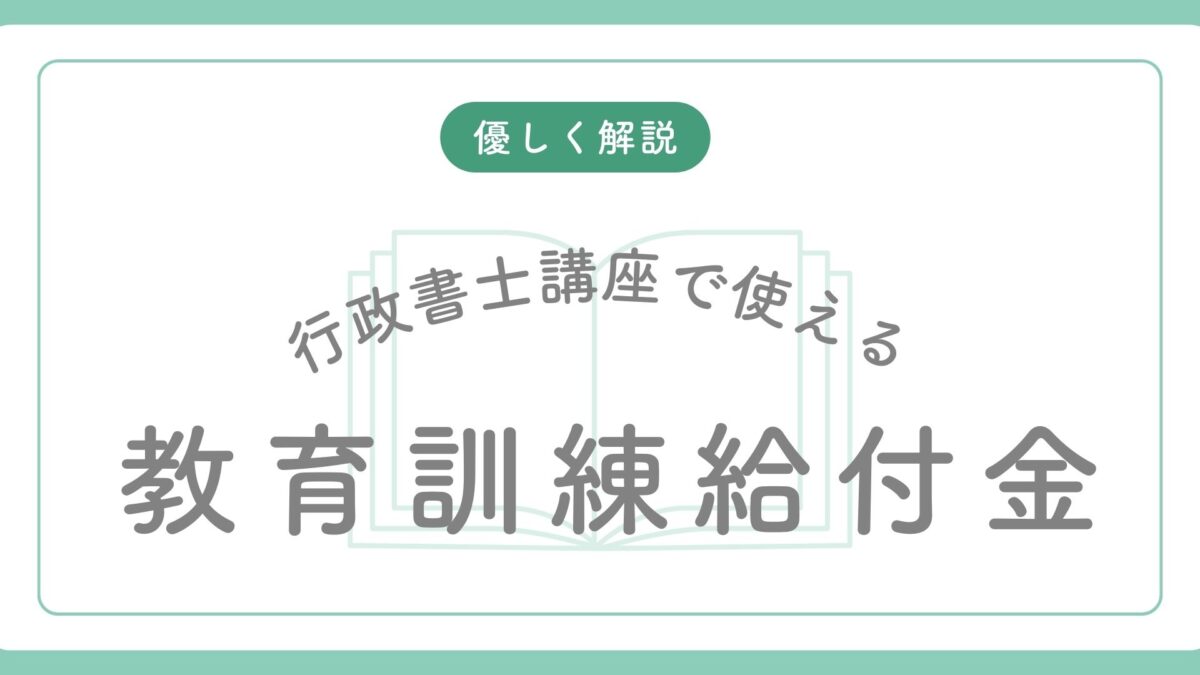第1章|教育訓練給付制度とは?仕組みと3つの給付タイプをわかりやすく解説
1.1 制度の目的と概要|「学び直し」を国が後押しする公的支援制度
教育訓練給付制度とは、働く人の主体的な能力開発やキャリア形成を支援するため、国が設けている雇用保険の給付制度です。対象の講座を修了した場合に、支払った受講料の一部がハローワークから給付される仕組みで、受講者にとって経済的な負担軽減につながります。
在職中の方はもちろん、離職後の一定期間内であれば利用できる点も特徴です。特に、資格取得を目指す方や再就職を視野に入れている方にとって、非常に心強い制度といえるでしょう。
制度の対象となる講座は、厚生労働大臣が指定した「教育訓練講座」に限られ、毎年4月1日と10月1日に指定内容が見直されます。そのため、最新の対象講座を確認することが重要です。
1.2 教育訓練給付制度の3タイプ|目的と給付率の違いを比較
教育訓練給付制度には、受講目的や専門性の違いに応じて、以下の3つの区分が設けられています。
- 一般教育訓練給付金
一般的なスキルアップや資格取得を支援する基本的な給付制度です。行政書士講座はこちらに該当し、受講料の20%(上限10万円)が支給されます。 - 特定一般教育訓練給付金
早期の再就職を目指す方を対象とした制度で、給付率は40%(上限20万円)。社会保険労務士や介護職関連講座など、就職に直結しやすい講座が中心です。 - 専門実践教育訓練給付金
看護師や保育士など、国家資格や専門職の養成課程が対象で、給付率は最大70%、年間上限は56万円(最長4年)。長期的なキャリア形成を目的とした支援制度です。
なお、行政書士講座はこのうち「一般教育訓練給付金」の対象として位置づけられており、次章からはこの一般枠を中心に詳しく解説していきます。
表1|教育訓練給付制度の3つの給付金を徹底比較
| 給付金の種類 | 制度の目的 | 給付率 | 給付上限額 | 主な対象者(初回利用) | 対象講座の例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一般教育訓練給付金 | 雇用の安定やキャリアアップの支援 | 受講料の20% | 最大10万円 | 雇用保険の被保険者期間が通算1年以上 | 行政書士、簿記、ITパスポート、語学講座など幅広いスキル系講座 |
| 特定一般教育訓練給付金 | 再就職支援や専門職への早期転換の促進 | 受講料の40% | 最大20万円 | 雇用保険の被保険者期間が通算1年以上(※要キャリアコンサルティング) | 社会保険労務士、税理士、介護初任者研修など就職直結系の資格講座 |
| 専門実践教育訓練給付金 | 中長期的な専門職キャリア形成の支援 | 受講料の最大70% | 年間最大56万円(最長4年) | 雇用保険の被保険者期間が通算2年以上(※要キャリアコンサルティング) | 看護師、保育士、建築士、介護福祉士、美容師などの養成課程 |
※対象講座は厚生労働大臣の指定を受けた講座に限られます。指定は毎年4月と10月に見直されるため、最新情報の確認が必要です。
第2章|あなたは対象になる?教育訓練給付金の受給資格をチェックしよう
2.1 受給資格の基本条件|在職中と離職後で異なる要件を理解する
教育訓練給付金を利用するには、一定の「雇用保険加入期間」と「受講開始時点の就業状況」に関する要件を満たしている必要があります。以下に、在職中の方・離職後の方に分けて基本条件をまとめます。
■ 在職中の方(雇用保険に現在加入している場合)
- 受講開始日に雇用保険の被保険者であること
- 初回利用の場合:通算1年以上の被保険者期間があること
- 2回目以降の利用では、別途条件あり(2.2で詳述)
■ 離職中の方(雇用保険に現在未加入の方)
- 離職日の翌日から数えて1年以内に受講を開始すること
(※育児・疾病等の理由がある場合は最長20年まで延長可能) - 初回利用の場合:離職前の通算被保険者期間が1年以上あること
2.2 【要注意】初回利用と2回目以降で変わる「被保険者期間」の考え方
教育訓練給付金は、利用回数によって必要な「被保険者期間(支給要件期間)」が異なります。
● 初回利用の場合
- 受講開始時点で、通算して1年以上の雇用保険被保険者期間があれば対象となります。
● 2回目以降の利用の場合(再利用)
- 前回の講座の「受講開始日」から起算して、今回の講座の受講開始日までに通算3年以上の被保険者期間が必要です。
- 前回より前の被保険者期間は「リセット」されるため、注意が必要です。
✅ 具体例(Aさんのケース)
Aさんは2021年4月1日に教育訓練給付制度を利用して講座を受講。2025年10月に再び制度を使って行政書士講座を受講する予定です。
- 2021年4月1日〜2025年10月1日までに3年以上の被保険者期間があれば利用可能。
- この間に1年以上の離職期間があると、期間不足で対象外になる可能性があります。
2.3 かんたん判定!教育訓練給付金の受給資格フローチャート
あなたが給付対象になるかどうか、以下のステップで簡易チェックしてみましょう。
✅ Step 1|現在、雇用保険に加入していますか?
- はい → Step 3へ
- いいえ → Step 2へ
✅ Step 2|離職日の翌日から1年以内に受講を開始しますか?
- はい → Step 3へ
- いいえ → 原則対象外(※延長申請の余地あり)
✅ Step 3|過去に教育訓練給付制度を利用したことがありますか?
- いいえ(初回利用) → Step 4へ
- はい(2回目以降) → Step 5へ
✅ Step 4|被保険者期間が通算1年以上ありますか?
- はい → ✅【対象の可能性あり】
- いいえ → ❌【対象外】
✅ Step 5|前回講座の「受講開始日」以降、通算3年以上の被保険者期間がありますか?
- はい → ✅【対象の可能性あり】
- いいえ → ❌【対象外】
第3章|失敗しないための5ステップ|申請から給付金受け取りまでの流れを完全解説
教育訓練給付金は、正しい手順を踏めば確実に受け取れる制度です。ここでは、行政書士講座で「一般教育訓練給付金」を利用する場合を前提に、申請から給付までの流れを5つのステップに分けてわかりやすく解説します。
Step1|受給資格をハローワークで事前確認する【任意だが推奨】
- 誰が:受講を検討している本人
- どこで:住所地を管轄するハローワーク(窓口・郵送・e-Gov)
- いつまでに:講座申込前に行うのが理想
- 内容:「教育訓練給付金 支給要件照会票」を提出して、制度利用の可否を事前に確認できます。
この確認は義務ではありませんが、後々のトラブル防止やスムーズな給付申請のために、早めの確認を強くおすすめします。
Step2|給付対象の講座に申し込む【本人名義が必須】
- 誰が:受講希望者本人
- どこで:アガルート、LEC、TACなどの予備校サイトや窓口
- 注意点:
- 申込時に「教育訓練給付制度を利用する」意思を必ず伝える(多くの予備校では申込フォームにチェック項目あり)
- 受講料の支払いは必ず受講者本人の名義で行う(会社名義は対象外)
Step3|講座を受講・修了する【修了要件を必ず確認】
給付金を受け取るには、「講座の修了」が必要条件です。各予備校によって修了基準が異なるため、必ず事前に確認しましょう。
📌 主な予備校ごとの修了基準(例)
| 予備校名 | 修了基準例 |
|---|---|
| アガルート | 講義の70%以上視聴+修了課題で70%以上の得点 |
| LEC | 添削課題提出80%以上+確認テスト70%以上 |
| TAC | 出席率80%以上+修了試験で60%以上(通学の場合) |
| クレアール | 全添削課題で60%以上の得点 |
修了基準は学習ペースの目安にもなります。「給付のため」というだけでなく、学習継続のモチベーションとしても有効です。
Step4|修了後、必要書類をそろえてハローワークへ申請する
- 誰が:受講者本人
- どこで:住所地のハローワーク(窓口・郵送・e-Gov)
- いつまでに:講座修了日の翌日から1か月以内(※厳守)
✅ 必要書類一覧(提出先:ハローワーク)
予備校から交付される書類
- 教育訓練給付金 支給申請書
- 教育訓練修了証明書
- 領収書 または クレジット契約証明書
- (あれば)返還金明細書(割引やポイント利用がある場合)
本人が準備する書類
- 本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカードなど)
- マイナンバー確認書類
- 雇用保険被保険者証 または 雇用保険受給資格者証
- 本人名義の通帳またはキャッシュカード
Step5|給付金の受給|通常1か月程度で入金
- 誰が:ハローワーク → 申請者本人
- どこで:申請時に指定した金融機関口座
- いつ頃:申請受理から通常1か月前後
申請が受理されると、受講料の20%(上限10万円)が計算されて指定口座に振り込まれます。これにて給付の手続きは完了です。
第4章|最新版比較|給付金対象の行政書士講座を選ぶ際のポイントと注意点
教育訓練給付制度を活用できる行政書士講座は限られています。本章では、2024〜2025年の最新情報をもとに、対象講座の比較と選び方のポイントを解説します。
対象講座の中でも、内容や受講形式、費用、サポート体制には違いがあるため、単に給付金が出るかどうかだけでなく「自分に合った講座かどうか」を見極める視点が重要です。
4.1 給付対象講座の全体像|主要予備校の対応コースを比較する
教育訓練給付金の対象として厚生労働大臣の指定を受けている行政書士講座は、全国の主要資格予備校が提供しています。表2では、対象となっている講座の正式名称、受講料、支給される給付額、講座の特長などを比較表形式でまとめました。
この表を参考に、ご自身の学習スタイル・予算・通学or通信の希望に合った講座を検討してみてください。
4.2 各予備校の講座設計と給付制度利用時の注意点
給付対象となっている講座であっても、申請・受給にあたっては以下のような注意点があります。
- 修了条件の達成が必須:講座を「修了」して初めて給付が認められるため、出席率・課題提出率・修了試験など、各校の基準を事前に確認する必要があります。
- 割引後価格で給付額が計算される:受講料の割引キャンペーンを適用した場合、給付金は割引後の金額を基準として20%が支給されます。
- 合格特典(全額返金制度)と併用できない場合がある:一部予備校では、給付金を受けた場合、合格返金制度が利用できないため、申込時の選択には要注意です。
- 講座ごとに「給付金対象プラン」の選択が必要な場合がある:特に資格スクエアなどでは、給付金用の専用プランに申し込まないと対象にならないことがあります。
このような制度的制限を見落とさず、講座選びと同時に申請要件も視野に入れておくことが、確実な給付受給につながります。
4.3 制度対象外の講座に注意|給付金が使えない人気講座もある
すべての行政書士講座が教育訓練給付制度の対象になっているわけではありません。一部の人気講座であっても、制度の対象外となっている場合があります。
✅ 現在、対象外である主な講座(2024年7月時点)
- 伊藤塾:公式FAQで制度対象外である旨を明示
- スタディング:行政書士講座は制度非対応と明記あり
これらの講座は教材の質や講師の実績には定評がありますが、給付金による受講料の軽減は受けられません。
表2|主要予備校の行政書士講座を徹底比較|教育訓練給付制度の対象コース一覧(2024-2025年版)
| 予備校名 | 給付対象講座の正式名称 | 給付制度の種類 | 受講料(税込) | 最大給付額(20%換算) | 講座の特長・補足情報 |
|---|---|---|---|---|---|
| アガルートアカデミー | 入門総合カリキュラム フル(2026年合格目標) | 一般教育訓練給付金 | 295,020円(割引適用時) | 59,004円 | 合格実績とサポートの充実度で人気。合格特典との併用不可のため注意。 📎 https://www.agaroot.jp/gyosei/ |
| LEC東京リーガルマインド | パーフェクトコース/速習講座 など複数 | 一般教育訓練給付金 | 45,000〜275,000円 | 最大10万円 | 大手予備校としての実績。通学・通信の選択肢が豊富。 📎 https://www.lec-jp.com/kyuufu/ippan/kouza_gyousei.html |
| TAC | プレミアム本科生Plus/ベーシック本科生 など | 一般教育訓練給付金 | 193,600〜264,000円 | 最大10万円 | 通学型の受講にも対応。修了基準が明確で安心。 📎 https://www.tac-school.co.jp/kouza_gyosei/gyosei_kyufu.html |
| 資格スクエア | 森Tの1年合格講座(給付金プラン) 短期集中講座(給付金対象) | 一般教育訓練給付金 | 69,300円/165,000円 | 13,860円/33,000円 | 人気講師によるオンライン特化講座。申込時に「給付金プラン」の選択必須。 📎 https://www.shikaku-square.com/gyoseisyoshi/ |
| クレアール | 2025年合格目標 完全合格カレッジコース | 一般教育訓練給付金 | 86,190円(割引適用時) | 17,238円 | 通信専門校。「非常識合格法」で効率重視。コスパ良好。 📎 https://www.crear-ac.co.jp/gyousei/course/ |
🚫 給付制度の対象外講座(2024年7月時点)
| 予備校名 | 対象外理由・公式情報 |
|---|---|
| 伊藤塾 | 現在、行政書士講座は給付制度の対象外である旨を公式に明記。 |
| スタディング | 行政書士講座は給付対象外。公式FAQに明記あり。 |
※補足:受講料は2024年7月時点の調査情報に基づきます。キャンペーンや割引の有無により金額が変動するため、申し込み前に各予備校の公式サイトで最新情報をご確認ください。
第5章|教育訓練給付制度を利用するメリットと注意点
教育訓練給付制度は、うまく活用すれば非常に有利な制度ですが、利用にあたってはいくつかの注意点も存在します。この章では、制度を使うことで得られる利点と、事前に理解しておきたいデメリットについて整理します。
5.1 メリット|経済的な負担軽減と「学習を続ける仕組み」
■ 経済的メリット:受講料の一部が戻ってくる
教育訓練給付金の最大の魅力は、支払った受講料の一部(最大20%、上限10万円)が支給される点です。
たとえば受講料が25万円の講座であれば、5万円が実質的に戻ってくるため、初期投資への心理的ハードルを下げる効果があります。
■ 学習継続のモチベーションになる「修了要件」
給付金を受け取るには、講座を「修了」することが条件となります。多くの予備校では、
- 一定の講義視聴率
- 課題提出率や修了試験の得点
といった基準を設けています。
これらの基準を満たす必要があることが、学習の継続を促す「良い意味での強制力」となり、モチベーションの維持に役立ちます。
■ 講座の信頼性が担保されている
制度の対象となる講座は、厚生労働大臣によって指定されたものに限られます。そのため、一定の教育品質が認められている講座であるという安心感も得られます。
5.2 デメリット|立替払いと煩雑な手続きに要注意
■ 受講料は全額を一旦自己負担する必要がある
給付金は「受講料の割引」ではなく、「修了後に申請し、後日支給される返還金」です。そのため、申し込み時点では受講料全額を自分で支払う必要があります。
分割払いや教育ローンを利用する場合でも、「本人名義での支払い」が条件になる点に注意してください。
■ 申請書類の準備と提出がやや煩雑
制度の利用には、修了後1か月以内に複数の書類をそろえてハローワークに提出する必要があります。
特に注意したいのが以下の2点です:
- 提出期限の厳守(修了日の翌日から1か月以内)
- 書類不備があると再申請が必要になるリスク
書類は予備校から交付されるものと、自身で準備するものがあるため、事前にチェックリストで確認しておくことが重要です。
■ 給付対象外費用に注意
教育訓練給付金の支給対象は「受講料(および教材費等)」に限定されます。以下の費用は対象外です:
- 行政書士試験の受験料
- 市販の参考書
- 通学にかかる交通費 など
また、割引やポイント利用がある場合、給付額は「実際に支払った金額×20%」で計算されるため、期待した金額より少なくなる場合もあります。
第6章|よくある質問(Q&A)で制度利用の不安を解消しよう
教育訓練給付制度は、制度の内容がやや複雑であるため、多くの方が共通する疑問や不安を抱きがちです。ここでは、実際によくある質問を5つ厳選し、制度利用の判断に役立つよう丁寧に解説します。
Q1. 退職したあとでも、教育訓練給付制度は利用できますか?
A:はい、条件を満たせば利用できます。
離職後でも、以下の2点を満たしていれば給付金の対象になります。
- 雇用保険の被保険者資格を喪失した日(離職日の翌日)から1年以内に講座の受講を開始していること
- 離職前の被保険者期間が通算1年以上あること(初回利用の場合)
Q2. 行政書士試験に不合格でも、給付金は受け取れますか?
A:はい、試験の合否は関係ありません。
給付金は「資格試験の合否」ではなく、「講座を所定の修了条件で修了したかどうか」に基づいて支給されます。そのため、
- 試験に不合格だった場合でもOK
- 受験しなかった場合でも、修了していれば支給対象です
Q3. 制度を利用したことが勤務先に知られることはありますか?
A:いいえ、勤務先に通知されることはありません。
教育訓練給付金の手続きは、
- 申請者(本人)
- 教育訓練実施機関(予備校)
- ハローワーク
の3者間で完結します。勤務先に連絡が入ったり、証明書を発行してもらったりする必要は一切ありません。
Q4. 複数の講座を同時に受講して、すべてで給付金を申請できますか?
A:いいえ、同時利用はできません。
教育訓練給付制度は、同一期間に複数の講座で併用することは認められていません。
また、複数回の利用が可能であっても、
- 前回の「受講開始日」から起算して3年以上の被保険者期間が経過している必要があります(2回目以降の場合)
Q5. 予備校の割引やポイントを使った場合、給付額はどうなりますか?
A:実際に支払った金額を基準に給付額が決まります。
給付金の算定は、「実際に自己負担した金額」に対して20%を掛けた金額(上限10万円)です。よって、
- 定価20万円 → 割引後18万円 → 支給額は 36,000円(18万円×20%)
というように、キャンペーンやポイント適用後の金額を基準に計算されます。
結論|教育訓練給付制度を味方につけて、行政書士への第一歩を確実に踏み出そう
行政書士という国家資格を目指す上で、教育訓練給付制度は非常に心強い制度です。最大10万円の給付という金銭的な支援だけでなく、制度を活用すること自体が「計画的に学習を進める力」や「修了までやり抜く意識」を高めてくれます。
本記事でご紹介したように、制度にはいくつかの条件や手続きがあるものの、あらかじめ要件や流れを把握しておけば、決して難しいものではありません。
以下の3つのステップを踏むことで、制度のメリットを最大限に活かすことができます。
- 自分が制度の対象かを確認する(支給要件・被保険者期間)
- 給付対象の講座を比較・検討し、自分に合うものを選ぶ
- 修了条件や申請期限を把握し、計画的に学習を進める
制度の利用によって、経済的な不安を軽減しつつ、集中して学習に取り組める環境を整えることができます。特に独学では続けにくいという方にとっては、「制度+講座のサポート体制」が大きな支えとなるでしょう。