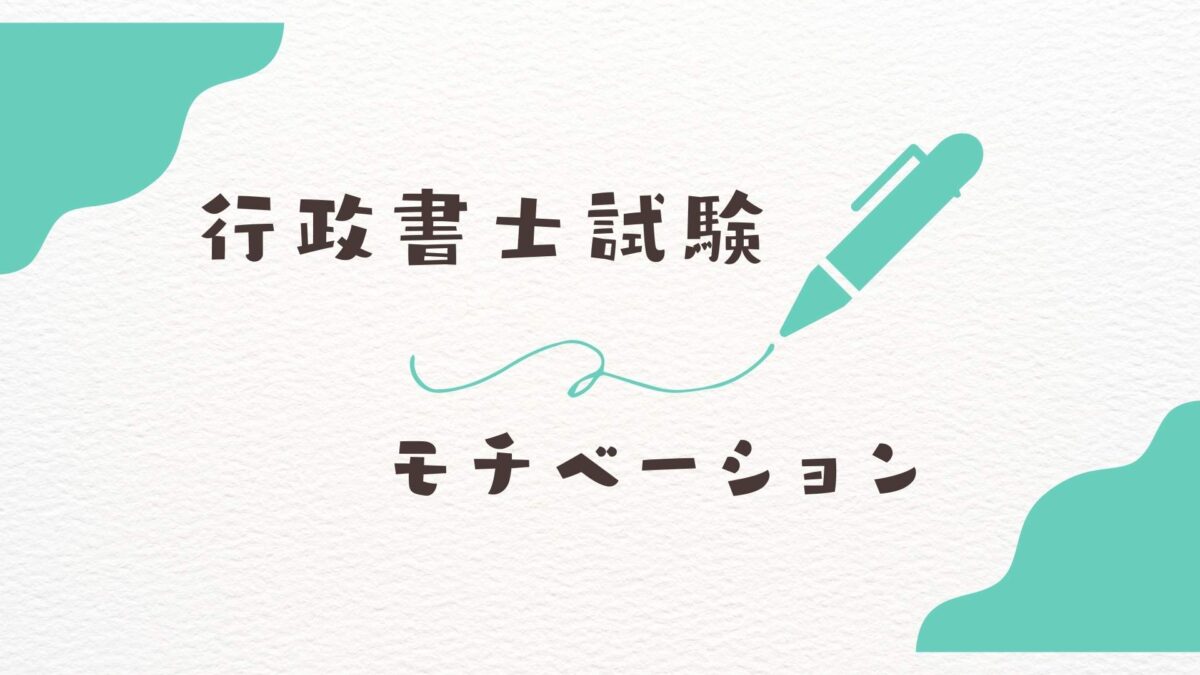行政書士を目指すあなたへ──不安を解消するQ&Aガイド
仕事に追われ、家庭を支えながら、それでも「行政書士になりたい」と志すあなたへ。
その一歩を踏み出すとき、多くの人が最初に感じるのは「この選択で本当に大丈夫だろうか?」という漠然とした不安や疑問です。実は、それはあなただけではありません。
このサイトは、私自身が社会人として、そして育児と両立しながら行政書士試験に挑み、2年の独学を経て合格した実体験をもとに作られています。遠回りと失敗を重ねたからこそ、いま「何に悩み、どこでつまずきやすいのか」が、手に取るようにわかります。
このページでは、その経験に加え、最新かつ信頼性の高いデータをもとに、受験生であれば一度は悩む疑問20選として一つずつ丁寧にお答えしていきます。
このQ&A集が、あなたの不安を解きほぐし、合格への道を一歩ずつ確実に進むための“羅針盤”となることを願っています。
第1部|試験の基本を知る:最初に押さえたい不安と素朴な疑問
Q1. 法律の勉強はまったく初めて。法学部出身じゃないと不利ですか?
A1. 確かに法学部出身者には一定のアドバンテージがありますが、合否を左右する決定的な要素ではありません。
法学部卒の受験生が有利なのは事実です。大学で民法・行政法・憲法などの主要科目に触れており、法律特有の用語や考え方に慣れているため、スタート時点での理解度に差が出るのは否めません。
しかし、それが合格を決める決定打になるわけではありません。実際、毎年多数の合格者が「法律完全未経験」からスタートしています。
むしろ初学者の方が、「なぜこのルールがあるのか」「この制度は何のために存在するのか」といった“目的志向”で学びやすく、本質理解が深まりやすいという側面もあります。
ただし注意すべきは、近年の受験環境の変化です。法科大学院修了生や司法試験経験者が「力試し」として行政書士試験を受験するケースが増え、全体のレベルが底上げされています。
行政書士試験は絶対評価で行われるため、他の受験生の出来にかかわらず基準点をクリアすれば合格できます。しかし、受験者の平均点が上がることで、問題の難易度自体が引き上げられる傾向も無視できません。
だからこそ、初学者にとっては「正しい順序と方法」に基づいた戦略的な学習が不可欠です。がむしゃらに読むだけでは、法律に親しんだ受験生との差が広がるばかりです。効率的かつ合理的な学習法を早期に確立することが、合格への第一歩となります。
Q2. 難関大出身でも落ちることがあるのはなぜ?
A2. 行政書士試験は「学力テスト」ではなく、「試験対策力」を問う実務型の資格試験だからです。
高学歴であっても行政書士試験に不合格となるケースは珍しくありません。その背景には、この試験ならではの「特殊な合格条件」があります。
行政書士試験では、知識の深さや学問的思考ではなく、
- 限られた範囲の法律知識を、
- 制限時間内に、
- 正確かつ実用的にアウトプットできるか
という、非常に現実的なスキルが求められます。
特に高学歴の受験生が陥りがちな失敗パターンは以下の通りです。
- 過信による戦略不足
「自分は地頭がいいから何とかなる」と思い込み、出題傾向や配点戦略を無視してしまう。 - インプット過多・アウトプット不足
知識を“読む”“聞く”に偏り、実際に問題を“解く”訓練が足りず、本番で機能しない。 - 独学での非効率な学習継続
自分のやり方に固執し、合格するための“型”や“セオリー”を理解しないまま走り続けてしまう。
この試験において重要なのは、「いかに効率よく得点できるか」という視点です。難しい問題を深く理解することよりも、「確実に取るべき問題を落とさない技術」が問われます。
合格する人は、試験の特性を把握し、それに特化した“勉強のルール”に沿って対策を重ねた人です。自分の頭の良さではなく、試験に合わせた合理的な準備ができたかどうかが、結果を分けます。
私自身も、学力には自信がありましたが、「合格の型」を知らなかった2年間は遠回りの連続でした。戦略を学び、必要な対策に集中した年に初めて合格をつかむことができました。
Q3. 暗記が苦手でも行政書士試験に合格できますか?
A3. はい、合格可能です。「丸暗記」ではなく「理解を伴う記憶」が求められる試験です。
「暗記が苦手で不安」という声は非常に多く寄せられますが、ご安心ください。行政書士試験は、電話帳のような条文を丸暗記する試験ではありません。
この試験で本当に求められるのは、
- ルールや制度の背景を理解する
- 「なぜこの規定があるのか」を納得する
- その理解をもとに記憶を定着させる
といった「意味のある記憶」です。
特に重要なのは、科目ごとに求められる記憶のスタイルが異なるという点です。
- 行政法
行政手続法や行政不服審査法など、制度の要件や手続きの流れが重要。繰り返し学ぶことで正確な記憶が点数に直結します。 - 民法
事例の中で条文をどう適用するかという“思考のトレーニング”が中心。丸暗記ではなく、理解を通じた応用力が問われます。
忘れて当然、という前提で、何度も「触れて」「戻って」「定着させる」。この反復プロセスを前提とした学習こそが、記憶が苦手な人にとって最も効果的です。
私自身も「暗記力には自信がないタイプ」でしたが、通信講座を通じて「覚える順序」や「定着させる仕組み」を学び、苦手意識を乗り越えることができました。やみくもな暗記ではなく、“科目に合った記憶戦略”を身につけることが、合格への近道です。
Q4. 記述式問題って結局「運」なんですか?採点が不透明で不安です…
A4. 「運ゲー」ではありません。記述式は“対策可能な技術”であり、しっかり取り組めば安定して得点できます。
「記述式は運しだいで点が変わる」──これは多くの受験生が抱える誤解の一つです。
確かに、記述問題の採点基準は公表されておらず、ブラックボックスに見える部分もあります。しかし、長年の出題傾向から導かれる共通点がいくつかあります。
採点の“実際”とは?
- キーワード重視の採点
法律用語や制度名など、採点上重要な“キーワード”を含めているかどうかで点数が加算されると推測されます。 - 部分点ありきの構造
満点を狙う必要はありません。60点満点のうち40点程度を確保する戦略で十分に合格可能です。 - 択一との連動性
記述式で問われる論点の多くは、過去に択一式で出題された内容やその応用です。記述はあくまで“択一知識の発展形”なのです。
対策のポイント
- 択一学習時に「なぜこの選択肢なのか」を説明できるようにする
- よく問われる条文や制度を“自分の言葉”で要約する練習をする
- 書く練習を通じて、キーワードを盛り込む力を養う
私自身も、記述式対策を「運まかせ」と思い込み、後回しにした結果、本番で痛い目を見ました。合格した年は、通信講座で「キーワード採点のロジック」や「想定問答のテンプレート」を学び、40点台後半を安定して出せるようになりました。
記述式は、闇ではなく、明確な技術です。正しい対策をすれば、再現性の高い得点源になります。
第2部|勉強法・学習戦略に関する疑問と対策
Q5. 勉強時間はどれくらい必要?「1000時間」は本当ですか?
A5. 「1000時間」はあくまで一つの目安。大切なのは“時間数”より“時間の使い方”です。
行政書士試験において、よく言われる「1000時間」という数字は、特に法律初学者が独学で合格を目指す場合の標準的な学習時間とされています。これを1年間で換算すると、1日あたり2〜3時間程度が目安となります。
ただし、これはあくまで目安にすぎません。
重要なのは、“量”ではなく“質”です。実際に、通信講座などを利用することで、学習の無駄や迷いを省き、500〜800時間程度に短縮して合格を果たす人も多くいます。
独学と講座で差がつく“見えない時間”とは?
独学では以下のような「学習以外の時間」がかかりがちです。
- 教材選びに悩む時間
- 学習計画を試行錯誤する時間
- 法改正や出題傾向を調べる時間
- モチベーションが落ちたときの立て直し時間
一方で、優れた講座では「何を・いつ・どの順番でやるか」が明確に設計されており、こうした“準備・迷い・停滞”にかかる時間を大幅に削減できます。
私自身も独学で2年かかりましたが、振り返れば「本当の意味で勉強していた時間」はその半分だったかもしれません。「学習の効率」を重視することで、あなたの時間的投資はぐっと小さくなります。
Q6. 勉強は何から始めるのが正解?
A6. 王道は「民法」からスタート。法律学習の土台を固めることが最優先です。
学習初期の最大の悩みが「どこから手をつけるか」。その問いに対する専門家の共通した答えが「民法から始める」というものです。
民法スタートが合理的な理由
- 法律の基礎的な考え方(リーガルマインド)を身につけやすい
- 行政法との共通概念が多く、応用が利く
- 76点と高配点で、合否を左右する重要科目
憲法から始めるという選択肢もありますが、より抽象度が高いため、法律の枠組みに慣れていない段階では難解に感じやすい傾向があります。
さらに重要なのは、「インプットとアウトプットを並行する」こと。多くの初心者が「テキストを一通り読んでから問題を解こう」と考えがちですが、これは大きな遠回りです。
最短効率の「ジグザグ学習法」
- テキストで1テーマを学ぶ(例:意思表示)
- すぐにそのテーマの過去問を1問解く
- 間違えても構わない。解説を読み、もう一度テキストを確認する
この“往復運動”によって、知識が血肉となっていきます。
私が初学者だった頃は、民法を「完璧に理解するまで進まない」と決めてしまい、1問も解かないまま数ヶ月を浪費しました。合格した年は、講義→演習の反復を徹底し、圧倒的に早く力がついた実感がありました。
Q7. 「捨て科目」を作ってもいい?商法・会社法はやらなくてもOK?
A7. 「捨てる」ではなく「絞る」が正解。限られた時間を活かす戦略的判断です。
行政書士試験は出題範囲が広く、すべての科目を完璧にこなすのは現実的ではありません。そこでよく議論になるのが、「商法・会社法を捨ててもいいのか?」という問題です。
確かに、商法・会社法は条文数が多く内容も複雑なわりに、出題は5問(20点)のみ。学習コストに対して得点効率が低く、“費用対効果の悪い科目”とされています。
合格者に共通する戦略は「部分得点主義」
- 商法総則・商行為
- 会社法の「設立」「株式」など、頻出で比較的理解しやすい分野
このあたりに絞って2〜3問を確保し、残りの時間を配点の高い民法や行政法に回す、というのが王道です。
「本当に捨てていい科目」は存在しない
一方で、民法・行政法は合計で全体の6割近くの配点を占める“最重要科目”。これらを「捨てる」のは、合格そのものを捨てるのと同義です。
私も独学時代、「捨てるか?やるか?」の判断に時間を浪費し、結局全部やろうとして中途半端に終わった経験があります。講座を活用した年は、「この分野は捨て、この分野は拾う」という明確な指示があり、迷いなく得点に集中できました。
「捨てる勇気」と「拾う判断基準」を持つことが、合格者の共通点です。
Q8. 過去問はいつから始める?何年分解けばいい?
A8. 学習開始と同時に始めるのが正解。最低5年分、できれば10年分を“分析重視”で使い倒しましょう。
「過去問はテキストを一周してから…」という声をよく聞きますが、それは大きな誤解です。正しい使い方は、テキスト学習と並行して、早い段階から少しずつ取り組むことです。
最低ラインと理想の目安
- 最低でも直近5年分
- 可能であれば10年分
繰り返し出題される「頻出論点」や出題パターンを体感するには、10年分をじっくり使い込むのが理想です。
単なる“演習”ではなく“分析”が命
合格者の多くは、以下のような視点で過去問を徹底的に活用しています。
- なぜこの選択肢が正解なのか
- なぜ他の選択肢は誤りなのか
- その根拠となる条文や判例は何か
つまり、1問で5つの選択肢を“教材”として吸収する意識です。解いて終わりではなく、「しゃぶり尽くす」ことが重要です。
私自身、1年目は過去問を“模試感覚”で使ってしまい、成績が伸び悩みました。2年目に「分析ツール」として活用する視点に切り替えたことで、得点力が一気に上がったのを実感しました。
Q9. 記述式対策はいつから?どうやって始めるべき?
A9. 択一の土台が固まったら着手。8〜9月ごろから「キーワード重視の書き方」を練習しましょう。
記述式問題は60点満点と配点が高く、得点源にも鬼門にもなり得ます。とはいえ、最初から取り組む必要はありません。まずは択一式(特に民法・行政法)の基礎力をしっかり固めるのが先決です。
着手の目安時期
- 択一の基本論点が概ね理解できた段階
- 学習開始から半年後〜8月ごろが目安(1年計画の場合)
効果的な取り組み方
- 問題と模範解答を読み込む(インプット)
最初は自分で書かず、出題の意図と模範解答の構成・キーワードを確認する。 - 40字程度の「要素を盛り込む練習」
完璧な文章よりも、出題の趣旨に沿って法律用語や制度名などの“キーワード”を正確に入れる練習をする。 - 自分の答案に客観的フィードバックをもらう
独学では難しい「採点基準とのズレ」に気づくためには、通信講座や添削サービスの活用が効果的です。
私も記述式を「なんとなく書ければOK」と思っていた時期がありました。しかし、得点できなかった原因は「キーワードの欠落」と「問いに正面から答えていない構成」だったと、後から気づきました。戦略的に取り組めば、記述は合格を引き寄せる最大の武器になります。
Q10. 六法って必要?おすすめはありますか?
A10. 必須ではありませんが、あると大きな武器になります。選ぶなら“行政書士専用の六法”一択です。
テキストにも条文は掲載されているため、「六法がないと受からない」ということはありません。ただし、合格者の多くは六法を使いこなし、知識の整理と理解を深めています。
六法を使う3つのメリット
- 条文の正確な確認ができる
テキストは解説中心。条文そのものの文言は六法でこそ正確に確認できます。 - 前後条文の関連性をつかめる
1つの条文を調べた際に、前後の流れや制度全体の構造も見えてきます。 - 記憶の定着に効果的
「自分で条文を引く」=能動的な学習になるため、理解も記憶も深まります。
おすすめの六法は?
- 普段使い・持ち歩き用
→ 三省堂『ケータイ行政書士 ミニマム六法』:軽量・コンパクトでスキマ時間学習に◎ - じっくり学習用(判例付き)
→ 早稲田経営出版『行政書士試験六法』:判例の要旨も掲載され、応用的な理解に◎
私自身、六法を持たずにテキストだけで学習していた時期は、条文理解が浅く、応用問題に対応できませんでした。六法を「辞書」ではなく「理解を深める道具」として活用できれば、学習の質は大きく変わります。
Q11. 模試は本当に必要?E判定でも落ち込まなくていい?
A11. 模試は“絶対に受けるべき”です。そしてE判定は落ち込む材料ではなく、“改善点を可視化するツール”です。
行政書士試験の模試は、単なる腕試しではありません。むしろ、本番の3時間という長丁場に慣れ、弱点を客観的に把握するための「戦略ツール」として活用すべき存在です。
模試を受けるべき理由は3つ
- 時間配分の体得
3時間で択一・多肢選択・記述を解き切る感覚を、本番前に経験しておくことは極めて重要です。 - 弱点の“見える化”
得点できていない分野や、思わぬミスの傾向が明確になります。 - 本番の雰囲気に慣れる
試験会場特有の緊張感や集中力の持続にも慣れておくと安心です。
大手予備校(TAC・LEC・伊藤塾など)が開催する模試を、最低2〜3回は受験するのが理想です。
E判定をどう受け止めるか?
- 落ち込む必要はありません
特に初期段階の模試で高得点を取れる受験生は稀です。 - 無視するのはNGです
「模試は模試だから」とスルーするのは最大の損失です。 - やるべきことは“分析”です
間違えた原因を細かく分析し、何を補強すべきかを特定しましょう。
私自身、模試でE判定を取ったとき、「やっぱり無理かも…」と落ち込んだ経験があります。しかし、模試の解説講義で出題者の意図や解法を学び直したことで、本番の得点力は劇的に上がりました。模試は、“点数を取る場”ではなく“合格の精度を高める場”なのです。
Q12. テキストの読み方やノートの取り方に正解はありますか?
A12. “まとめノート”は不要です。テキストにすべてを集約する「一元化学習」が最も効率的です。
多くの受験生が陥りがちな罠、それが「綺麗なノートを作ることが目的化してしまう」ことです。一見、勉強しているように見えて、実は情報を複製しているだけの非効率な作業になっていることもあります。
非効率なノート術の例
- テキストの内容をそのまま書き写す
- 自作の図や枠で“見栄え重視”のノートを作る
- 復習時に結局テキストとノートを行ったり来たりしてしまう
合格者が実践する効率的な方法
- 基本テキストにすべての情報を“書き足していく”
過去問の解説、講義のメモ、ゴロ合わせ、自分なりの気づき──すべてをテキストの余白に記入し、「あなただけの参考書」に仕上げます。 - 唯一の例外:「間違いノート」は作る価値あり
何度も間違える論点・知識だけをピックアップして作る「弱点特化ノート」は、直前期の最強アイテムになります。 - 復習の効率を最優先に設計
テキストを1冊、徹底的に使い倒すことが、記憶の再現性と理解の深さにつながります。
私も以前は何冊も「綺麗なノート」を作って満足していましたが、振り返れば、その労力のほとんどは合格に直結していませんでした。最終的にボロボロになるまで使い込んだ1冊のテキストこそが、合格の礎となったのです。
第3部|両立・モチベ維持・学習環境に関する悩み
Q13. 仕事や育児と勉強を両立するにはどうしたらいい?
A13. 「まとまった時間」を探すのではなく、「スキマ時間」を仕組み化し、生活に勉強を組み込むことがカギです。
仕事、家事、育児…。忙しい日常の中で、「勉強時間をどう確保するか」は最大の課題です。
多くの方が「まとまった静かな時間が必要」と考えがちですが、実際にはその時間はほとんどやってきません。だからこそ、“スキマ時間の積み重ね”こそが最大の武器になります。
両立を成功させる3つの具体策
- 朝活・夜活の活用
家族が寝ている時間帯(早朝 or 深夜)を“固定の学習時間”として確保する。 - 細切れ時間の有効活用
- 通勤電車 → 過去問アプリで10問解く
- 昼休み → 音声講義を1本聴く
- 5分の隙間 → 条文カードを見る など
- 家事の時短と外注の工夫
食洗機や掃除ロボットの導入、週末の一時保育など、時間を「生み出す工夫」を積極的に取り入れる。
私自身、子どもが小さい中での学習は、決して“まとまった時間”で進んだわけではありません。むしろ、日々の15分〜30分の積み重ねが、試験直前には大きな差を生んでくれました。
Q14. モチベーションが下がったときはどうすればいい?
A14. 落ち込むのは当然です。休む勇気と“原点回帰”が、再起の第一歩になります。
試験勉強は長期戦です。常にやる気満々の人など存在しません。誰もが途中で不安や倦怠感に襲われます。それは“意志が弱い”のではなく、人間として自然な反応です。
やってはいけないNG行動
- 「気合いで乗り切る」と無理をする
- 気分転換の名目で新しい教材に飛びつく
- 自分を責めて自己肯定感を下げる
回復のための処方箋
- 思い切って休む
「今日は完全オフ」と決めて、リフレッシュすることで、逆に回復が早まります。 - 原点に立ち返る
「なぜ行政書士を目指したのか?」を思い出す。未来の自分の姿を具体的に想像するのも有効です。 - ハードルを極限まで下げる
「今日は10分だけ」「1問だけ」など、小さな行動を再開のきっかけに。 - 誰かに話す・共有する
勉強仲間や家族に正直な気持ちを打ち明けることで、視点が変わり心が軽くなることもあります。
私も、何度も「やめようか」と思いました。そんなとき救われたのは、“一緒に頑張る仲間の存在”と、“合格後の自分”を思い描くことでした。モチベーションは「意志の力」でなく、「構造の力」で支えるものなのです。
Q15. 家族の理解と協力を得るにはどう伝えればいい?
A15. 「想い」「方法」「必要な協力」を言語化して共有し、日々の行動で“本気度”を示すことが最善の近道です。
資格取得には家族の協力が不可欠です。しかし、ただ「勉強したい」と伝えるだけでは、なかなか理解は得られません。ポイントは、「感情」だけでなく「論理的説明」と「具体的配慮」をセットで伝えることです。
家族の協力を得る3ステップ
- Why:なぜ行政書士を目指すのかを伝える
キャリアアップ、収入増、自己実現──あなたの本気の想いを、丁寧に言葉にして伝えましょう。 - How:家族への影響を最小限にする工夫を示す
「朝5時〜7時に勉強するから、夜は一緒に過ごす」など、家族の生活リズムを尊重する姿勢を見せます。 - What:費用・時間・必要な協力を具体的に説明する
教材費・講座費・勉強に必要な時間などを共有し、事前に了承を得ておくことが信頼を築きます。
そして何より大事なのは、日々の積み重ねこそが最大の説得力になるということです。
言葉以上に、毎朝決まった時間に机に向かうあなたの姿を見たとき、家族は次第に応援者に変わっていきます。私自身、最初は無関心だった家族が、最終的に誰よりも支えてくれる存在になった経験があります。
第4部|教材・ツール・デジタル活用に関するQ&A
Q16. 独学と通信講座、どちらを選ぶべき?
A16. 「時間」「自己管理能力」「不合格リスク」の3点で考えれば、最適な選択が見えてきます。
行政書士試験において、独学と通信講座のどちらを選ぶべきかは、受験生一人ひとりの状況によって異なります。ただし、判断の軸を明確にすれば、後悔のない選択ができます。
独学の特徴
- メリット
- 低コスト(市販テキストと問題集で2万円前後から可能)
- 自分のペースで進められる自由度 - デメリット
- 教材選び・計画立案・法改正対応などをすべて自己完結しなければならない
- モチベーションの維持や疑問の解消が難しく、挫折率が高くなりやすい
通信講座の特徴
- メリット
- カリキュラム・教材・講義・質問制度など、合格に最適化された仕組みが整っている
- 法改正・出題傾向の最新情報に即応できる
- スケジューリング・進捗管理・仲間との交流などで継続しやすい - デメリット
- 一定の費用(5万~20万円前後)が必要
判断のポイント
- 「限られた時間をどう使うか」
- 「不合格になった場合の損失をどう見るか」
時間換算すると、独学(1000時間)と通信講座(500~800時間)の差は数百時間。これは、費用以上に大きな“時間的損失”につながる可能性があります。
私も2年かけて独学で合格しましたが、今振り返ると、通信講座を活用していれば1年早く合格できていたと思います。つまり、「時間」を買う投資と捉えることができれば、講座の価値は十分に元が取れます。
Q17. 行政書士試験の勉強に役立つアプリやサイトはありますか?
A17. あります。スキマ時間を“得点力”に変える強力な補助ツールとして活用しましょう。
忙しい社会人・子育て世代にとって、スマホやタブレットを活用したスキマ学習は非常に効果的です。以下は、受験生に支持されている主要アプリ・サイトです。
おすすめアプリ・サイト
- 行政書士 過去問アプリ(2025年版)
→ 一問一答形式で手軽に演習できる定番アプリ。無料版でも十分使えます。 - 予備校公式アプリ(TAC、伊藤塾、資格スクエアなど)
→ 有料受講者向けの機能付き。動画・テキスト連携・進捗管理なども便利。 - 合格道場(Webサイト)
→ 過去問・オリジナル問題を大量に解ける老舗サイト。無料で質も高い。 - 行政書士試験研究センター(公式)
→ 出題実績と正解データが公表されている一次情報サイト。 - Studyplus(学習記録アプリ)
→ 勉強時間の可視化、仲間とのSNS連携でモチベーション維持に役立つ。
活用のコツ
アプリやWebツールは“主教材”ではなく“補助教材”と割り切って使うのがコツです。メインの学習(講義・テキスト・演習)をしっかり行い、その補強・定着にアプリを組み合わせることで、効率が最大化されます。
Q18. iPadやタブレットでの学習は効果的ですか?
A18. 非常に効果的です。正しく使えば、紙ではできない高度な学習が実現できます。
iPadなどのタブレット端末は、行政書士試験のような情報量の多い試験において、学習の柔軟性と効率性を飛躍的に高めるツールです。
デジタル学習のメリット
- 軽量・多機能でどこでも勉強可能
→ テキスト・過去問・講義動画が1台に集約。カバンも頭もスッキリ。 - 検索性と可視化の強さ
→ 条文や用語をすぐに検索。紙では不可能なスピードで確認が可能。 - 高度な学習ワークフロー
→ 画面を2分割しながら、講義を見てメモを取る/PDFに直接書き込むなど多様な学習が実現。
必須アプリ例
- GoodNotes 5
→ 手書きノートアプリの定番。なめらかな書き心地と整理機能が優秀。 - Adobe Scan
→ 紙の教材をその場でPDF化。自作教材のデジタル管理に便利。 - Notability / Kindle / PDF Expert なども用途に応じて活用可能。
注意点
本試験は「紙」で実施されるため、直前期には紙の模試・記述演習を使い、現場対応力を養うことが必要です。
私も紙教材派でしたが、iPad導入後は「どこでも講義→即復習→即書き込み」ができるようになり、格段に学習効率が上がりました。デジタルはあくまで“道具”。うまく使えば、あなたの時間を何倍にも活かすパートナーになります。
第5部|試験後の心構えと再スタートへの備え
Q19. 解答速報はどこまで信用できる?自己採点はどう活用すべき?
A19. 信頼性は高いが、“正確な合否判定”ではない点を理解した上で活用することが大切です。
行政書士試験では、本試験終了後すぐに大手予備校(LEC・TAC・伊藤塾など)が「解答速報」を公開します。これらは長年の分析実績にもとづいた精度の高い速報であり、自己採点に十分活用できます。
解答速報の精度と注意点
- 法令科目の五肢択一式・多肢選択式・記述式の模範解答を各校が独自に作成
- 選択肢ごとの根拠や出題意図も丁寧に解説されているため、自己分析にも有用
- ただし、正式な正解と異なる可能性がゼロではないため、最終判断は慎重に
特に記述式問題(20点×3問)については、「部分点がどの程度もらえるか」は自己採点では正確に測れません。そのため、合否ライン(180点)前後の人は“最終結果が出るまでわからない”という前提で受け止めるのが賢明です。
自己採点の活用法
- 次の行動判断の参考にする(講座申込・教材購入・学習計画など)
- 得点戦略の振り返り資料として保存する
- 記述の再現答案はできる限り正確に記録しておく(今後の参考・講師添削依頼用)
Q20. 不合格だったとき、まず何から始めればいい?
A20. “敗因分析”と“戦略の再設計”が再挑戦への第一歩です。感情ではなく、論理で動きましょう。
行政書士試験は、1回で合格できる人よりも、複数年にわたって挑戦し合格を勝ち取る人の方が多いのが実情です。不合格という結果を前向きな材料に変えるためには、「感情」ではなく「分析」で次の一手を決めることが重要です。
再スタートのステップ
- 自己採点の結果を冷静に振り返る
- 合格ラインとの点差は?
- 科目別の得点バランスは?
- 記述の再現答案と講評の比較 - 敗因の可視化
- 時間不足、暗記の定着不良、過去問演習不足、基礎理解の浅さなど
- 「わかっていたのに解けなかった」の原因は何かを明確にする - 新たな戦略の構築
- 学習リソースの見直し(講座受講の検討含む)
- スケジュールの再設計(仕事・家庭とのバランスも含めて)
モチベーションの保ち方
- 「不合格=失敗」ではありません。「不合格=材料の不足」です。
- あなたの努力はすでに“合格に近づく土台”を築いています。
- 来年の合格に向けた準備は、今日から始まっています。
心が折れそうになったら、「あと1点で届く人」が何千人もいる試験だという事実を思い出してください。その1点を取りに行く準備を、ここから始めましょう。
おわりに|あなたの挑戦は、確実に合格への道を切り拓いている
行政書士試験は、「努力すれば必ず報われる」タイプの国家試験です。学歴や年齢、職歴にかかわらず、正しい戦略と継続的な努力を積み重ねた人に合格のチャンスが与えられます。
試験制度の特性を理解し、自分に合った学習法を見つけること。そして、限られた時間とエネルギーを「本当に効果のあること」に集中させること。それが合格までの“最短ルート”です。
不安になる日もあるかもしれません。周囲と比較して自信をなくすこともあるでしょう。それでも、あなたが「合格したい」と願い、行動を積み重ねている限り、その挑戦は無駄になりません。
このガイドが、あなたの挑戦に確かな方向性と安心感を与える一助となれば幸いです。
合格後の未来を見据えて、今日の一歩を大切にしてください。

行政書士試験徹底解説
行政書士試験の完全攻略ガイド|ゼロから始める社会人のための難易度・勉強法・合格ロードマップ