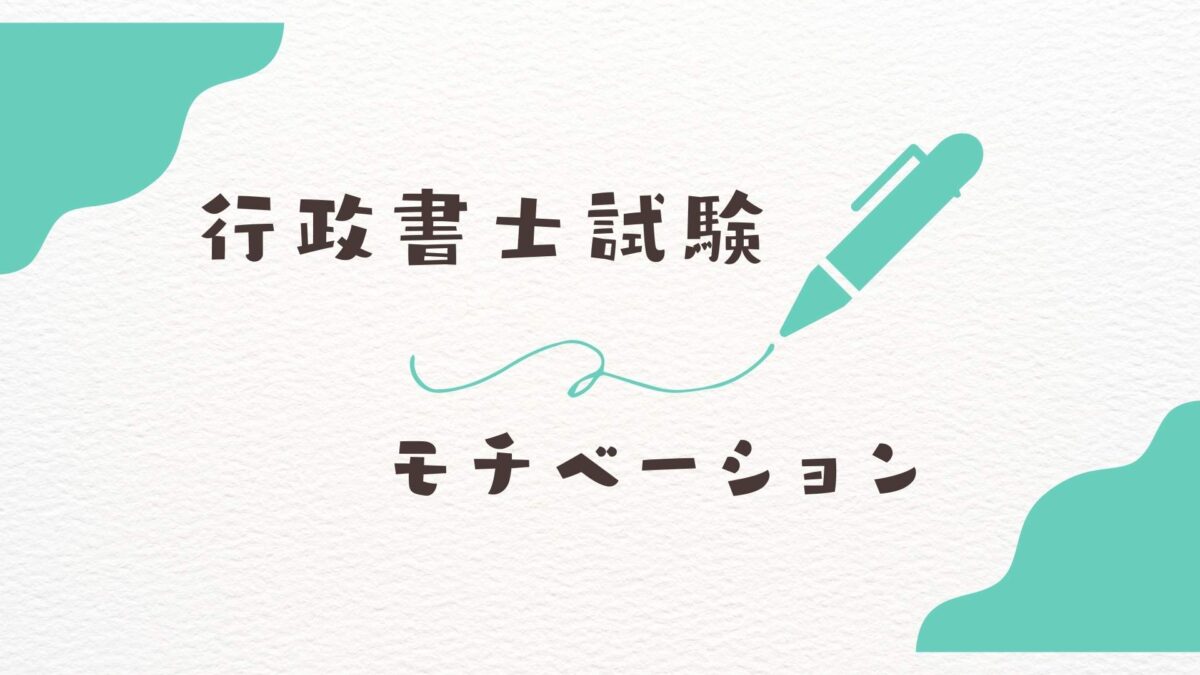「行政書士はやめとけ」と言われる理由を、正面から見つめる
行政書士を目指す過程で、多くの受験生が一度は目にするのが「行政書士はやめとけ」「稼げない」「将来性がない」といった否定的な言葉です。SNS、ブログ、掲示板などネット上には、資格取得をためらわせるような情報が溢れています。
こうした言説が多くの人に不安を与えているのは事実です。しかし、それらの主張は果たしてどれほど信頼に値するのでしょうか?
本記事では、日本行政書士会連合会(日行連)や総務省などの公的統計、民間の信頼性ある調査レポート、そして現役の行政書士としての実務経験も交えながら、巷にあふれる“ネガティブ評価”を多角的に検証していきます。
私たちがここで問いかけたいのは、
「行政書士は本当に“やめとけ”と言われるような資格なのか?」
それとも
「取り組み方次第で、大きな可能性を秘めた資格なのか?」
という根本的なテーマです。
その答えを導くために、本記事では以下の観点から深掘りしていきます:
- 「やめとけ」言説の構造と論拠
- 行政書士市場の実態(登録者数・廃業率・市場規模)
- 収入の実情と成功事例
- AI時代における職域の変化
- 法改正がもたらす未来の展望
- 成功する行政書士の共通点とキャリア戦略
この記事が、感情や噂に振り回されず、自分の人生にとって合理的で戦略的な判断を下すための材料となることを願っています。
第1章|なぜ「やめとけ」と言われるのか?ネットに広がる評価の構造を読み解く
1.1|拡散されやすいのはどんな声?ネット上の発信メディアと傾向
「行政書士はやめとけ」「食えない」「将来性がない」──こうしたネガティブな言葉は、主に個人ブログ、X(旧Twitter)などのSNS、そして匿名掲示板などで多く見られます。
これらの発信源では、統計や客観的な分析よりも、個人の体験談や感情が重視されやすい傾向があります。中でも「うまくいかなかった」「思っていたより厳しかった」といった失敗談や後悔の声は、共感を呼びやすく、拡散されやすいという特性があります。
実際に取り上げられるネガティブな論点は、以下のようなパターンに集約されます:
- 行政書士の数が多く競争が激しい(=市場が飽和している)
- 収入が安定しない、または低い
- 書類作成業務がAIに取って代わられる
- 営業力がないと仕事にならない
- 求人が少なく、就職に直結しない
こうした意見は、たしかに一部の現実を反映している側面もあります。しかし、その多くは特定の環境や状況における体験に基づいたもので、必ずしも行政書士という職業全体を公平に評価したものとは限りません。
1.2|「行政書士はやめとけ」論を支える4つの主張──その裏にある誤解とは?
ネット上の議論を丁寧に分析すると、「行政書士はやめとけ」とされる理由は、大きく次の4つに分類されます。
1. 市場がすでに飽和している
行政書士の登録者が多すぎて、新しく始めても仕事を取れない、という声です。競争が激しいという現実はありますが、それが即「飽和」を意味するわけではありません。
2. 食えない・収入が低い
行政書士の年収は低く、特に資格手当程度にしかならないケースもあるため「生活が成り立たない」と言われます。しかし実際は、平均年収や売上の分布には大きな幅があり、収入の二極化が起きていることが後の章で明らかになります。
3. AIに代替される職業である
「書類作成はAIでできるようになり、行政書士の仕事は不要になる」という未来予測です。確かに定型業務はAIの得意分野ですが、行政書士の真の価値は、依頼者との信頼関係や状況に応じた解決力といった、人間ならではの対応力にあります。
4. 営業・集客が難しく、資格だけでは通用しない
行政書士の業務は待っていても来ない、自ら営業して仕事を取りに行かなければならない、という現実があります。これは事実ですが、行政書士が「士業」であると同時に「事業者」でもあるという点を理解していれば、むしろ当然の前提です。
これらの主張の多くは、行政書士という資格そのものを否定するものというより、「準備不足のまま開業した結果としての失敗体験」が原因です。
資格取得後すぐに独立できるという参入のしやすさは、裏を返せば、実務スキル・経営力・集客力を備えないまま開業してしまうリスクもあるということ。
つまり「やめとけ」という声の多くは、資格そのものの問題ではなく、事業としての準備不足による失敗を映し出しているのです。
その構造を理解することが、資格の「本当の価値」を見極める第一歩となります。
第2章|本当に「飽和状態」なのか?行政書士市場の実情をデータで読み解く
2.1|登録者数の増加と人口比──「多すぎる」は本当か?
「行政書士は多すぎて仕事がない」とよく言われますが、実際の登録者数はどの程度なのでしょうか?
日本行政書士会連合会(日行連)の統計によると、登録者数は2015年時点で約44,740人。それが2024年には52,953人と、約10年で8,000人以上の増加となっています。
一見すると「増えすぎ」と思われがちですが、重要なのはその“割合”です。たとえば2024年現在、行政書士1人あたりの日本人口は約3,177人。これを他士業(例:司法書士・税理士など)と比較すると、決して突出して多いわけではありません。
つまり、登録者数の絶対数だけを見て「飽和している」と断じるのは早計です。真に問うべきは、「需要に対して供給が過剰かどうか」という市場バランスの視点なのです。
2.2|「廃業率9割」の都市伝説──統計的に正しい見方とは?
インターネットではしばしば、「行政書士は5年以内に9割が廃業する」といった極端な意見を目にします。しかしこの数字、実は正確ではありません。
たとえば令和4年度(2022年度)の実績を見ると:
- 年間の廃業者数:1,592人
- 年度内の総登録者数(=期首登録数+新規登録者数):50,286人+2,713人=52,999人
- 廃業率:1,592 ÷ 52,999 ≒ 約3.0%
同様に、令和5年度は約4.4%、令和3年度でも約3.8%と、いずれも日本の中小企業平均の廃業率(おおむね年3〜4%)と同水準であり、「特別に廃業しやすい資格業」とは言えません。
では、なぜ「5年で9割廃業」などという誤解が広まってしまったのか?
その理由は、【新規登録者数と廃業者数】を“同年度内で”単純に比較してしまうという、統計的に誤った計算方法にあります。
たとえば、ある年に新規登録が2,687人で、同じ年に廃業者が1,881人いた場合、
1,881 ÷ 2,687 ≒ 約0.70(≒7割)
という見せ方ができてしまいます。しかしこれは、「今登録した人がすぐに廃業した」わけではなく、全く別の世代の数字です。信頼できる統計は、常に【全体数】に対する割合で評価する必要があります。
2.3|市場は縮小していない──拡大する業界規模と売上の傾向
もう一つ重要なのは、市場そのものの成長性です。行政書士という職業が“食えない”という前提が成立するには、業界全体の売上が停滞または減少している必要があります。
ところが、総務省の「経済センサス(活動調査)」によると、行政書士事務所全体の年間売上は以下のように推移しています:
- 2012年:約300億円
- 2021年:約622.6億円
10年足らずで、業界全体の売上が2倍以上に成長しているという明確なデータが示されています。
さらに、行政書士1人あたりの平均売上も上昇傾向にあり、2012年の約350万円から、2021年には約465万円にまで増加しています。
補足データ|行政書士業界の登録者数と市場規模の推移(2012年〜2024年)
| 調査年 | 登録者数(年度初/末) | 新規登録者数 | 廃業者数 | 年間廃業率(概算) | 業界全体の売上高 | 一人あたり平均売上高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012年 | 約42,177人 | ― | ― | ― | 約300億円 | 約350万円 |
| 2015年 | 約44,740人 | 2,490人 | ― | ― | ― | ― |
| 2016年 | ― | ― | ― | ― | 約400億円 | 約400万円 |
| 2021年 | 約49,480人 | 2,687人 | 1,881人 | 約3.8% | 約622.6億円 | 約465万円 |
| 2022年 | 約50,286人 | 2,713人 | 1,592人 | 約3.0% | ― | ― |
| 2023年 | ― | ― | 2,330人 | 約4.4% | ― | ― |
| 2024年 | 約52,953人(推定) | ― | ― | ― | ― | ― |
出典:日本行政書士会連合会、総務省経済センサス(※数値は各年の公開資料および統計に基づく)
この表から読み取れるのは、
- 登録者数が年々増えている一方で、廃業率は約3〜4%台で安定
- 業界の売上規模は過去10年で2倍以上に成長
- 一人あたりの売上も上昇傾向
というポジティブな実態です。単に「数が増えている」ではなく、「業界全体が拡大し続けている」点に注目すべきです。
これらのデータが物語るのは、
「市場が縮小しているのではなく、むしろ成長している」
という事実です。
ただし、登録者数も同時に増えているため、「競争は確実に激化している」という点は見逃せません。
つまり、仕事がないのではなく、仕事を“選ばれる立場”として獲得できるかどうか──その競争力が問われているのです。
結論として、「行政書士市場は飽和している」という言説は、統計的には根拠に乏しいといえます。
実態は、競争が激しくなっている成長市場であり、「成功できるかどうか」は、資格取得の先にある“戦略”と“差別化”にかかっているのです。
第3章|行政書士は本当に「食えない」のか?収入のリアルを戦略的に読み解く
3.1|平均年収と中央値──数字の“落とし穴”に要注意
行政書士の収入に関する情報には、大きなばらつきがあります。
まず平均年収を見てみると:
- 厚生労働省「job tag」(令和5年):約551.4万円
- 民間調査(MS-Japan調べ・2024年):約586万円
これだけを見ると「思ったより悪くない」という印象を持たれるかもしれません。
しかし一方で、中央値(年収を低い順に並べた中間の値)は400〜450万円程度と推定されており、平均と中央値に100万円以上の差があるという現象が起きています。
これはどういうことかというと、ごく一部の高収入層が全体の平均を引き上げていることを示しています。実際、日行連のアンケート結果からは以下のような分布が読み取れます:
- 年間売上500万円未満:全体の約8割
- 500万〜1,000万円未満:約11%
- 1,000万円以上:約10%
つまり、「食える人もいれば、苦戦している人もいる」というのが実情です。
3.2|開業初期〜5年後までの収入カーブ
独立開業した行政書士が、どのような収入の軌跡を描くか──これは非常に現実的かつ重要な問いです。
開業1年目
- 売上200〜300万円前後が一つの現実的なライン。
- 顧客ゼロ・人脈ゼロからのスタートが多く、最初の数ヶ月は“収入ゼロ”も珍しくない。
- 500万円以上を初年度で達成するのは、ごく一部の営業力や人脈に恵まれた例外的ケース。
開業2〜3年目
- 口コミや紹介によって顧客数が安定しはじめ、売上が2〜3倍に伸びる例も多い。
- ある程度の専門分野が定まり、業務効率も上がってくる。
開業5年目以降
- 基盤が整い、「自動的に仕事が入ってくる」フェーズに入る人も出てくる。
- この時点で年収1,000万円を超える層に入る人もいれば、依然として年収300〜400万円で停滞する人もおり、ここで「二極化」が顕著になります。
このように、収入の推移は単なる年数ではなく「どんな戦略をとるか」によって大きく左右されます。
3.3|高収入を実現する鍵は「専門分野」と「単価設定」にあり
年収1,000万円以上を達成する行政書士は、例外ではありません。
彼らの多くに共通しているのが、高単価で専門性の高い業務分野に特化しているという点です。
以下は、行政書士の代表的な高単価業務と報酬の目安です(※日行連「令和2年度報酬額統計調査」等に基づく):
| 業務分野 | 具体業務 | 平均報酬 | 最大報酬(報告事例) | 特徴・戦略のポイント |
|---|---|---|---|---|
| 国際業務(入管) | 帰化許可申請 | 約17.8万円 | 約50万円 | 専門性・語学力が必要。外国人支援との相性も良好 |
| 建設業許可 | 新規許可(法人) | 約13.7万円 | 約35万円 | 継続案件(決算変更・経審)につながりやすい |
| 相続・遺言 | 遺言執行 | 約38万円 | 約500万円 | 丁寧な対応と信頼構築が鍵。リピート性高い |
| 補助金支援 | 事業再構築補助金など | 成功報酬(採択額の10〜15%) | 案件ごとに変動 | 事業計画力と中小企業支援スキルが問われる |
| 風俗営業許可 | 営業許可申請 | 約16万円〜 | ケースにより個別設定 | 手続きが煩雑で専門性が高く、競合が少ない |
こうした業務に共通するのは、「単発で終わらず、継続や顧問契約に発展しやすい」「他士業との連携が取りやすい」「価格競争に巻き込まれにくい」という特徴です。
結論として、「行政書士は食えるか?」という問いに対する答えは、「資格をどう活かすか」に尽きます。
収入の差は、環境や運ではなく、選ぶ分野・売り方・専門性の磨き方で決まるのです。
第4章|AI時代に問われる「人間行政書士」の真価とは?
ChatGPTをはじめとする生成AIの急速な進化により、「行政書士の仕事はAIに奪われるのでは?」という声も少なくありません。
実際、書類作成の自動化や法務リサーチの効率化が進むなかで、業務のあり方が問われているのは事実です。
では、行政書士という仕事の本質は、どこにあるのでしょうか?
ここでは、AIが得意とする分野と、AIには決して代替できない“人間行政書士”の強み、そして先進的な事務所の活用事例を通じて、未来の行政書士像を探ります。
4.1|AIで自動化される仕事、されない仕事
行政書士の業務の中で、AIによる代替が進みやすい領域は次のようなものです:
- 定型的な書類作成
申請書や届出書など、フォーマットに従った記載が中心の文書。
生成AIは入力情報に基づき、高速かつ正確にドラフトを作成可能です。 - 法令や判例のリサーチ
膨大な情報を瞬時に検索・要約する力に優れています。 - 形式的な誤字脱字チェックや文章校正
細かな文法エラーの自動検出なども、AIが得意とする作業です。
こうした領域では、AIを活用することで、従来よりも圧倒的に時間とコストを削減することが可能になります。
一方で、「行政書士業務の9割以上がAIで代替可能」とする一部の研究は、業務を“単純作業の寄せ集め”と捉えた極端な見方であり、実務の本質を捉えているとは言えません。
4.2|AIにはできない「人間行政書士」の役割とは?
行政書士が本当に担っているのは、単なる“代書”ではなく、以下のような高度かつ繊細な専門対応です。
- コンサルティング力と課題解決力
顧客の置かれた背景・法的立場・目的に応じて、最適な手続を選定し、スケジュールや関係先との調整を含めて伴走する力は、人間ならではの専門技術です。 - 信頼関係の構築と感情的ケア
相続・許認可・家族や企業の将来設計など、人生の転機に関わる場面では、依頼者の感情に寄り添う姿勢が不可欠です。 - 行政との非公式な折衝(根回し)
窓口との事前調整や個別事情の説明など、制度と現場の“あいだ”を埋める行為は、AIには再現不可能な「実務のリアル」です。
これらは、マニュアルや法令だけでは解決できない領域であり、むしろAI時代において一層価値が高まる「人間らしさに基づいたプロフェッショナリズム」です。
4.3|AIを“敵”ではなく“味方”に変える事務所の実践例
すでに多くの行政書士事務所が、AIを脅威ではなく“生産性を高める道具”として積極的に取り入れています。代表的な事例は以下のとおりです:
- 書類作成のドラフトを生成AIで時短
ChatGPTなどを使い、必要な情報を入力すれば数分で下書きが完成。行政書士は内容の精査とアレンジに専念できます。 - AI+クラウドツールで顧客管理・案件進捗を効率化
タスク管理や記録の自動整理、帳票の作成、期日のアラート機能などで、バックオフィスの負担を軽減。 - FAQチャットボットで一次対応を自動化
よくある質問への即時回答をAIで対応し、行政書士自身は重要な相談に集中できる体制を構築。 - リーガルテックとの連携
法律文書管理のクラウドツール(VDR)や契約書レビュー支援AIなどとの連携により、業務の透明性・セキュリティも向上。
実際、2021年の行政書士法改正では、「デジタル社会の進展への対応」が明文化され、行政書士自身がICTやAIを活用する方向性が“制度的にも”支持されている状況です。
今後の行政書士は、「書類を作る人」から「専門的な法的ナビゲーター」へと進化していきます。
AIの進化を恐れるのではなく、それを取り込みながら、“人間でしかできない価値”を再定義し、発揮していくことこそが、真のプロフェッショナル像なのです。
第5章|法改正とデジタル化が切り拓く、行政書士の新たなステージ
「行政書士は将来性がない」と言われることもありますが、現実には逆の流れが進んでいます。
近年の法改正やデジタル行政推進の中で、行政書士の業務領域はむしろ拡大しつつあり、社会から求められる役割も変化しています。
ここでは、2つの大きな動き──「特定行政書士」制度の創設と「デジタル手続法」のインパクト──を通して、行政書士の未来像を展望します。
5.1|「特定行政書士」がもたらす、行政手続の“出口”まで伴走する力
2014年の行政書士法改正により、「特定行政書士」制度が創設されました。
これは、所定の研修を修了し考査に合格した行政書士に対し、「行政不服申立手続」における代理権を与える制度です。
この改正が意味するものは大きく、行政書士がこれまで担ってきた「許認可申請」などの“入口”業務に加え、申請が拒否された場合の「不服申立て」=“出口”業務まで一貫して関与できるようになったことを意味します。
▶ 制度の主な意義
- 業務領域の拡大
かつては弁護士のみが行っていた領域に、行政書士が一定の条件下で関与できるように。 - 専門性と社会的評価の向上
不服申立ては、法律構成力・主張立証力が求められる分野であり、特定行政書士は“行政法の専門家”としての地位を強化する役割を担います。 - 費用対効果の面でもユーザーフレンドリー
弁護士よりも身近な存在でありながら、行政との折衝力や書類作成力に長けた行政書士が代理人となることで、利用者にとっても選択肢が広がります。
特定行政書士は、まさに“制度に強く、実務に通じた”専門職として、行政と市民の間の法的橋渡し役となる存在です。
5.2|デジタル手続法の本質──「自動化」ではなく「適正化」の時代へ
2020年以降、日本政府は「デジタル手続法」や「デジタル社会形成基本法」などを整備し、行政手続のオンライン化を原則とする体制を急速に進めています。
これにより、「今後は誰でも申請できるようになるから、行政書士はいらなくなるのでは?」という不安の声も一部にはあります。
しかし、これは誤解を含んだ認識です。
▶ オンライン化の“脅威”として語られるポイント
- 簡単な申請であれば、個人でも直接行えるようになる
- 書類の提出が「押印・紙」から「マイナンバー・電子署名」へと変わる
たしかに、単純な手続きに関しては代行の必要性が減少する場面も出てくるかもしれません。
しかし一方で、オンライン化によって手続の“形式要件”がより厳格化される側面があることにも注意が必要です。
▶ 「デジタル申請時代の行政書士」に求められる新しい役割
- 申請内容の真正性を担保する“法的チェック機能”
電子申請の時代だからこそ、書類の正確性・添付資料の整合性・申請趣旨の法的妥当性を確認できる専門家が必要とされています。 - 複雑化する“制度間の横断的知識”のナビゲーター
例えば補助金申請においては、法人設立→事業計画→許認可→実績報告と、複数の制度をまたいだ申請が求められます。これを一元的にコーディネートできる行政書士の役割は大きくなっています。 - 行政との調整役・根回し役としての価値
デジタル化が進んでも、“制度の運用解釈”や“窓口との事前調整”は依然として重要。行政書士はその実務対応の最前線に立っています。
また、行政書士法第1条には「国民の権利利益を擁護し、行政の円滑な運営に資すること」という根本理念が掲げられており、制度の変化に応じて進化する職業であることが法制度上も示されています。
この章が伝えたいのは、行政書士という資格は「過去の制度にしがみつく職業」ではなく、変化に対応しながら新しい社会構造の中で価値を高めていく専門職であるということです。
法改正やデジタル化は、行政書士の可能性を奪うのではなく、「新たな専門性を磨くチャンス」と捉えるべき変化なのです。
第6章|稼げる行政書士は何が違うのか?成功に不可欠なスキルとキャリア戦略
ここまで見てきたように、「行政書士はやめとけ」という意見には、根拠のない噂ではなく、“準備不足のまま開業した人がつまずきやすい”という現実が含まれています。
では、逆に「うまくいっている行政書士」は、何が違うのでしょうか?
ここでは、実際に安定・成長している行政書士に共通するスキルとキャリア構築の考え方を、独立開業型と企業内勤務型の両面から解説します。
6.1|独立開業で成功する人が身につけている「4つの力」
独立開業を選ぶ行政書士にとって、必要なのは法律知識だけではありません。
個人事業主=経営者としての視点が不可欠であり、成功者には次の4つの力が共通しています。
(1)専門特化力(Specialization)
「何でもできます」というスタンスは、逆に“選ばれない”原因になります。
建設業、入管、農地転用、補助金、相続など、自分の強みや地域ニーズに合った分野に専門特化することで、価格競争から脱却し、継続案件や紹介を生み出しやすくなります。
(2)マーケティング・営業力(Attracting Clients)
廃業理由の多くは「集客不足」です。プロとしての信頼感が伝わるホームページ、SEOやブログによる情報発信、SNSや異業種交流によるネットワークづくりなど、“売れる仕組み”を自ら作る力が求められます。
(3)経営者マインド(Entrepreneurship)
行政書士は士業であると同時に経営者です。売上管理・資金繰り・戦略的投資(広告や設備)、業務フローの構築など、事務所を“事業”として捉え、主体的に育てていく意識が欠かせません。
(4)IT・業務効率化スキル(Digital Literacy)
業務の電子化、顧客対応の自動化、クラウド管理の導入など、限られた時間で最大の成果を出すための効率化ツールの活用は、今や必須です。ChatGPTなどの生成AIも積極的に取り入れている事務所ほど、生産性が高い傾向にあります。
6.2|ダブルライセンスが生む“掛け算の専門性”
近年、行政書士と他資格の組み合わせによる「ダブルライセンス戦略」が注目を集めています。
これにより、業務の幅が広がるだけでなく、“顧客の悩みを一気通貫で解決できる”という大きな付加価値が生まれます。
▶ 主な相性の良い組み合わせ例
- 行政書士 × 社会保険労務士
→ 会社設立・許認可から、労務管理・助成金までトータル支援が可能 - 行政書士 × 宅地建物取引士
→ 農地転用や開発許可と、不動産売買の手続を一括でサポート - 行政書士 × 司法書士
→ 遺産分割協議書の作成と不動産登記をワンストップ対応 - 行政書士 × ファイナンシャルプランナー(FP)
→ 相続・事業承継における資産設計・税務相談まで幅広く対応
このように、組み合わせ次第で“価格競争に陥らない独自のポジション”を築くことができます。
結論として、行政書士という資格は「どのような道を選ぶか」「その道にどう戦略的に取り組むか」によって、まったく異なるキャリア像を描くことができます。
自分の価値観・得意分野・ライフスタイルに合った戦略を立てることこそが、行政書士としての成功の第一歩なのです。
結論|行政書士という資格は「成功の保証」ではなく「活かし方がすべて」
ここまでの検証を通じて、繰り返し浮かび上がったのは――
行政書士は“やめとけ”と言われる資格ではない。だが、“誰でも成功できる”資格でもない。
という現実です。
「資格さえ取れば食べていける」「独立すれば自由になれる」といった幻想のまま開業すれば、たしかに厳しい現実が待っているでしょう。
廃業者の多くが、準備不足・戦略不足・マーケティングの軽視により、顧客を獲得できずに市場から撤退しているのも事実です。
しかし一方で、今回紹介してきたデータが示すように――
- 市場は“飽和”ではなく“成長”している(業界売上は10年で2倍超)
- 収入は“低水準”ではなく“二極化”している(高単価業務で年収1,000万円超も現実的)
- AIは“脅威”ではなく“共存すべきツール”である(業務効率化と差別化の両立が可能)
- 法改正・デジタル化は“終わり”ではなく“始まり”である(特定行政書士や電子申請の対応力が求められる)
- キャリアは“独立”だけでなく、“企業内”でも発揮できる(年収700万超の法務職求人も多数)
という、むしろ“可能性の広がる資格”であることもまた明らかです。
問うべきは「この資格に価値があるか?」ではない。
本質的な問いは、こうです:
「自分は、この資格の価値を最大限に引き出せる戦略を持てているか?」
資格を取るだけでは何も変わりません。
しかし、“どんな分野に特化するか”“どのように顧客に価値を伝えるか”“変化にどう適応するか”という戦略が明確であれば、行政書士はあなたにとって、人生を変える強力な武器になります。
行政書士は「制度と社会のあいだに立つ法律家」です。
社会が変われば、その役割も進化します。変化を怖れず、時代に合わせてアップデートしていける人こそ、この資格の真価を引き出せるのです。

行政書士試験徹底解説
行政書士試験の完全攻略ガイド|ゼロから始める社会人のための難易度・勉強法・合格ロードマップ