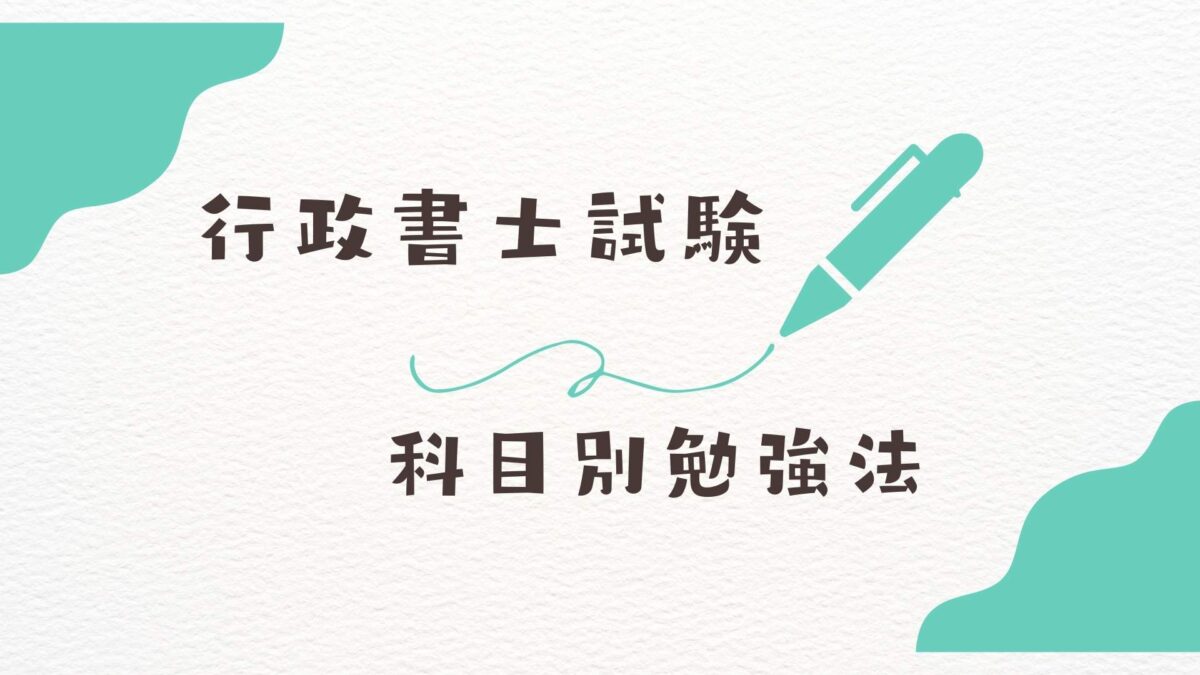なぜ記述式が“合格を左右する要所”なのか──記述対策を制する者が、試験を制す
60点の重み──“逆転可能”な高配点領域
行政書士試験は、総得点300点中180点以上で合格となる試験です。そのうち記述式問題は、行政法1問・民法2問の計3問が出題され、各20点、合計60点が割り当てられています。この60点は、全体の20%にあたる非常に大きな配点であり、合格ライン180点の実に3分の1を占めます。
つまり、記述式問題で安定して得点できれば、択一式の多少の失点を補って合格を狙える“逆転エリア”となります。逆に、記述式で大きく失点してしまえば、択一で高得点を取っていても不合格となるケースもあり得ます。それほど、記述式は合否に直結する重要セクションなのです。
ただし、この記述式にはもう一つの特性があります。それは「採点基準が公開されていない」ことです。記述式の採点は不透明で、大手予備校や合格者からは“ブラックボックス”と呼ばれることもあるほどです。
一般財団法人行政書士試験研究センターは、例年の合格率(およそ11~12%)を一定に保つ傾向があり、その調整に記述式の採点が使われているのではないかという指摘もあります。実際、択一の平均点が高い年は記述の採点が厳しくなり、平均点が低い年はやや緩和される傾向があると考えられています。
こうした相対評価的な採点の仕組みを踏まえると、「満点を狙う」のではなく「確実に部分点を積み上げる」戦略がより現実的です。記述式では、キーワードを押さえた記述ができれば部分点が与えられるため、白紙だけは絶対に避け、すべての設問に何かしら書くことが極めて重要です。
各問で7〜13点ずつ獲得できれば、合計30〜40点台の安定した得点源になります。これは採点基準の変動に影響されにくく、合格に向けて極めて有効な得点戦略となります。
なぜ多くの受験生が記述式でつまずくのか
記述式問題で点を落とす受験生は非常に多く、その原因は単なる「知識の不足」ではありません。むしろ、択一とは異なる“記述式特有のスキル”を求められることにあります。
以下は、特に多くの受験生が陥りがちな失点要因です。
- 時間配分ミス:3時間の中で記述3問に割くべき時間(目安:1問10分程度)を確保できず、焦って解答してしまう。
- 設問の誤読:事例形式で提示される問題文の要点を正確に把握できず、論点がずれたまま回答してしまう。
- 法律用語のミス:「審査請求」と「再審査請求」など、似て非なる用語の混同や、誤字脱字による減点。
- 応用力不足:模範解答を暗記しただけの“表面的な理解”では、少しひねった問題に対応できない。
これらのミスの多くは、「択一式の基礎知識が不十分なまま記述に取り組んでいる」ことに根本原因があります。
実際、記述式で問われる条文や判例の多くは、択一式の範囲と重なっています。択一を「なぜこの選択肢が正しくて、他が違うのか」とまで深く理解していれば、それを応用して記述答案を組み立てることができます。
つまり、記述式は択一の延長線上にある学習であり、“別物”ではなく“深化版”なのです。
基礎知識をしっかり身につけ、記述の特性に応じた訓練を積めば、多くの受験生が苦手とするこのセクションを、自分の“武器”に変えることができるのです。
合格者はこう考える──記述式解答までの“3ステップ思考法”
──感覚ではなく、再現性のあるプロセスで書く力を鍛える
Step1 問題文の読み解き方──論点を正しく見抜く
記述式問題を解く際、最初に行うべきは“丁寧かつ正確な読解”です。ただ文字を追うだけでなく、法的に「何が問われているのか」を読み取ることがポイントになります。
特に以下の4つの観点から問題文を読み解くことが重要です。
- 登場人物と法的関係の把握:誰がどの立場で登場し、どのような関係性(例:売主と買主、申請者と行政庁)にあるのかを明確にします。
- 法的紛争の特定:何を巡るトラブルなのか(例:契約不履行、行政処分など)を把握します。
- 設問の趣旨の把握:最後にある設問の文(例:「〜とは何か、40字程度で説明しなさい」など)を読み取り、解答すべきフレームを明確にします。
- 事実関係の法的分析:問題文にある具体的な事実が、どの法律の要件に対応するのかを見極めていきます。
こうした問題の読み方を補助する思考モデルとして、予備校アガルートが提唱する「J→T思考」があります。これは、目の前の具体的な事案(Jian)から、適用される抽象的な法的テーマ(Theme)を導き出すという手法です。
この“論点のマッピング”に失敗すれば、その後の知識検索や解答構成もすべてズレてしまいます。記述式において最も慎重に行うべきステップといえるでしょう。
Step2 必要な知識を正確に引き出す
論点が特定できたら、次は頭の中に蓄積した知識データベースから、関連する条文や判例などを引き出す段階です。ここでは、以下の3要素を素早く思い出す訓練が求められます。
- 関連条文:該当する法律の条文番号とその要旨。
- 重要判例:該当条文の解釈に関する判例の趣旨。
- 制度の要件と効果:法律制度が適用されるための条件(要件)と、それにより生じる法的な結果(効果)。
このフェーズでは、日頃の択一式対策で得た知識の“深さ”と“整理の精度”が問われます。
知識が曖昧であれば、思い出せなかったり、誤った用語を使ってしまったりと、記述式で得点することは困難になります。正確なアウトプットを意識したトレーニングが不可欠です。
Step3 40字で伝える“設計図”を作る
知識を思い出したら、すぐに解答を書き始めるのではなく、まず“骨子(構成案)”を組み立てるのが合格者の習慣です。この段階では、論理的かつコンパクトな解答を目指して、次の2つの作業を行います。
- キーワードの選定:Step2で得た情報の中から、40字以内で絶対に入れたいキーワード(2〜4語程度)を選びます。具体的には、当事者名・請求や救済手段・その根拠などが該当します。
- 文章構成の組み立て:「誰が・誰に対し・何を・なぜ(どの法的根拠で)」というフレームを基本にして、論理の流れを設計します。
たとえば、「AはBに対して、行政不服審査法◯条に基づき、審査請求をすることができる。」といった形式がベースになります。いくつかの定型文(テンプレート)を事前に用意しておくと、試験本番でもスムーズに対応できます。
記述式の答案作成は、「文章を書く」というより、「キーワードを正しく組み立てる」作業に近いものです。採点も、キーワードの有無によって点数が決まることが多く、余計な装飾表現を入れる余地はありません。
そのため、模範解答を単に暗記するのではなく、「どのキーワードが使われていて、どう論理的に配置されているのか」を分析する学習が重要です。キーワードを部品、解答を構造物として捉える視点が、応用力を伸ばす鍵となります。
40字で伝える!法律答案“精密ライティング”の技術
──簡潔さと正確さが問われる、法律文章の書き方
得点される文章とは?──法律文の“骨組み”を意識する
行政書士試験の記述式問題において求められるのは、文学的な文章ではなく、「論理的かつ法的に正しい構造を持った文章」です。
採点官が評価する答案には、以下のような要件が備わっています。
- 主語と述語が明確であること
「誰が」「誰に対して」「何をするか」という基本構造がはっきりしている文章は、それだけで部分点を獲得できる可能性が高まります。特に主語・客体は、問題文から登場人物を正確に抜き出して使うだけでも加点対象になります。 - 冗長な表現を避けること
「〜ということ」「〜において」「〜する点で」などの冗長な語は、1文字たりとも無駄にできない記述式では不利です。意味が通じる範囲で、可能な限り短く、簡潔な表現にする意識を持ちましょう。 - “解答の型”を活用すること
記述式問題には、一定のパターン(型)が存在します。例えば「〜に基づき、〜を請求することができる」といった法的構成要素を含むテンプレートを複数用意しておけば、本番でも速やかに構成を整えやすくなります。
記述式は“文章力”ではなく“構成力と要素選定力”が試される領域です。自分なりの型を持つことは、合格答案を安定的に生み出すための有力な手段となります。
文字数制限を乗りこなす技術──句読点・漢字の“使い分け”で差がつく
40字という厳しい制限の中で、法的内容を正確に表現するには、言葉の選び方や文字の使い方にも高度な注意が必要です。
句読点の使い方
- 句点(。)や読点(、)も1文字としてカウントされます。
- 文意が明確な場合、「。」を省略するのも一つの方法です。
- 読点は1文につき1つ程度に抑え、文の構造を壊さないようにします。
試験では公用文規程に従う必要はありませんが、「読みやすさ」「一貫性」を意識して使うことが大切です。
漢字とひらがなの使い分け
- 法律用語は正確に漢字で書く
「瑕疵」「相殺」「審査請求」など、法律用語の誤字は“理解不足”とみなされ、大幅減点のリスクがあります。書けるように練習しておきましょう。 - 接続詞や補助語はひらがなで
「とき」「こと」「もの」など、法的意味を持たない語句や助詞・接続詞はひらがなにする方が読みやすく、文字数削減にもつながります。
表現の精度を意識する
- 抽象的な言い回しではなく、明確な法的表現を用いることで得点力が上がります。
- たとえば「〜する必要がある」ではなく「〜を請求できる」「〜を行うことができる」など、法的効果を明示する表現が好まれます。
記述式問題は、文章を書く試験ではありません。「限られた文字数の中で、得点につながるキーワードを過不足なく配置する」ための技術が問われているのです。
極端に言えば、40字の中で“法的コードを書く”ような意識で、キーワードと論理を組み立てていくことが、得点力を最大化するための鍵となります。
よくある“落とし穴”とその回避法──不合格になる人の答案には、共通のパターンがある
減点される答案の典型パターンとその理由
記述式問題で得点を落とす受験生には、いくつかの“典型的な失敗パターン”があります。これらをあらかじめ理解し、回避策を講じることで、確実に得点力を伸ばすことができます。
パターン① キーワード不足
論点の方向性は合っているものの、得点に直結するキーワードが抜けているケースです。
例:訴訟提起の問題で「訴訟を起こせる」と記述しても、「義務付け訴訟」など具体的な訴訟名を書かないと、得点に結びつきません。
パターン② 論点のズレ
設問の趣旨を取り違え、全く異なる法的問題に言及してしまうミスです。内容がいくら正しくても、「問いに答えていない」ため0点となる危険性があります。
パターン③ 文章構造の破綻
主語と述語が対応していなかったり、法的構成要素がバラバラだったりと、文法的・論理的に整っていない答案です。この場合、キーワードが含まれていても減点されやすくなります。
パターン④ 単なる暗記の丸写し
条文や判例の文言を“覚えたまま書いただけ”の答案で、問題文の事案に即していないものです。
例:「債権者」「債務者」などの一般用語をそのまま使い、「A」「B」など具体的な当事者名に置き換えていない場合などが該当します。
“つまずきパターン”別の対策トレーニング法
前項で挙げた失敗パターンは、それぞれ原因が異なるため、対策も個別に考える必要があります。
■ キーワード不足・論点ズレへの対策
→【問題文読解の強化】
この2つのミスは、多くの場合、「問題文の読み方が浅い」ことが原因です。
以下のようなトレーニングを通じて、“論点抽出力”を高めましょう。
- 択一問題を解いた後、「なぜこの選択肢が正しくて他が誤りなのか」を口頭で説明する習慣をつける
- 問題文の事案を“法律要件に分解する”訓練を繰り返す(J→T思考)
■ 文章構造の乱れへの対策
→【骨子作成&テンプレート化】
このエラーは、書き出す前に“構成”を作っていないことが原因です。
以下を実践してみましょう。
- 解答前に、余白にキーワードをメモし、構造を整理してから書き始める
- 「AはBに対して、〜に基づき、〜を請求できる」など、典型文型を複数用意しておく
■ 丸暗記型ミスへの対策
→【模範解答の“分析学習”】
このタイプのミスは、知識を「覚えること」から「使うこと」へと視点を切り替える必要があります。
- 模範解答を見て、「どのキーワードが使われているか」「それらがどう繋がっているか」を分析
- 自分の言葉で“要素”を再構成し直す練習を繰り返す
これらの対策を習慣化することで、記述式問題における致命的ミスを大幅に減らし、安定して得点できる力が身についていきます。
重要なのは、「自分がどこでつまずく傾向があるか」を正確に把握し、それに応じたピンポイントの対策を講じることです。
記述式で差をつけるための学習戦略──「書ける力」は戦略的に育てられる
学習フェーズ別:記述対策のタイミングと取り組み方
記述対策は「最初から全力でやるもの」ではありません。むしろ、知識が整理されていない段階で取り組んでも非効率になりがちです。ここでは、学習時期に応じた最適な対策の進め方をご紹介します。
■ 初期(〜7月頃):まずは択一・多肢を優先
この時期は、無理に記述対策を始める必要はありません。むしろ択一式や多肢選択式の土台を固めることに集中しましょう。記述式は、こうした基礎知識を応用する力を問う形式のため、ここを飛ばして記述に挑むのは「家の土台がないまま2階を建てる」ようなものです。
■ 中期(8〜9月):本格的な記述対策をスタート
知識がある程度体系化されてきたこのタイミングで、記述式の対策を開始します。この時期は「思考プロセスの訓練」「過去問分析」「解答構成の練習」に重点を置き、40字で論理的に答える力を育てていきます。
■ 直前期(10月〜試験本番):実戦形式での完成度を高める
模試や総復習の中に記述対策を完全に組み込み、本番同様の環境下で解く訓練を行います。時間配分、設問読解、骨子作成まで、これまで積み上げたスキルを“時間内に出し切る”練習にシフトします。
過去問の「分析的」活用法──量より質が問われる
記述式対策における最大の教材は、やはり過去問です。ただし、ただ解くだけでは不十分。得点に直結する使い方をマスターしましょう。
■ 何年分解けばよいか?
目安は過去15年分。これは、出題傾向の変遷を掴みつつ、問われやすいテーマや論点のカバー率を最大化するためです。15年分を丁寧に分析すれば、試験本番で出題される内容の6〜7割に対応できるとも言われています。
■ 分析・トレーニングの具体的ステップ
- 出題パターンを分類する
「訴訟の選択」「法制度の定義」「法的効果の説明」など、問題のタイプ別に分類することで、解答構成の型が明確になります。 - 模範解答を分解する
解答文を、キーワードと論理構成に分けて“骨組み”を理解します。解答を丸暗記するのではなく、「なぜそのキーワードが必要か」「どういう順序で並べるのか」を読み解きます。 - 自分の解答と比較する
実際に書いた答案と模範解答を照らし合わせ、自分が書けていないキーワード、論理の抜けなどをチェックします。
独学者でもできる!“自己添削”の技術と工夫
独学での記述対策で最も悩ましいのが「自分の答案をどう評価するか」です。ここでは、自宅でも精度高く自己評価するためのテクニックをご紹介します。
■ キーワード採点法を導入する
模範解答をただ眺めるのではなく、「キーワードごとに点数を割り振る」ことで、採点の客観性を高める方法です。
- 模範解答から必須キーワード(例:「義務付け訴訟」「申請者A」「処分性」など)を抽出
- 各キーワードに点数を設定(例:訴訟類型 10点、当事者関係 6点、法的効果 4点など)
- 自分の解答にそのキーワードが含まれているかを確認し、採点する
「完全一致」でなくても、「趣旨が合っていれば部分点OK」といった柔軟な評価も取り入れましょう。
■ 外部の力も活用しよう
自己採点に限界を感じたら、予備校の添削サービスやAI採点ツールを利用するのも有効です。
- 予備校:講師の視点からフィードバックがもらえ、記述のクセや甘さが明確になります。
- スタディングなどのAI添削:スピード重視で反復練習したい方に向いており、コストパフォーマンスも良好です。
記述式の実力は、一朝一夕で身につくものではありません。しかし、「正しい時期に」「適切な方法で」対策を積み上げていけば、独学でも十分に合格点に届きます。大切なのは、焦らず戦略的に取り組むことです。
記述式対策に役立つ教材・講座・情報リソース──信頼できるツールを選ぶことで、独学の精度が変わる
市販の記述式問題集:目的別に選ぶべき一冊
記述式問題に特化した市販問題集は多数ありますが、すべての受験生に合うとは限りません。自身の学習レベルや目的に応じて最適な一冊を選ぶことが重要です。以下に、信頼性の高い主要教材を比較します。
| 書名 | 著者・出版社 | 特徴 | 対象レベル |
|---|---|---|---|
| みんなが欲しかった!行政書士の40字記述式問題集 | TAC株式会社(行政書士講座)/TAC出版 | 解答に至る思考過程が丁寧にマニュアル化されており、初心者が「どう考えればよいか」を学びやすい。 | 初級〜中級 |
| 合格革命 行政書士 40字記述式・多肢選択式問題集 | 行政書士試験研究会/早稲田経営出版 | 過去問とオリジナル問題がバランス良く収録され、記述と多肢選択を一冊で効率よく学べる。 | 中級〜上級 |
| 出る順行政書士 40字記述式・多肢選択式問題集 | 東京リーガルマインドLEC総合研究所/LEC | 頻出テーマに的を絞った問題構成で、効率重視の学習が可能。LECの実績と分析に裏付けられた安心感あり。 | 中級〜上級 |
選び方のポイント:
- 初学者は「思考過程」が詳しい教材を優先
- 中上級者は「論点網羅」や「演習量」を重視
講座・添削サービス:記述対策に強いスクール比較
記述式の得点力をさらに高めたい、独学では限界を感じている、という場合には、予備校の記述対策講座や添削サービスの活用が非常に有効です。各予備校の特色を理解し、自分に合ったものを選びましょう。
| 予備校名 | 主な講座・サービス例 | 特徴 | 添削方法 | 料金目安 |
|---|---|---|---|---|
| アガルートアカデミー | 記述式対策講座、記述答練 | J→T思考など論理的な解法を重視し、得点に直結する思考訓練が中心。 | 講師添削 | 高価格帯 |
| 伊藤塾 | 記述式対策講座、厳選60問スピードチェック、模試 | 丁寧な解説と体系的な講義構成に定評。司法試験系指導のノウハウが活きている。 | 講師添削 | 高価格帯 |
| LEC東京リーガルマインド | 解法ナビゲーション講座、公開模試 | 長年の記述採点データを活かした現実的な解法指導。模試でも記述式採点あり。 | 講師添削 | 高価格帯 |
| TAC | 記述対策講座、全国模試 | 自社教材と連携した実践的カリキュラム。解法プロセスの習得を重視。 | 講師添削 | 高価格帯 |
| スタディング | 合格答練、合格模試 | AIによる即時フィードバック機能が特徴。コスパ重視の反復学習に最適。 | AI添削 | 非常に安価 |
| 資格スクエア | 森Tの記述対策講座 | 人気講師による解説講義。要点整理が明快で、ピンポイント学習にも適している。 | 講座添削 | 比較的安価 |
補足:
- 高価格帯=2万円〜5万円程度
- AI添削や単科講座はコストを抑えつつ質の高い演習が可能
おわりに:記述式は“苦手科目”ではなく“得点源”に変えられる──合否を分けるのは、知識の深さより“運用力”と“継続力”
記述式問題は、多くの受験生にとって“鬼門”とされがちです。しかし、それは「書けない」のではなく、「書き方を知らない」からに過ぎません。
本記事で解説してきたように、記述式は
- 択一式で培った知識を応用する力、
- 問題文を分解し論点を見抜く力、
- 限られた文字数で法的要素を整理し表現する力、
これらの“実務的アウトプット力”を試すセクションです。
記述式の得点を安定させるには、天性の文章力よりも「思考プロセスの確立」と「日々の訓練の積み重ね」が何より重要です。
まずは白紙をなくすことから始め、やがてキーワードを確実に拾えるようになり、最終的には40字の中で論理的・法的に成立する答案を書けるようになります。そこに至るプロセスは、決して感覚的なものではなく、誰でも再現可能な「技術」です。
そして、あなたが今苦手だと感じているその分野こそ、適切な方法で学び直せば、最大の得点源へと変わります。
記述式は、受かる人だけが“活かせている得点源”です。
あなたの答案も、今日からその“合格答案”の一つになれる準備は整っています。
焦らず、丁寧に。
正しい戦略で、記述式を“武器”に変えていきましょう。

行政書士試験徹底解説
行政書士試験の完全攻略ガイド|ゼロから始める社会人のための難易度・勉強法・合格ロードマップ