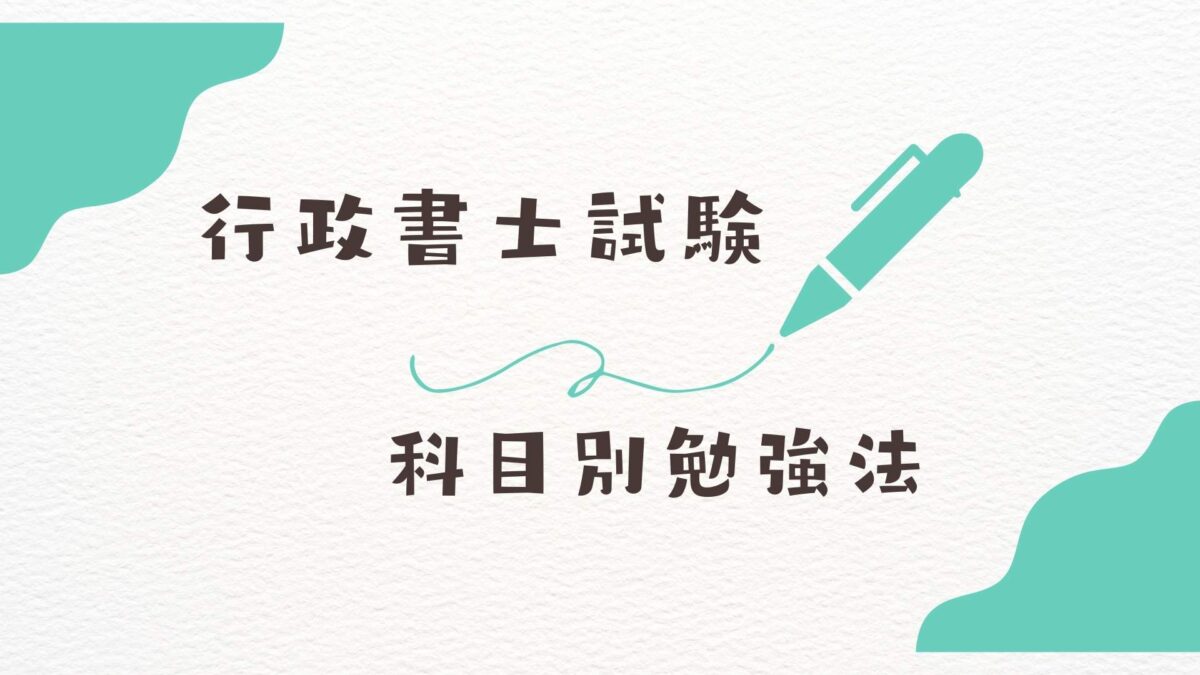第1章 文章理解は“軽視できない得点源”である
1.1 試験全体における配点と位置づけ
行政書士試験は全60問・300点満点の中で、「基礎知識」科目が14問・56点分を占めています。その中でも文章理解は3問(計12点)を占めており、全体の約4%という数字以上に戦略的な意味を持ちます。
文章理解は、知識の暗記に依存せず、本文中の情報のみで完結する出題形式のため、対策次第で安定して得点が見込めます。特に他の基礎知識問題(政治・経済・社会など)が出題範囲の広さゆえに不確実性を伴うのに対し、文章理解は比較的コントロールしやすい「得点源」として位置づけることが可能です。
1.2 「基礎知識」足切り対策のキーポイント
行政書士試験には「足切り点(基準点)」が設定されており、基礎知識では14問中6問(24点)以上の正答が合格の必須条件です。
文章理解で3問中2問以上正解できれば、それだけで足切り突破の半分以上を確保できる計算になります。3問すべて正解すれば、残る11問中3問正解で済むため、他の分野の負担を大きく軽減できます。
つまり、文章理解を制することが、基礎知識全体の合格ラインを大きく引き寄せることにつながるのです。
1.3 得点戦略としての文章理解の強みとは?
文章理解は、出題傾向が安定しており、訓練によって確実に得点力を高められる数少ない分野です。問題文中にすべての解答根拠が含まれているため、特別な知識を必要とせず、純粋な読解スキルだけで勝負できます。
また、多くの合格者が「試験開始直後に文章理解を解く」戦略を取っています。これは、序盤で文章理解をクリアすることで心理的な安定を得られ、残りの高配点科目(法令等)に落ち着いて取り組めるという効果があるからです。
文章理解は「足切り回避の保険」であると同時に、「試験全体のリズムを整える起点」としても機能します。したがって、本試験の戦略設計において無視できない、極めて重要なパートといえるでしょう。
第2章 なぜ文章理解が苦手になるのか?よくある原因と対策の視点
2.1 読み方のミスと時間のムダづかい
文章理解でつまずく受験生の多くが、本文を最初から丁寧に読もうとするあまり、設問の要求を確認しないまま読み進めてしまうという共通の誤りを犯しています。
この「目的なき精読」は、時間の浪費につながるだけでなく、文章の主旨が曖昧になり、必要以上に難しく感じてしまう原因にもなります。
さらに、「この2択で迷うけど決めきれない……」という場面で時間を使いすぎるのも典型的な失敗例です。これは、本文の根拠に基づいて選択肢を絞り込むための論理的な読解プロセスが確立されていない状態を示しています。
伊藤塾ではこのような状態を「分かったつもり」と表現し、最も危険な段階だと警告しています。表面的な理解では正確な判断ができず、誤答につながるリスクが高まるからです。
2.2 「主観読み」のクセが正答を遠ざける
LECの人気講師・横溝慎一郎氏は、「文章理解が苦手な受験生の多くは、自分の感想や主観をもとに選択肢を選んでしまう」と指摘します。
これは、「筆者が何を言っているか」ではなく、「自分はどう思ったか」を基準にしてしまうという危険な思考パターンです。試験で求められているのは、出題者や筆者の主張を客観的に読み取る力であり、自分の意見ではありません。
また、アガルートアカデミーの分析では、「間違いを素直に受け入れられるかどうか」が読解力の成長を大きく左右するとも言われています。合格者は誤答を正面から見つめ直し、講師の指導を柔軟に受け入れる一方で、伸び悩む受験生は「本当は分かっていた」といった言い訳をしてしまいがちです。この姿勢が、読解力向上のブレーキとなるのです。
2.3 法令科目と同じ勉強法では通用しない
文章理解の学習では、法令科目とはまったく異なるアプローチが必要になります。
法令科目では、条文・判例・定義などの知識を蓄え、選択肢に照らし合わせて答えを導くスタイルが有効ですが、文章理解ではその知識がそもそも問われません。必要な情報はすべて問題文中に含まれており、それをもとに論理的に正解を導き出すプロセスが重視されます。
そのため、「過去問を繰り返して正解を覚える」といった学習法は文章理解には不向きです。重要なのは、「なぜその選択肢が正解なのか?」「他の選択肢が不正解なのはなぜか?」という理由を本文の記述と照らし合わせて説明できるようにすることです。
伊藤塾やアガルートも一貫して、「正解を覚えるのではなく、不正解の根拠を言語化できる力を養うべき」と強調しています。単なる正誤確認で終わらず、不正解の選択肢と本文との矛盾点まで徹底的に分析することが、文章理解を合格水準まで引き上げる鍵となります。
第3章 【満点を狙う】文章理解の解法ステップと実践テクニック
3.1 「先に選択肢」か「まず本文」か──読む順番の最適解とは?
文章理解の解き始めで迷うのが、「本文から読むべきか」「選択肢から読むべきか」という順番の問題です。実は、どちらが正しいかは一概には言えません。設問形式に応じて使い分けることが、最も合理的なアプローチです。
- 選択肢先読み型(特に初学者に有効)
あらかじめ選択肢を確認しておくことで、「本文のどこに着目すればよいか」という読みのフレームが明確になります。読解の方向性が定まるため、迷走を防ぐ効果があります。 - 本文先読み型(主旨把握問題などに有効)
先に選択肢を読むと、内容に対する先入観が生じることがあるため、主張の把握が重要な問題では、本文を先に読む方が素直な読解ができます。 - 統合型アプローチ(最も推奨)
出題形式によって柔軟に使い分ける「ハイブリッド戦略」が、最も安定した成果につながります。たとえば、空欄補充や文章整序では選択肢先読み、内容一致や主旨把握では本文重視、という具合です。
3.2 接続詞・指示語・キーワード──論理構造を見抜く読み方
評論文のような論理的文章においては、単に意味を追うだけでなく、「構造を読む」ことが不可欠です。そのカギとなるのが、以下の3要素です。
- 接続詞の役割に注目する
文章の流れや筆者の主張を見抜くために、接続詞は重要な手がかりになります。 - 逆接(しかし、だが):主張の核心が後に来るサイン
- 順接(だから、したがって):結論や理由を導くヒント
- 言い換え(つまり、すなわち):主張を補足・強調する合図 これらを意識して読むことで、論旨の展開がクリアに見えてきます。
- 指示語の内容を正確に把握する
「これ」「それ」「このような」といった指示語が何を指しているのかを、その場で特定する習慣を持つことが大切です。あいまいに読み流すと、選択肢との整合性を見誤る原因になります。 - キーワードとキーセンテンスを見極める
筆者の主張や文章全体の論旨は、具体例や補足情報とは明確に区別されます。不正解の選択肢は、具体例をあたかも全体の主張のように見せる罠を含んでいることが多いため、論旨と事例の位置づけを常に意識して読み進めましょう。
3.3 設問ごとの出題パターンと攻略法
文章理解の設問は主に3パターンに分類され、それぞれに効果的な解法があります。
■ 内容一致問題(主旨・論点の把握)
- 正解の選択肢は、本文の論旨を言い換えたものが多く、不正解は次のようなパターンが典型です:
- 筆者の主張と真逆の立場を取っている
- 本文にない情報や誇張を含んでいる
- 一部の事実だけを取り上げて、全体を誤解させる内容になっている
■ 空欄補充問題(文脈と論理のつながりを問う)
- 空欄の前後文を読み、自然なつながりになる選択肢を選ぶのが基本です。
- 空欄が文章の冒頭であれば導入、末尾なら結論やまとめである可能性が高く、その位置にも注目しましょう。
■ 文章整序問題(文の順番を組み立てる)
- 各文の接続詞や指示語から「この文の前には何が来るべきか?」を考え、小さな文のセットを組んでいく「セット作り」が効果的です。
- たとえば「しかし」で始まる文には、それに対立する前提の文が必要です。このようなセットをいくつか作り、論理的に順序を組み立てていきます。
3.4 時間配分──あなたに合った解答ペースを見つけよう
文章理解にどれだけ時間を割くべきかは、受験生の読解力や試験戦略によって異なります。各予備校・合格者の推奨時間を参考に、自分に合ったペースを見つけることが大切です。
| 1問あたりの目安 | 3問合計の目安 | 主な方針 | |
|---|---|---|---|
| 伊藤塾 | 6~7分 | 約20分 | 慎重な読解で確実に得点 |
| アガルート | 3~5分 | 10~15分 | 時間短縮し法令科目に集中 |
| LEC | 時間より優先度重視 | 試験前半で処理 | 足切り回避を重視した配分 |
| 合格者一般 | 5~7分 | 15~20分 | 標準的なバランス感覚 |
| 初心者戦略 | 約10分 | 約30分 | 焦らず丁寧に解き切る練習 |
重要なのは「固定的な時間配分」ではなく、「模試などで計測しながら自分に最適なリズムを見つける」ことです。
あなたにとって最も集中できる時間配分を模索し、それを本番に落とし込むことで、文章理解の3問を確実な得点源にすることができます。
第4章 現代文が苦手でも大丈夫!文章理解力を伸ばす効果的な勉強法
4.1 インプット重視:読解力の土台を作る教材選び
文章理解で得点するために必要なのは、特定の知識を覚えることではなく、「どんな文章でも筋道立てて読める力=論理的読解力」です。
この力を養うには、文章の構造を捉えるための「読み方の技術」を学べる教材を選ぶことが重要です。
以下は、実績ある各種教材の特徴です。
| 教材タイプ | 書籍例 | 特徴 |
|---|---|---|
| 総合テキスト | 合格革命(早稲田経営出版)、出る順(LEC)、うかる!(伊藤塾)、合格のトリセツ(LEC) | フルカラーや図解で初学者に親切。各シリーズごとに問題集との連動も充実。 |
| 補強問題集(資格向け) | TAC出版「過去問解きまくり!」シリーズ(公務員試験用) | 行政書士試験と同形式の文章理解問題を大量に演習可能。文章整序や空欄補充の訓練に有効。 |
| 補強問題集(大学入試向け) | 河合出版「入試現代文へのアクセス」など | 「なぜその読み方になるのか」を丁寧に解説。文章構造を理解する訓練に適しており、実力養成に効果的。 |
文章理解は知識ではなく「読解技術」が問われる分野だからこそ、「構造に着目した教材」を選ぶことが最短ルートです。
4.2 アウトプット重視:過去問演習と復習の質がカギ
読解技術をインプットしたら、それを本番形式の問題で繰り返し使って「実践力」へと転化する段階に進みます。
■ 過去問の使用法:年数と形式の使い分け
- 対象年度:平成18年(2006年)の制度変更以降の問題が推奨対象です。
- 量の目安:最低5年分、理想は10年分を繰り返し解くことが目安です。
- 形式の選び方:
- 学習初期:分野別に整理された「論点別」過去問で基礎を固める
- 学習後期:時間配分も含めた実戦訓練として「年度別」過去問を活用
■ 復習の仕方:正解・不正解の「理由」にこだわる
ただ正解・不正解を確認するだけでは、得点力は伸びません。
重要なのは、「正解の根拠はどこか」「不正解の選択肢は、本文のどこに反しているか」を、自分の言葉で説明できるレベルまで分析することです。
アガルートや伊藤塾も「選択肢の根拠の言語化こそが最も重要」と強調しています。
■ 時間を意識する:模試形式での訓練
過去問や模試を解くときには、必ず時間を計りましょう。本試験と同じプレッシャー下で解くことで、「焦らず最後まで解き切る力」が身につきます。
4.3 学習スケジュールと継続のコツ
文章理解の力は、短期間で急に伸びるものではなく、日々の積み重ねによって少しずつ磨かれていくものです。
■ 毎日少しずつが最も効果的
- 平日:毎日15~20分程度、大学入試や公務員試験の問題集から1〜2問を解く
- 週末:3時間の模試や年度別過去問演習を行い、解いた問題を徹底的に分析・復習
このように文章理解を「ウォーミングアップ」として日課に組み込むことで、読解感覚を維持し、他の法令科目の学習効率も高まります。
■ 早期対策が直前期をラクにする
文章理解は一度基礎を作れば、維持にかかる負荷は小さく済みます。したがって、学習初期から対策を始めておけば、試験直前期には法令科目に集中する余裕を生み出せます。
日々のルーティンに「文章理解を1問解く習慣」を取り入れることが、合格戦略を支える基盤になります。
第5章 文章理解に関するよくある質問(Q&A形式)
5.1 古文は出題されるの? → 出ません!
行政書士試験の文章理解は、現代文(主に評論文)からの出題に限られており、古文や漢文は一切出題されません。
公式の試験概要や各種予備校の教材でも、出題対象は明確に「現代文のみ」とされています。そのため、古文の対策は不要です。時間と労力は現代文読解のスキル強化に集中させましょう。
5.2 新聞や本を読むのは効果がある? → 効果ゼロではないが、効率重視が正解
一般的な読書習慣が文章理解の感覚を養うことはありますが、行政書士試験対策としては非効率な方法です。
限られた学習時間の中で得点力を上げるには、試験形式に即した問題演習(過去問・公務員試験問題など)を通じて、出題傾向や解法プロセスに慣れることの方が圧倒的に効果的です。
試験直結のアウトプット教材を活用することが、スコアアップへの最短ルートです。
5.3 満点を取るにはどのくらい勉強すればいい? → 時間より「方法」が重要です
文章理解で満点を目指すには、何時間勉強したかよりも、「正しい方法で学習しているか」が重要です。
- ただ本文を読むだけの非効率な勉強を50時間続けるよりも、
- 解法プロセスを意識した効率的な学習を25時間行う方が、得点力は確実に上がります。
目安としては、以下のような学習計画で多くの受験生が満点圏に到達しています。
- 正しい解き方(第3章で解説)を学ぶ
- その手順を習慣化するまで毎日15〜30分の練習を数ヶ月継続
- 過去問や補強問題集で質の高い演習を30〜50時間程度こなす
このようなプロセスに取り組めば、現実的に満点を狙える実力が身につきます。
5.4 本番でパニックになったらどうすればいい? → 事前対策と冷静な切り替えがカギです
試験本番で焦りや不安に襲われることは、誰にでも起こり得ることです。重要なのは、それに対処するための準備をしておくことです。
以下の3つの対策を事前に身につけておきましょう。
- 思考のリフレーミング
「この問題は他の受験生にとっても難しいはず。ここで合否は決まらない」と自分に言い聞かせ、一旦後回しにして冷静さを取り戻す。 - 呼吸を整える
深い腹式呼吸で心拍数を下げ、脳に酸素を送り込む。これは、緊張や焦りを和らげる科学的に有効な方法です。 - リセットの時間を設ける
試験中に数十秒間、目を閉じて呼吸を整える、あるいは意図的にトイレ休憩を取るなど、意識的に「思考の中断」をはさむ。
また、最も効果的なパニック対策は「模試や過去問で本番環境をシミュレーションしておくこと」です。
本番さながらの状況で成功体験を積み重ねておくことで、自信が生まれ、冷静さを保ちやすくなります。
おわりに:文章理解は“足切り回避”を超えて“合格を引き寄せる武器”になる
文章理解は、かつて「基礎知識の一部」として軽視されがちな分野でした。しかし近年では、制度の見直しや出題傾向の安定化により、戦略的に取り組む価値がますます高まっています。
3問12点という配点は、一見すると小さく思えるかもしれません。しかし、そのすべてを確実に得点できれば、「足切り」対策として絶大な安心感を得られるだけでなく、他の基礎知識科目への負担を大きく軽減することができます。
さらに、文章理解の強化は試験全体のパフォーマンスにも好影響を与えます。序盤でスムーズに得点を確保できることで、精神的な安定を得て、残りの高配点科目にも集中しやすくなります。
つまり、文章理解は「落とされないための保険」ではなく、「合格に向かって攻めるための武器」なのです。
本記事で紹介した戦略・解法・学習法を、自分の学習スケジュールに組み込み、日々の演習に取り入れてみてください。
読み方の技術を身につけたあなたなら、文章理解の満点も、決して夢ではありません。

行政書士試験徹底解説
行政書士試験の完全攻略ガイド|ゼロから始める社会人のための難易度・勉強法・合格ロードマップ