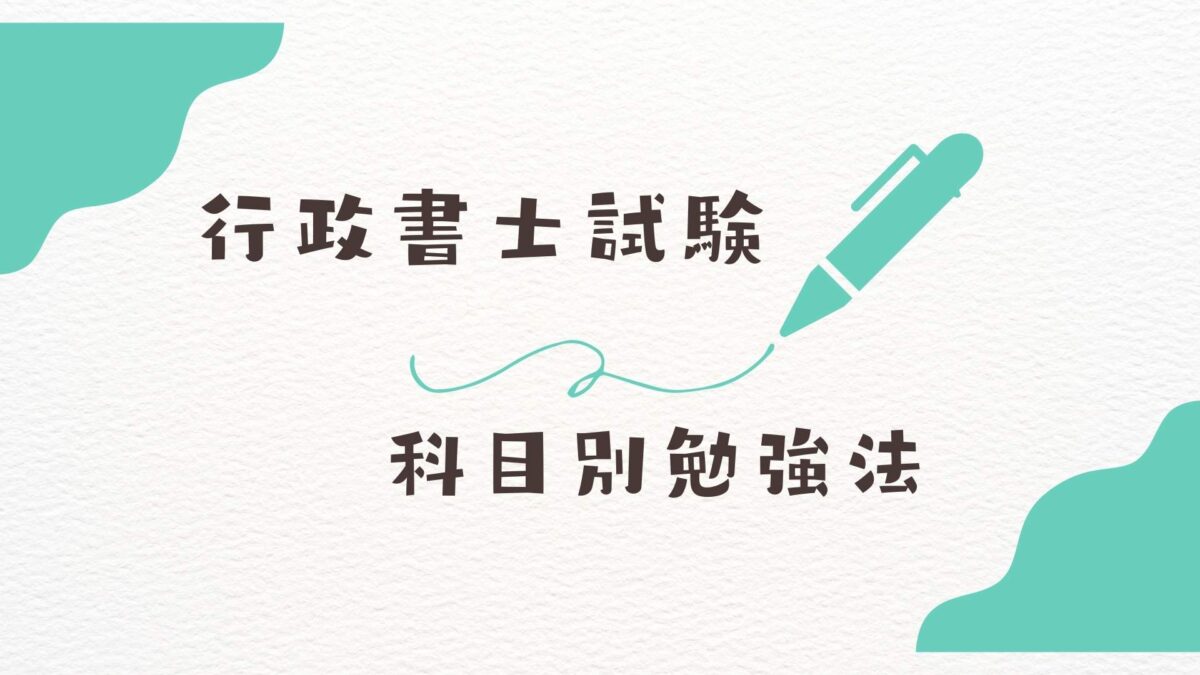なぜ「たった8点」が合否を分けるのか?
行政書士試験の広大な出題範囲の中で、「基礎法学」をどう位置づけるか――これは多くの受験生にとって悩ましいテーマです。全300点中のわずか8点という配点から、「時間をかける価値はない」「捨て科目にすべき」といった意見が根強くあります。
一方で、「そのたった8点が合否を決めた」という声も少なくありません。つまり、軽視すれば足をすくわれ、戦略的に押さえれば強力な保険となるのが基礎法学なのです。
特に問題となるのが次の二つの論点です。
- 【論点1】基礎法学は試験開始直後に解くべきか、それとも後回しにすべきか?
- 【論点2】そもそも基礎法学は本格的に対策する必要があるのか?
これらは単なる“好み”ではなく、限られた時間をどう配分し、どう得点を積み重ねていくかという合格戦略の核心です。
本記事では、予備校講師や合格者の声、そして試験データなど信頼できる複数の情報源をもとに、これらの問いに明確な答えを提示します。
読み終えるころには、漠然とした不安や迷いは消え、基礎法学を“リスク管理”ではなく“得点戦略”として活かすための具体的な方針が手に入っていることでしょう。
第1章 基礎法学の本当の役割とは?──合格戦略における正しい位置づけ
1-1 たった8点、されど8点──“小さな配点”が持つ大きな重み
行政書士試験における「基礎法学」は、法令等科目に分類され、5肢択一式の2問が出題されます。1問4点で合計8点、全体の300点満点中での割合は約2.7%。この数値だけを見ると、「優先度の低い科目」「勉強の手間に見合わない」と判断したくなるかもしれません。
しかし、注意すべきは試験の合格基準が“絶対評価”であるという点です。行政書士試験では、以下の3つすべての条件を満たさなければなりません:
- 法令等科目(244点満点)で122点以上
- 基礎知識科目(56点満点)で24点以上
- 全体(300点満点)で180点以上
この「絶対点で合否が決まる」という仕組みの中で、たった8点といえど、ボーダーライン付近では合否を左右する“決定打”になりうるのです。
事実、多くの受験生が180点の合格基準を目前にして涙をのんでおり、「あと4点足りなかった」「1問落として不合格になった」という体験談も後を絶ちません。その中には、基礎法学を軽視して無対策で挑んだ人も含まれます。
つまり、基礎法学は“全体の2.7%”という相対的な価値ではなく、“たった1問が合格を呼び込む100%の価値”を持つ場面があるということです。
このように考えると、基礎法学は「配点の低さ」だけで判断してはいけない、極めて戦略的な意味を持つ科目であることがわかります。
配点と全体に占める割合(科目別一覧)
| 科目 | 出題数 | 配点 | 全体に占める割合 |
|---|---|---|---|
| 基礎法学 | 2問 | 8点 | 約2.7% |
| 憲法 | 6問 | 28点 | 約9.3% |
| 行政法 | 22問 | 112点 | 約37.3% |
| 民法 | 11問 | 76点 | 約25.3% |
| 商法・会社法 | 5問 | 20点 | 約6.7% |
| 基礎知識(一般知識) | 14問 | 56点 | 約18.7% |
| 合計 | 60問 | 300点 | 100% |
1-2 狙うのは満点ではない──「4点を確保する」ことが最大の戦略
基礎法学の配点は全体のわずか8点ですが、多くの予備校や合格者が共通して掲げる目標は「満点を取る」ことではありません。現実的かつ合理的な戦略は、「2問中1問を確実に取り、最低4点を死守する」ことにあります。
なぜなら、基礎法学には“8点のパラドックス”とでも呼ぶべき性質があるからです。配点が低いため、対策を後回しにする受験生が多い一方で、180点の合格基準においては、わずかな失点が命取りになるケースが後を絶ちません。実際、「あと4点足りなかった」「1問多く取れていれば合格だった」という声は毎年聞かれます。
こうした“ボーダーライン層”にとって、基礎法学の4点は「相対的な価値」ではなく、「合否を分ける絶対的な価値」を持ちます。だからこそ、戦略的な到達目標は「満点」ではなく、「0点を避けて最低4点を確保する」ことなのです。
この4点は、他科目での思わぬ失点をカバーできる“得点の保険”として、あなたの合格を守る存在になります。
1-3 基礎法学は“奇問”の宝庫?──試験序盤を揺さぶる心理的圧力
基礎法学は、例年、試験問題の問1・問2に登場することが多く、その出題内容はときに受験生の予想を大きく超える“奇問・難問”となることがあります。
これらは単なる知識問題ではなく、試験序盤に精神的な揺さぶりをかける「心理戦」の一面も持ち合わせています。開始直後、見たことのない難問に遭遇して焦ると、その後の得点源となる行政法や民法でのパフォーマンスに悪影響を及ぼしかねません。
出題者側は、法的知識だけでなく、「初見の問題に冷静に対応できるか」「時間配分を適切に行えるか」といった“試験マネジメント能力”も見ていると考えられます。
過去の出題傾向を分析すると、以下のようなテーマが多く見られます:
- 法制度全体の構造理解:裁判制度、司法制度改革、判決と命令の違いなど
- 法解釈・法源:慣習法・判例法・条理、法律の分類や解釈方法など
- 時事法学:災害時支援に関する法律、ADR(裁判外紛争解決手続)など
これらを踏まえると、基礎法学は「1問は標準的な過去問ベース」「もう1問は高難度の応用問題」という構成になる傾向があります。
1-4 基礎法学は“抽象的な基礎”ではなく“知識を統合する羅針盤”
基礎法学は、法体系全体の構造や法解釈の基本原理を学ぶものであり、法律学習の“基盤”であると同時に、“知識を統合する羅針盤”でもあります。
民法や行政法などの主要科目で学んだ内容を、どのような理念や法体系の中で理解すべきか──その指針を与えてくれるのが基礎法学の役割です。
ただし、この羅針盤の効果が最大限に発揮されるのは、学習初期ではなく、主要科目を一通り学んだ後です。具体的な法的知識という“地図”を手に入れてから、抽象的な法理を学ぶことで、点在していた知識が有機的に結びつき、法的思考の全体像が明確になります。
このように基礎法学は、学習の“スタート地点”ではなく、“キャップストーン(学習の総仕上げ)”として位置づけることで、その価値を最大限に活かすことができます。
第2章 最小の努力で最大のリターンを得る勉強法
2-1 基礎法学はいつ・どの順で学ぶ?──“後半で一気に”が正解
行政書士試験の合格に必要な総学習時間は、一般的に500〜1000時間といわれています。その中で基礎法学にかけるべき時間は、わずか15〜20時間程度。あくまでも「コンパクトに押さえるべき科目」として位置づけるのが現実的です。
学習に着手するタイミングとして適しているのは、主要科目である民法・行政法・憲法を一通り終えた“後半フェーズ”です。
多くの予備校や合格者が推奨する科目ごとの学習順は、次のようになっています:
民法 → 行政法 → 憲法 → 一般知識 → 基礎法学 → 商法・会社法
この順序の意図は明確です。基礎法学は概念が抽象的で、法的知識の土台がないまま学ぶと理解が進みづらい一方で、主要科目を学習済みであれば、抽象的な法原理を現実の知識と結びつけて整理できるようになります。
つまり、基礎法学は「学習のスタートライン」ではなく、「知識を再構成するゴールライン」として活用することで、学習全体の理解を深める“統合的効果”が期待できるのです。
2-2 教材は「1冊+過去問」でOK──最小投資で最大効果を狙う
基礎法学のために専門書を新たに購入する必要はありません。予備校の基本テキスト1冊と、過去問5〜7年分だけで、必要な知識と得点力は十分に養えます。
基本テキストの使い方
- 該当章を1〜2回通読すればOK。
- 目的は「完璧な理解」ではなく、「全体像の把握」と「重要用語に慣れること」。
過去問の使い方
- 5〜7年分を2周するのが理想。
- 出題パターンを体感し、標準的な問題に対応できるようにするのが目的。
教材選びに悩む方は、下記の教材比較表を参考に、自分の学習スタイルに合った1冊を選ぶとよいでしょう(→前項の表を参照)。
「深入りせず、得点に直結する部分だけ押さえる」──それが、基礎法学における教材活用の鉄則です。
合格者に支持される主要教材シリーズの比較表
| シリーズ名 | 出版社(予備校) | 特徴と強み | こんな方におすすめ |
|---|---|---|---|
| 合格革命シリーズ | 早稲田経営出版(TAC) | 全ページフルカラー、図表が豊富で視覚的に理解しやすい。テキストと問題集の連動性が高い。 | 初学者、カラー図表で学びたい人、体系的に理解したい人 |
| 出る順シリーズ | 東京リーガルマインド(LEC) | 長年の実績あり。落ち着いた2色刷りで情報が整理されており、独学者に根強い人気。 | シンプルな構成が好きな人、実績重視の独学者 |
| うかる!シリーズ | 伊藤塾 | 法律系試験に強い伊藤塾のノウハウを凝縮。解説が丁寧でわかりやすい。フルカラーで見やすい。 | 質の高い解説で学びたい人、講師の視点を重視する人 |
2-3 “深入りしない勇気”が合格を呼ぶ──得点に直結する3つのコツ
基礎法学で4点を確保するためには、「必要なところだけ学ぶ」という割り切りが重要です。そのためのポイントは、次の3つです。
① 出題範囲を限定する(パレート戦略)
基礎法学の出題範囲は非常に広いものの、実際に得点につながるのは頻出テーマに限られます。出題頻度の高い“20%のコア領域”に絞って対策することで、時間あたりの効果を最大化できます。
② 判例の読み方は“要点だけ”
判決文を全文読む必要はありません。基本テキストに掲載されている重要判例について、「どんな事案か」「どんな結論か」を大筋で理解するだけで十分です。
③ 専門用語の定義は正確に押さえる
法律用語は日常語と意味が異なることも多く、誤解しやすい部分です。以下のような基本語彙は、確実に理解しておきましょう。
| 用語 | 意味の概要 |
|---|---|
| 善意 | ある事実を知らないこと(例:第三者の善意取得) |
| 悪意 | ある事実を知っていること |
| 権原 | 法律上の正当な根拠(例:所有権に基づく占有など) |
| 権限 | 法律・契約上で許されている行為の範囲 |
| 無効 | 行為が初めから法的効力を持たない状態 |
| 取消し | 有効に成立した行為を、後から遡って効力を消滅させること |
このように、基礎法学は「広く・深く」ではなく、「狭く・深くない」学習が合格への近道。限られた時間とリソースを、最も費用対効果の高い場所に集中投下しましょう。
第3章 本試験での「解く順番」はどう決める?──得点効率を最大化する戦略とは
3-1 まず基礎法学から解く?──勢いをつけたい人向けの戦法
「試験の最初に基礎法学から手をつけるべきか?」という問いは、多くの受験生が直面する悩みのひとつです。この戦法を支持する人たちの主張は、以下のようなものです。
- 出題が易しければスムーズに解け、自信と勢いがつく
- 試験のウォーミングアップとして機能する
- 問題番号順に解くことでマークミスが起きにくい
確かに、難易度の低い問題が出題された場合には、ペースをつかむうえで有効な戦略となります。しかしながら、基礎法学は毎年「初見の難問・奇問」が出題されやすく、運悪く最初にそのような問題に出くわすと、焦りと時間ロスを招きかねません。
このリスクを乗り越えられるのは、基礎法学に強い自信があり、かつ精神的に動揺しにくいタイプの受験生に限られるでしょう。
3-2 あえて後回しにする?──“確実に獲れる”ところから得点を積み上げる戦略
一方、最も多くの合格者や講師が推奨するのは「基礎法学は後回しにする」という戦略です。この方法の狙いは、ズバリ「リスクの最小化」。
- 試験序盤に高配点科目(行政法や民法)から着手し、得点の土台を早めに固める
- 基礎知識(一般知識)の文章理解から解くことで、足切りの不安を早期に解消する
基礎法学のような難易度の読みにくい科目を最後に回すことで、メンタルの安定を維持しつつ、得点効率の高い順に試験を進めることができます。
また、実際の失敗談として「基礎法学と憲法に時間を使いすぎて、得点源の行政法が時間切れになった」という声もあります。このようなリスクを避けるためには、全体戦略として“配点の高い順に解く”ことが非常に合理的です。
3-3 結論:自分に合った「解き順」は模試で見つけるのが鉄則
最終的な結論として、「この順番が正解」という絶対的なルールはありません。しかし、現実的には“最初に基礎法学を解かない”戦略の方が、多くの受験生にとって安全かつ効果的です。
LECの横溝講師をはじめとした多くの専門家も、「基礎法学から解くのは非推奨」としており、この方針は認知科学の観点からも裏づけられています。
たとえば、試験開始直後は緊張により脳の「認知負荷」が高まっており、そこへ抽象的で難解な基礎法学の問題をぶつけると、思考が停止してしまうリスクがあります。一方、行政手続法や文章理解など“型が決まっていて手をつけやすい問題”から始めれば、脳をスムーズに試験モードに切り替えることができるのです。
結局のところ、最も大切なのは「模試で試して自分に合った順番を見つけること」です。模試は本番のシミュレーションであり、自分の性格や得意・不得意をふまえて、最適な解き順をパーソナライズする絶好の機会です。
【参考表】主要な解き順パターンとその特徴
| 解き始めの科目 | 戦略意図 | メリット | リスク・注意点 | 向いているタイプ |
|---|---|---|---|---|
| 基礎法学から | 問題番号順で解く/マークミスを避ける | 問題が易しければ勢いに乗れる | 難問に当たると精神的ダメージが大きく、時間を浪費する | 精神的に強く、基礎法学が得意な人 |
| 行政法・民法など高配点科目から | 得点源を早めに確保 | 確実に点数を積み上げられ、安心感が得られる | 他科目が後回しになり、配点バランスに注意が必要 | 得点計画を重視し、法令科目が得意な人 |
| 一般知識・文章理解から | 足切りを早めに回避 | 読解力が活きる序盤戦で勢いに乗れる | 法令科目にかける時間が足りなくなる恐れ | 文章理解が得点源の人、足切りが不安な人 |
第4章 「対策不要論」は危険!──基礎法学とどう向き合うべきか?
4-1 なぜ「捨て科目」と言われるのか?その背景と理由
行政書士試験において、基礎法学はよく「捨て科目」と呼ばれます。その背景には、以下のような理由があります。
- 配点が低すぎる:全体300点中たった8点(約2.7%)しかない
- 時間対効果が悪い:出題範囲が広く、網羅的に勉強しても得点につながりにくい
- 奇問・難問の出題リスク:対策しても正答できない“不可避問題”が毎年のように出る
こうした要因から、「だったら最初から捨てて、行政法や民法に集中した方が効率的では?」という考えが生まれやすくなります。
一見すると合理的に思えるこの考え方。しかし、それには重大な見落としがあります。
4-2 “あと4点”で落ちる現実──平均で考えるのは危険
「配点が低いから、4点くらい失っても大丈夫だろう」というのは、統計的に見て非常に危険な発想です。
行政書士試験は絶対評価制度であり、合格ラインは常に180点以上と固定されています。そして実際、最も多くの不合格者が集中しているのは「170点台後半」というボーダー付近です。
つまり、「あと4点あれば…」という“惜敗”が最も多く発生している領域であり、その“たった1問(4点)”が合否を左右することは珍しくありません。
例えば、法令択一や記述でやや失点してしまった受験生が、基礎法学で1問取れていれば合格していた、というケースは現実に多々存在します。
このように、「平均的な価値」で見ると軽視されがちな基礎法学も、「合格ラインという絶対的な視点」で見ると、極めて重い意味を持つのです。
4-3 基礎法学は“保険”でいい──合格を守る最小限の備え
ここまでの検討を踏まえれば、合理的な結論は明白です。
「対策は不要」ではない。 ただし、「完璧を目指す必要もない」。 最小限の努力で“確実に1問(4点)取れる”状態にする。
これが、最もコストパフォーマンスに優れた向き合い方です。
この考え方を理解する鍵は、基礎法学を「合格を守る保険」として捉えることです。
- 想定外の失点が出たときの“補填”になる
- ボーダー付近での“生死を分ける得点源”になる
- 対策時間は15〜20時間程度で済む=“保険料”としては格安
この保険で得られる“保険金”は、他ならぬ「合格通知書」です。もう1年勉強し直すという時間的・精神的コストを考えれば、この4点の価値は計り知れません。
実践すべきは、以下の3ステップのみ:
- 基本テキストの該当箇所を1〜2回通読する
- 過去問を5年分ほど2周して、出題傾向に慣れる
- 模試で出たテーマは必ず復習し、知識を定着させる
“完璧ではないが、確実に1問は取れる”──この状態を作ることこそ、基礎法学における最適戦略なのです。
おわりに:基礎法学を“計算できる得点源”に変えるために
行政書士試験における「基礎法学」は、配点の少なさから軽視されがちな一方で、合否のボーダー付近では極めて重要な意味を持つ“低リスク・高インパクト”科目です。
本記事では、次の3つの視点から、基礎法学に対する最適な戦略を整理しました。
- 位置づけの再確認:確かに優先順位は高くないが、「あと1問で不合格」を防ぐための“最後の砦”となる
- 対策のあり方:「対策不要論」はリスクが高い。最小限の努力で“4点を死守”するというミニマム戦略が合理的
- 試験での扱い方:いきなり解かず、模試を通じて“自分に合った解き順”を確立することが得策
基礎法学を恐れる必要はありません。しかし、無対策で臨むほど甘い科目でもありません。
この科目の“本質”と“扱い方”を正しく理解し、学習時間と得点効率を最大化する戦略を立てることで、基礎法学は「捨てる科目」から「守りの得点源」へと変貌します。
もう1年勉強するリスクを回避するためにも、わずか15〜20時間の投資で、合格を確実に手繰り寄せる――
そのための最小努力こそ、最良の合格戦略です。

行政書士試験徹底解説
行政書士試験の完全攻略ガイド|ゼロから始める社会人のための難易度・勉強法・合格ロードマップ