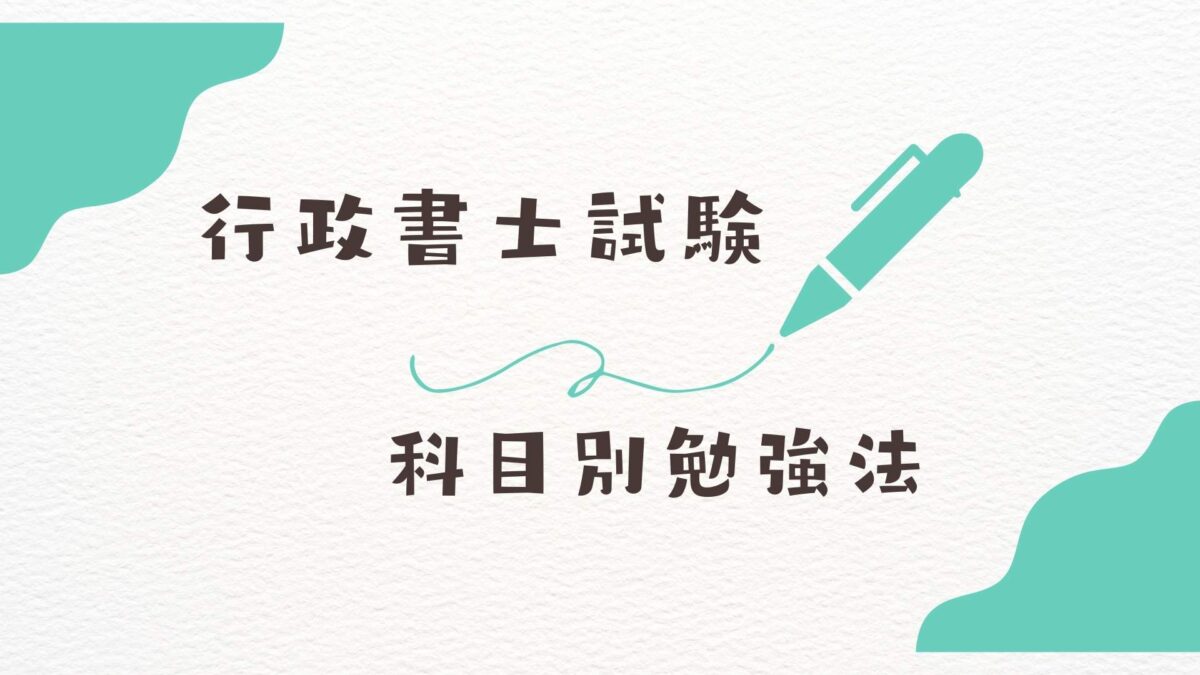はじめに:なぜ行政法は“合否を左右する最重要科目”なのか?
行政書士試験の合格を目指し、このページにたどり着いたあなたへ。まずはその志に、心から敬意を表します。
ところが、いざ「行政法」のテキストを開いた瞬間、その膨大な分量や馴染みのない専門用語に圧倒され、「何から始めればいいのか分からない…」と悩んでいませんか?
または、すでに学習を進めているにもかかわらず、知識が断片的で点数につながらず、不安や焦りを感じている方もいるでしょう。
そんな方にこそ、このガイドをお届けしたいのです。
本記事では、「なぜ行政法が行政書士試験において最重要科目とされるのか」、その客観的根拠とともに、広大な学習範囲をどのように整理し、着実に“得点源”へと変えていくのか、具体的な方法を明示していきます。
もう、闇雲に手探りで進む必要はありません。
この「行政法徹底攻略ガイド」が、あなたの合格への道を照らす羅針盤となることを願っています。
第1章 行政法が“最重要科目”と断言できる理由とは?
1.1 配点の大きさが示す「得点源」の実力
行政法は、行政書士試験の中でも圧倒的なボリュームと配点を誇ります。全体300点満点のうち、行政法の配点はなんと112点。これは全体の約37%に相当し、法律科目の中ではダントツのウエイトを占めています。
| 科目 | 出題数 | 配点 | 配点比率(目安) | 出題形式 |
|---|---|---|---|---|
| 行政法 | 22問 | 112点 | 約37% | 択一・多肢・記述 |
| 民法 | 11問 | 76点 | 約25% | 択一・記述 |
| 憲法 | 6問 | 28点 | 約9% | 択一・多肢 |
| 商法・会社法 | 5問 | 20点 | 約7% | 択一 |
| 基礎法学 | 2問 | 8点 | 約3% | 択一 |
上記の通り、行政法だけで試験全体の1/3以上を占めており、ここを得点源にできるかどうかが、合否に直結すると言っても過言ではありません。
1.2 あらゆる出題形式に対応する“唯一の科目”
行政法が特に重要視されるもう一つの理由は、択一式・多肢選択式・記述式のすべての形式で出題される唯一の科目であるという点です。
これは、単に知識の量だけでなく、深い理解と応用力が求められている証でもあります。たとえば、
- 択一式では、条文や判例の正確な知識が問われ
- 多肢選択式では、複数の事例を比較して判断する分析力が問われ
- 記述式では、論理的に条文・判例を適用し文章化する表現力が求められます
つまり、行政法は知識の「丸暗記」では通用せず、“運用できる知識”として使える状態に仕上げることが求められる科目です。
だからこそ、「行政法を制する者が行政書士試験を制する」と言われるのです。
第2章 行政法で多くの受験生がつまずく「3つの壁」とは?
行政法は合否を左右する最重要科目ですが、その学習に苦戦する受験生は非常に多いです。その背景には、以下の3つの“共通の壁”が存在します。
これらの障壁は、正しい戦略をもって取り組めば必ず乗り越えられます。本章では、その全体像を明らかにします。
2.1 壁①:範囲が広すぎる――6分野にまたがる構成を理解する
「行政法」とは一つの法律を指す言葉ではありません。実際には以下のような6つの法律分野を総称したものです。
- 行政法総論
- 行政手続法
- 行政不服審査法
- 行政事件訴訟法
- 国家賠償法
- 地方自治法
それぞれが独立した法体系・条文構造を持ち、試験では全分野から出題されます。そのため、学習範囲が非常に広く、「どこから手をつけるべきか分からない」と感じる受験生が多いのです。
この“範囲の壁”を乗り越えるには、全体像を把握し、優先順位をつけて学習に取り組むことが欠かせません。
2.2 壁②:概念が抽象的すぎる――日常とつながりにくい学習内容
民法などと異なり、行政法では「行政行為」「公権力の行使」「原告適格」など、抽象的かつ実生活では馴染みの薄い概念が頻出します。
たとえば「処分性」「取消訴訟」「義務付け訴訟」などの用語を、初学者がいきなり理解するのは難しく、具体的なイメージが持てないことが、学習の妨げになります。
この抽象性の壁を超えるためには、判例や具体例と結びつけて、「法律が現実にどう適用されるのか」を実感しながら学ぶことが効果的です。
2.3 壁③:専門用語の多さ――初学者泣かせの言葉の嵐
行政法では、「不利益処分」「聴聞」「法律の留保」「信頼保護原則」といった専門用語が頻繁に登場します。しかも、同じ“処分”という言葉でも、文脈によって意味が異なるため混乱を招きやすいのです。
初学者にとっては、この“用語の壁”が大きなハードルになります。言葉の定義を理解せずに先に進むと、後で内容がごちゃごちゃになり、復習が機能しなくなってしまいます。
だからこそ、最初の段階で基本用語の意味をしっかり押さえ、テキストや問題集の解説と照らし合わせながら、段階的に知識を積み上げていくことが重要です。
これら3つの壁は、誰もがぶつかる難所です。しかし、正しい学習戦略と段階的な理解をもってすれば、必ず突破できます。次章では、行政法攻略のための具体的な学習戦略を紹介していきます。
第3章 合格を引き寄せる行政法学習の「戦略マップ」
行政法は単なる暗記科目ではありません。だからこそ、がむしゃらに学習を始めるのではなく、「戦略的な道筋」を描くことが合格への近道です。
この章では、行政法を効率よく・着実に得点源に変えていくための全体戦略と、実行手順を4つのステップに分けて解説します。
3.1 合格に必要なのは“完璧”ではなく“180点”
多くの受験生がやってしまう最大の失敗は、「最初からすべてを理解しよう」としてしまうことです。
しかし、行政書士試験の合格基準は300点中180点。つまり、満点を取る必要はなく、戦略的に点を積み上げて合格ラインを超えることが重要です。
細かい判例や条文の細部まで最初から完璧に覚えようとすると、途中で挫折してしまうリスクが高まります。まずは「合格点主義」という考え方に切り替えることが、長く学習を継続するための第一歩です。
3.2 行政法攻略のための4ステップ学習法
行政法を効率よくマスターするには、以下の4つのステップを意識して学習を進めることが鍵となります。
ステップ①:全体像の把握
まずはテキストや講義を高速で一周し、行政法全体の地図を頭に入れます。理解度は5割程度で十分です。重要なのは「全体の構造」を捉えることです。
ステップ②:分野ごとのインプット
次に、行政手続法・行政事件訴訟法など、各分野ごとにテキストを丁寧に読み込み、基礎知識を整理していきます。知識の定着を意識して読み進めましょう。
ステップ③:徹底的なアウトプット
インプットした内容は、すぐに過去問で確認します。問題を解くことで、「どの知識が、どのように問われるか」を実践的に学び、知識が使える形に変わります。
ステップ④:戦略的な復習
間違えた問題や曖昧だった知識を中心に、テキストに戻って周辺情報を再確認します。復習を通じて、知識の穴を潰し、理解を深めていきましょう。
この4ステップのサイクルを、分野ごとに何度も繰り返すことが、合格への確かな実力を築く最短ルートです。
3.3 黄金比「インプット3:アウトプット7」が意味するもの
学習時間の配分として意識すべきは、「インプット3:アウトプット7」という黄金比です。
多くの初学者が「まずは全部覚えてから問題を解こう」と考えがちですが、それでは非効率です。行政書士試験で求められるのは、「知っている」ではなく、「使える」知識です。
つまり、重要なのは条文・判例を具体的な事例にどう当てはめるかという運用力。この力は、問題演習を通じてしか養えません。
また、間違えた問題は、あなたの理解の弱点を教えてくれる最高の教材です。その都度しっかりと分析し、復習に活かすことが知識の定着に直結します。
だからこそ、学習時間の7割をアウトプットに振り向けることが、最短合格への合理的な学習スタイルなのです。
第4章 分野別・行政法 完全攻略ルート
4.1 行政法総論(一般原則)
――抽象的な原則をどう理解し、どう得点に結びつけるか?
抽象概念が多い“行政法総論”は「土台」として軽視できない
行政法総論は、行政法全体に共通する原則や基本的な考え方を学ぶ分野です。条文ベースの学習が中心となる他の分野と比べ、こちらは条文そのものよりも抽象的な理念や考え方が問われるのが特徴です。
たとえば、「法律による行政の原理」「信頼保護の原則」「比例原則」といったキーワードは、条文化されていない場合もありますが、判例や学説を通じて体系化されています。
このように、行政法総論は初学者にとって“つかみどころのない難しさ”がありますが、行政手続法・行政救済法の理解にも直結する、非常に重要な基礎知識です。
頻出テーマ:4つの基本原則は必ず押さえる
行政法総論で特に頻出となるのが、以下の4つの基本原則です。それぞれの趣旨と適用場面を理解しましょう。
- 法律による行政の原理
行政活動は、必ず法律の定めに基づいて行われなければならないという原則です。 - 法律の優位
行政は、憲法や法律に違反することなく行われるべきであるという大原則です。 - 法律の留保
国民の権利義務に関わる行政行為には、法律の根拠が必要とされるという原則です。 - 信頼保護の原則
行政庁の発言や行動に対して国民が正当に期待して行動した場合、その信頼は保護されるべきという考え方です。たとえば、許可を出しておいて後になって突然覆すような行政行為は原則として許されません。
学習ポイント:判例ではなく「原則の意味と趣旨」に注目する
この分野では、細かな判例の暗記にこだわる必要はありません。大切なのは、各原則が「何のために存在するのか」「誰を守るためのものか」といった本質的な意味・趣旨を理解することです。
たとえば、「信頼保護の原則」は、行政の継続性や市民との信頼関係を守るために機能しています。このように背景にある価値観をつかむことで、抽象的な内容でも実感をもって学ぶことができます。
過去問では、こうした原則が具体的な事例にどう適用されるかを問う設問が多いため、「原則と具体例のつながり」を意識しながらアウトプット演習に取り組みましょう。
4.2 行政手続法
――「処分前」のルールを制す者が、行政法の基礎点を制す
明文化された“手続きルール”をいかに押さえるか
行政手続法は、行政庁が国民に対して許認可や不利益処分などを行う際、その前段階で必要とされる手続的ルールを定めた法律です。
この法律の最大の特徴は、判例や理論よりも条文の正確な知識が点数に直結するという点にあります。
つまり、ここは「覚えた分だけ点が取れる」数少ない高効率な得点源。手続きの流れや条文の要件を正確にインプットできれば、確実に得点を積み上げられる分野です。
頻出テーマ:「申請に対する処分」と「不利益処分」の違いを徹底整理
行政手続法では、以下の2つの処分形態の違いを明確に理解しておくことが極めて重要です。
- 申請に対する処分:
国民から「許可してほしい」と申請があった場合に、行政庁が許可・不許可などを判断する手続き。 - 不利益処分:
営業許可の取消しなど、すでに与えられていた権利・利益を行政が制限・剥奪するような手続き。
この2つの処分には、行政庁に課される義務や手続的要件が異なっており、それがそのまま試験に問われます。頻出の比較項目は以下の通りです。
| 比較項目 | 申請に対する処分 | 不利益処分 | 関連条文 |
|---|---|---|---|
| 審査基準・処分基準 | 設定義務(審査基準) | 努力義務(処分基準) | 5条・12条 |
| 基準の公表 | 原則:義務 | 努力義務 | 5条・12条 |
| 標準処理期間 | 設定努力義務 | 規定なし | 6条 |
| 理由の提示 | 拒否の場合:義務 | 原則:義務 | 8条・14条 |
| 意見陳述の機会 | 不要 | 原則必要(聴聞・弁明) | 13条 |
これらの違いは暗記に頼るだけでなく、「なぜ違いがあるのか」「どのような場面でその条文が適用されるのか」を理解することが得点アップにつながります。
学習ポイント:「条文から理解する」姿勢が合格を分ける
行政手続法では、判例や理論よりも条文の構造を正確に読み取れるかどうかがすべてです。
対策としては、テキストを読みながら自分で比較表を作ってみるのが効果的です。さらに、過去問では必ずと言っていいほど出題される「申請処分 vs 不利益処分」の違いを軸に、条文ごとの役割と流れを頭に入れておくとよいでしょう。
また、「処分の前提となる正当な手続きがどう整備されているか」という視点で全体を捉えると、行政手続法の目的や背景が理解しやすくなります。
4.3 行政不服審査法
――「処分後」に使える内部救済制度を体系的に理解しよう
行政不服審査法とは何か? その役割と位置づけ
行政不服審査法は、行政庁が行った処分に対して国民が「納得できない」「見直してほしい」と考えたときに、裁判所ではなく、行政庁の内部でその是非を再審査してもらう制度を定めた法律です。
つまり、これは行政の“自己チェック機能”のようなものであり、外部的な救済手段(たとえば行政事件訴訟法)に進む前に活用される“内部救済制度”と位置づけられます。
行政手続法(処分前のルール)と、行政事件訴訟法(裁判で争う処分後のルール)との中間にある制度として、全体像を体系的に押さえることが重要です。
頻出テーマ:「審査請求の流れ」と「裁決の種類」
行政不服審査法の出題で必ず押さえるべきポイントは、次の2点です。
- 審査請求の手続きの流れ
誰が、どこに、どの期限までに、どのような方法で申し立てるか。これらを“フローチャート的に”理解しておくと記憶の定着が進みます。 - 裁決の種類と効果
審査請求の結論として出される「裁決」には、大きく分けて以下の3種類があります。 - 却下裁決:手続き的に不備がある場合(例:期間徒過や形式不備)
- 棄却裁決:手続きは有効だが、請求内容に理由がないと判断された場合
- 認容裁決:請求に理由があると認められた場合(処分の取消し・変更など)
これらの用語は意味だけでなく、「どういうときに、どの裁決になるのか」を具体例で理解しておく必要があります。
学習ポイント:他法との比較で理解を深める
行政不服審査法は、行政手続法や行政事件訴訟法と似た用語・手続が多いため、「どの法律が、どの段階のルールなのか」を区別する意識が大切です。
たとえば:
- 行政手続法:処分前のルール
- 行政不服審査法:処分後の行政庁による自己審査
- 行政事件訴訟法:処分後の裁判所による審理
このように時系列で整理し、全体の位置関係を頭に入れておくと、混同を防ぎやすくなります。
また、審査請求の流れは図解やフロー図を自作し、手続の各段階を視覚的に整理すると、記憶の定着にも効果的です。
4.4 行政事件訴訟法
――裁判による最終救済と「訴訟要件ビッグ3」の突破法
行政事件訴訟法とは?――国民が行政と対峙する“最後の手段”
行政事件訴訟法は、行政庁の処分によって権利や利益を侵害された国民が、裁判所に対して処分の取消しなどを求めるためのルールを定めた法律です。
この法律は、行政による違法な処分を司法がチェックする“最終救済手段”として機能しており、行政の行為に対して「法の支配」を貫く制度的な柱といえます。
他の行政法分野と比べて、ここでは特に判例の理解が重要視されます。なぜなら、訴訟の適格や利益の判断において、実際の裁判例が解釈と適用を大きく左右しているからです。
頻出テーマ:「訴訟要件ビッグ3」は毎年問われる超重要論点
とくに重要なのは、「取消訴訟」に関する次の3つの訴訟要件です。これらは毎年のように試験で狙われる鉄板テーマです。
- 処分性:行政庁の行為が、裁判で争う対象となる「処分」に該当するかどうか。
- 原告適格:訴えを起こす者が、その処分によって法律上の利益を害された“正当な当事者”であるか。
- 訴えの利益(狭義):たとえ勝訴しても実質的な救済効果がない場合、訴訟の利益が否定されてしまうため、その利益が具体的に存在するかどうか。
これらは単なる定義暗記ではなく、「なぜその判断になるのか?」という理由づけ(ロジック)まで問われるのが特徴です。
学習ポイント:判例を“丸暗記”ではなく“構造理解”せよ
行政事件訴訟法で得点を伸ばす最大のポイントは、重要判例の「構造」まで押さえることです。
特に以下の3要素をセットで整理する習慣をつけると、択一対策だけでなく記述対策にも効果絶大です。
- 事案:どんな行政行為・状況だったか(例:ダム建設で保安林指定を解除)
- 争点:法的に何が問題となったか(例:周辺住民に原告適格があるか)
- 判旨:裁判所の結論とその理由(例:原告適格あり。保安林制度は住民の個別的利益も保護している)
このような整理を通じて、「なぜこの訴訟要件が問題になり、どう結論づけられたのか」を説明できるようになることが理想です。
また、行政事件訴訟法は、記述式問題の出題対象としても頻度が高く、判例の理解がそのまま記述力につながります。単なる知識で終わらせず、思考プロセスごと定着させる訓練を意識しましょう。
4.5 国家賠償法
――短くても奥深い!条文と判例で学ぶ“国家責任”の基本構造
国家賠償法とは?――行政の違法に対する金銭的な救済制度
国家賠償法は、行政機関の違法な行為や施設管理の不備によって損害を受けた国民が、国や地方公共団体に対して金銭的な賠償を請求できるよう定めた法律です。
条文数はわずか6条とコンパクトですが、その分、条文の一語一句の理解と、関連判例の解釈が極めて重要となります。特に出題頻度が高いのが、第1条と第2条の責任構造の違いです。
頻出テーマ:「1条責任」と「2条責任」の違いを完全整理せよ
国家賠償法の中心は、次の2つの責任類型です。それぞれの対象・根拠・要件を明確に理解しておく必要があります。
| 比較項目 | 第1条(公務員の違法行為) | 第2条(営造物の設置・管理の瑕疵) |
|---|---|---|
| 責任の対象 | 公務員の職務上の行為 | 公の営造物(道路・河川など) |
| 加害主体 | 公務員(国家・地方公共団体が賠償) | 国や地方公共団体 |
| 必要な要件 | 故意・過失+法令違反 | 善管注意義務違反または危険の存在 |
| 責任の性質 | 過失責任 | 無過失責任に近い構造 |
| 判例による補足 | 職務行為性の判断がポイント | 通行人など第三者の安全配慮が争点 |
- 第1条の典型例:警察官が違法に逮捕・拘束したことで損害が発生したケース
- 第2条の典型例:老朽化した道路のガードレールが破損し、通行人が転落したケース
このように、両条文は「加害者の主体」「責任の種類」「必要となる立証内容」がまったく異なるため、混同しないように明確に線引きして覚えることが不可欠です。
学習ポイント:判例で“どちらの条文が適用されるか”を判断する訓練を
国家賠償法の過去問では、「このケースは1条か2条か?」を判断させる出題が頻出です。
そのため、単なる条文の暗記だけでは対応できません。実際の事例に対して「①加害主体は誰か」「②行為なのか施設の不備なのか」「③違法性や過失の有無はどうか」という観点から、条文の適用を論理的に導けるようになる必要があります。
また、国家賠償法は記述式でも出題されやすい分野です。判例のロジックを文章で再現できるよう、要件ごとに整理しながらインプットしていきましょう。
4.6 地方自治法
――“出るところだけ”を狙い撃つ!範囲と効率のバランス戦略
地方自治法は「完璧主義NG」の代表格
地方自治法は、都道府県や市町村といった地方公共団体の組織や権限、住民の関与制度などを定める法律で、条文数は2000条を超える圧倒的ボリュームを誇ります。
しかし、行政書士試験においての出題数は非常に限られており、「出題数に対して範囲が広すぎる」という、学習効率の悪さが最大のネックです。
だからこそ、地方自治法は深追いせず、出題頻度の高いテーマだけを重点的に学ぶ“選択と集中”の戦略が不可欠です。
頻出テーマ:過去問が証明する「出るところしか出ない」事実
地方自治法では、以下のような“毎年狙われる鉄板テーマ”に的を絞るのが最も効果的です。
- 住民の直接請求制度
条例の制定・改廃請求、事務監査請求、解職請求(リコール)など。署名数の割合や手続期限など、数字に関する出題が多い。 - 住民監査請求・住民訴訟
監査請求を前提とした住民訴訟の流れや、対象となる違法行為の範囲などが問われる。 - 公の施設の利用関係
図書館や公民館といった“公の施設”における管理と利用のルール(私人との契約関係との違いなど)。 - 議会と長(知事・市町村長)との関係
議会による不信任決議、専決処分、再議など、地方議会と首長の対立構造に関するルール。 - 数値を問う出題
「請求に必要な署名数は有権者の○分の1以上」「何日以内に通知・決定をしなければならないか」など、正確な数値の暗記がそのまま得点に直結します。
学習ポイント:「覚えるべき数字」に絞って得点を狙う
この分野では、テキストの全範囲を網羅する必要はまったくありません。むしろ、Aランク・Bランクなど出題頻度に応じて論点が整理された教材を使い、重要度の高いテーマに絞って取り組むことが最大の攻略法です。
とくに、“数字の問題”は確実に得点できるボーナス問題と捉え、語呂合わせや暗記カードを活用して確実に押さえましょう。
例:
- 条例制定請求 → 有権者の50分の1以上
- 解職請求 → 有権者の3分の1以上
- 再議の議決 → 議員の3分の2以上の出席・そのうち3分の2以上の同意 など
このような「数字の決まりごと」を確実に押さえることが、最小限の努力で最大限の効果を得るためのコツです。
第5章 行政法の学習効率を最大化する教材とその使い方
行政法を得点源に変えるためには、正しい学習戦略だけでなく、自分に合った教材を選び、それを正しく使いこなすことが不可欠です。
ここでは、行政法対策におけるテキスト・問題集・過去問の選び方と、最大限に活用するための具体的なポイントを解説します。
5.1 テキスト選び:レベル別に選ぶ“最適な一冊”
行政法のテキストは、どれも一見すると同じように見えますが、構成や難易度、解説スタイルには明確な違いがあります。自分のレベルや学習スタイルに合わせた選択が非常に重要です。
初学者・法律が苦手な方におすすめ
- 図解やイラストが豊富で、視覚的に理解しやすい構成
- 条文や制度の背景にある考え方を、平易な言葉でかみ砕いて説明してくれるもの
おすすめシリーズ例:
- 『合格革命 行政書士 基本テキスト』
- 『みんなが欲しかった!行政書士の教科書』
中級者・法学経験者におすすめ
- 情報が網羅的で、判例の論理構造や法理にもしっかり踏み込んだもの
- 読み応えがある分、理解力と応用力の養成に最適
おすすめシリーズ例:
- 『うかる!行政書士 総合テキスト』シリーズなど
5.2 問題集選びと“シリーズ統一”の重要性
問題集は、テキストと同一シリーズのものを使うのが鉄則です。
理由は以下のとおりです:
- 出題範囲・用語・論点の表現が完全に連動しており、テキストとの往復がスムーズ
- 解説と対応ページが明示されているものも多く、復習効率が大幅に向上
逆に、異なるシリーズを組み合わせると、「テキストで説明がない問題が出る」「用語の使い方が違う」といったストレスが生まれ、学習効率が落ちます。
シリーズを揃えることで、「インプット→アウトプット→復習」のサイクルを自然に回すことができ、理解と定着のスピードが格段に上がります。
5.3 過去問の活用術:最強のアウトプットトレーニング
過去問は、単なる“模擬試験”ではなく、出題傾向の分析・知識の定着・応用力の養成に使える「最高の教材」です。
どのくらい解くべきか?
最低でも5年分、可能であれば10年分は取り組むのが理想です。これにより、重要論点の“繰り返し出題パターン”が自然に身につきます。
どう解くべきか?
ただ解いて丸付けするだけでは意味がありません。以下の方法を実践しましょう:
- 選択肢を解剖する
正解・不正解を問わず、すべての選択肢について「なぜ正しいのか」「なぜ間違っているのか」を、条文・判例に基づいて説明できるようにする。 - 最低3周は繰り返す
1周目:全体像の把握
2周目:理解の強化と誤答分析
3周目:スピードと正確性の向上
※目的を持って繰り返すことが重要です。 - “間違い”を宝の山に変える
間違えた問題こそ、あなたの弱点そのもの。それをテキストで再確認し、周辺知識ごと強化していくことで、最短で苦手を克服できます。
正しい教材を選び、それを正しい手順で使いこなすこと。これが、行政法を“最強の得点源”に変えるための実践的な第一歩です。
まとめ:行政法は“最大の壁”ではなく“最強の味方”になる
ここまで、行政書士試験の合否を左右する「行政法」について、全体戦略から分野別攻略法、教材活用法までを体系的に解説してきました。
最後に、要点を振り返っておきましょう。
- 行政法は試験配点の約37%を占める最重要科目。しかも、択一・多肢・記述の全出題形式に対応する唯一の科目であり、得点源にできれば合格が一気に近づく。
- 学習の基本戦略は「インプット3割:アウトプット7割」。知識を“使えるかたち”で運用できるよう、演習中心の学習サイクルを確立することが大切。
- 6分野それぞれに攻略ポイントがある。
行政法総論では抽象原則の理解、行政手続法では条文の精読、行政不服審査法と行政事件訴訟法では制度の構造理解と判例対策、国家賠償法では1条・2条の使い分け、地方自治法では出題頻度の高い論点への絞り込みが鍵。 - 過去問は“解剖”してこそ意味がある。全選択肢の正誤理由まで分析し、「考え方の型」を自分の中に定着させていく。
行政法は、初学者にとって最初に立ちはだかる大きな壁かもしれません。しかし、正しい地図(戦略)と道具(教材)を手に入れたあなたにとって、もはや“暗闇の迷路”ではありません。
この科目をしっかり攻略できれば、あなたの合格はぐっと現実的になります。
行政法を“試験最大の難関”から、“合格を引き寄せる最強の武器”へと変えていきましょう。
あなたの挑戦を、心から応援しています。

行政書士試験徹底解説
行政書士試験の完全攻略ガイド|ゼロから始める社会人のための難易度・勉強法・合格ロードマップ