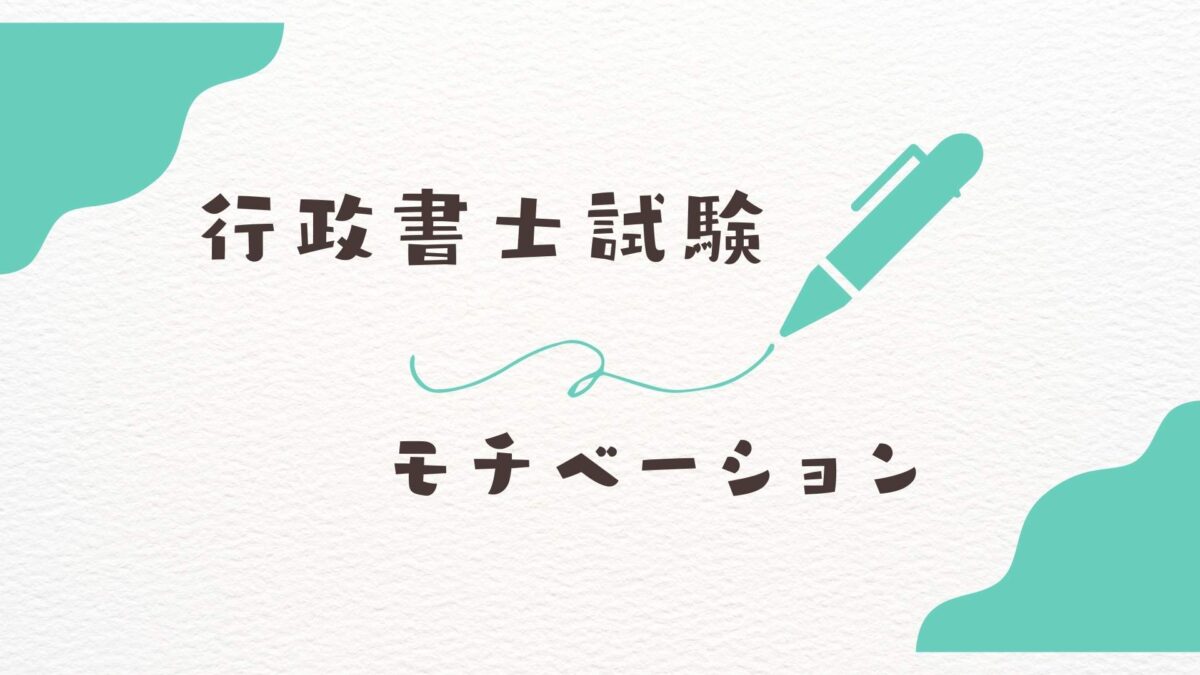不合格という現実を受け入れ、次の合格に向けて歩き出す
行政書士試験は、法律系国家資格の中でも比較的チャレンジしやすく、合格後には独立開業も視野に入る魅力的な資格です。しかし、毎年の合格率は10〜15%程度にとどまり、挑戦する人の多くが一度は不合格を経験するという現実があります。これは、能力の有無ではなく「誰にでも起こりうる結果」であることを意味しています。
私自身も経験しましたが、仕事や家庭と両立しながら勉強に取り組んできた社会人や主婦・主夫の方にとっては、不合格という結果は大きな挫折となりがちです。積み上げた時間、犠牲にしたプライベート、家族の支援──それらが実を結ばなかったとき、人は強い自己否定感や焦燥に襲われます。
しかし、大切なのは「この悔しさをどう使うか」です。落ち込むこと自体は自然な反応ですが、そこで立ち止まってしまっては、次への道が閉ざされてしまいます。
本記事では、独学に限界を感じた受験経験者、とりわけ社会人受験生に向けて、「不合格を次の合格の糧に変える」ための戦略を示します。第1部では、不合格者に共通する典型的な敗因を〈学習戦略〉〈勉強方法〉〈時間・メンタル管理〉という3つの視点から明確に整理し、読者自身が「自分はどこでつまずいたのか」を客観的に振り返るための視座を提供します。
続く第2部では、その敗因分析を踏まえて、再挑戦に必要な具体的アクション──精神的な立て直し、成績通知書を活用した弱点の特定、そして効果的な学習環境の整備といった「再出発のロードマップ」を提案します。
この記事が、「もう一度挑戦したい」と思うすべての方にとって、前を向いて一歩を踏み出すための支えとなれば幸いです。
第1部|なぜ不合格だったのか?──典型的な落とし穴を徹底分析
行政書士試験に落ちる人の“兆候”とその背後にある根本原因
| よくある症状(あなたにも当てはまる?) | 考えられる主な原因 | 補足・参考コメント |
|---|---|---|
| テキストや講義は一通り終えたのに、本番の点数が伸びない | アウトプット不足。知識を“使う”訓練が不十分 | インプットに偏り、演習の量と質が足りない |
| 過去問は何周も解いたが、本試験では対応できなかった | 解答を“覚えただけ”。法的思考力が不足している | 条文や判例の背景理解が浅く、応用が利かない |
| 法令科目は合格点付近だが、一般知識で足切りされた | 一般知識の対策が後回しor軽視されていた | 最低ライン(24点)を切ると即不合格になる科目 |
| 択一はそこそこ得点できたが、記述で大きく失点した | 記述式対策が直前期まで手つかず | 40字以内で論点を整理する訓練が不足していた |
| 教材を複数買ったが、どれも中途半端で終わった | “教材コレクター化”による戦略の迷走 | 一つの教材に絞って反復できなかったことが原因 |
| 勉強計画通りに進まず、直前期に崩れた | 非現実的なスケジュール設定 | 家庭や仕事を考慮した設計になっていなかった |
| 一人での学習が続かず、途中でやる気が切れた | 孤独な環境によりモチベーションが枯渇 | 講師や仲間からの刺激・支援が不足していた |
1.1 戦略ミスが招く不合格──間違った「学びの方向性」
行政書士試験における不合格には、共通する“戦略上の誤り”が存在します。合格を左右するのは、単なる努力量だけではなく、「何に、どのように時間とリソースを配分したか」という選択そのものです。ここでは、多くの不合格者が陥りやすい代表的な戦略ミスを4つの切り口から見ていきます。
インプットばかりに偏っていた──「わかったつもり」で止まっていないか
テキストを読んだ、講義を視聴した──これらはいわゆるインプット学習です。しかし、それだけで満足してしまい、実際に知識を使う「アウトプット」学習を疎かにしていた受験生は少なくありません。
問題演習を通じて、自分の知識が使える形で定着しているかを検証することこそ、実力養成の鍵です。インプットだけでは「理解したつもり」止まりになり、本試験で求められる応用力や判断力は育ちません。
過去問の「正しい使い方」を知らなかった
「過去問は繰り返し解いた」という方でも、点数に結びつかなかった場合、その使い方に問題がある可能性があります。
過去問学習の本質は、問題と正解を“覚える”ことではなく、なぜその選択肢が正しく、他は誤りなのかを深く理解することにあります。条文・判例・制度趣旨に立ち返り、「法律的思考プロセス」を身につけることで、初見の問題にも対応できる“応用力”が育まれるのです。
足切り・記述対策が不十分──「配点構造」を甘く見ていた
行政書士試験には2つの“落とし穴”があります。それが「一般知識の足切り」と「記述式の大配点」です。
- 一般知識等科目では、14問中6問正解(24点)に満たなければ、法令等科目でどれだけ得点していても即不合格。
- 記述式問題は1問20点×3問で合計60点。択一で高得点を取っても、記述の失敗が致命傷になることもあります。
にもかかわらず、「記述は後でやればいい」「一般知識はなんとかなる」という甘い見通しのまま直前期を迎えてしまったケースが多く見られます。試験制度の構造を理解し、それに即した対策を早期から講じることが合格の前提条件です。
時間配分を見誤った──「全科目を平等に」は非効率
行政法と民法で全体の約6割の配点があるにもかかわらず、商法・基礎法学・一般知識等といった周辺科目に過剰に時間を割いてしまった受験生も少なくありません。
「すべての科目を均等にやらなければ不安」という心理は理解できますが、行政書士試験は満点を取る必要がない“相対的な合格基準”です。配点の高い科目に重点的に時間を投下し、その他は必要最低限に抑える──これが合格のための合理的なリソース配分です。
このように、学習戦略における判断ミスは、どれも一見すると「真面目な努力」に見える落とし穴です。大切なのは、「努力の質」と「努力の向かう方向性」を見直すこと。次章では、さらに具体的な学習方法の改善点に踏み込んでいきます。
1.2 正しく学ばなければ意味がない──“使えない知識”を生む学習方法の落とし穴
たとえ学習時間を確保できていたとしても、勉強のやり方そのものが間違っていれば、得点にはつながりません。ここでは、行政書士試験の受験生が陥りがちな学習法上のミスを3つの視点から解説します。
丸暗記に頼っていた──「なぜ?」を考える力が不足していた
条文や判例の“結論だけ”を覚える学習は、行政書士試験では通用しません。少しひねった出題や、初見の事例に対応するには、制度趣旨や法的価値判断といった背景を理解し、自分の頭で考える力が必要です。
例えば、
- なぜその条文が存在するのか?
- なぜその判例がそう判断したのか?
といった問いに自分なりの言葉で答えられることが、応用力の土台になります。特に、記述式問題ではこの「なぜ?」の理解があるかどうかが、得点を大きく左右します。
教材の選び方を誤った/手を広げすぎた
独学受験生にとって、教材選びは命運を分ける要素のひとつです。古い情報のままの市販教材を使っていたり、自分のレベルに合っていない難解な教材に手を出したりすると、学習の効率が著しく下がります。
また、複数の教材に手を出してしまい、どれも中途半端に終わる「教材コレクター化」も典型的な失敗パターンです。これは不安の裏返しでもありますが、「信頼できる1冊を繰り返す」ことが、合格への最短ルートであることは間違いありません。
法改正情報をキャッチアップできていなかった
行政書士試験は、その年の試験日時点で「施行されている法律」に基づいて出題されます。つまり、たとえ過去問や参考書でカバーされていても、法改正を踏まえていなければ意味がないのです。
独学では、法改正の情報を自力で集め、内容を把握し、学習に反映させるという高度な作業が求められます。しかも、それは毎年のように発生します。これを怠ると、「知らないうちに試験範囲外の知識を学んでいた」「重要な改正点に対応できなかった」といった深刻な事態を招きかねません。
学習方法の誤りは、どれも“努力しているのに報われない”という結果に直結します。正しい知識を、正しい方法で、正しく定着させる──これが行政書士試験で結果を出すための基本です。
1.3 時間と心のマネジメント──独学で乗り越えるには限界がある
行政書士試験において、学習内容そのもの以上に多くの受験生を悩ませるのが「時間管理」と「メンタル維持」です。特に仕事や家庭と両立しながら挑戦している社会人受験生にとって、この2つの課題は避けて通れません。ここでは、よくあるつまずきのパターンを整理し、その背景にある構造的な問題を読み解いていきます。
無理な計画で学習ペースが崩壊した
「毎日4時間勉強する」「1か月で1冊終わらせる」──意気込みとしては立派でも、現実の生活と噛み合っていないスケジュールは、すぐに破綻します。
行政書士試験の合格に必要とされる学習時間は、おおよそ800〜1000時間。これを1年間で消化しようとすると、平日でも2〜3時間、休日には5〜6時間の確保が必要になります。
しかし実際には、仕事の繁忙期、家庭の事情、体調不良などで予定通り進まない日が必ず出てきます。最初から「遅れる前提」でバッファを設けておかないと、焦りや自己否定が積み重なり、学習そのものを断念してしまうこともあります。
独学者の多くは、学習の全体像や必要なボリュームを正確に把握しないまま計画を立ててしまい、気づけば破綻している──このパターンに陥りがちです。合格者の多くが語るように、無理のない「継続可能なペース設定」こそが、長期戦を制する鍵となります。
孤独な環境に打ち勝てなかった
独学は自由度が高い一方で、孤独との戦いでもあります。わからないことをすぐに質問できる講師はいない。進捗を共有できる仲間もいない。壁にぶつかったときに相談できる相手がいない──こうした「ひとりで抱え込む状況」が、知らず知らずのうちにモチベーションを蝕んでいきます。
SNSで学習仲間を探したり、交流グループに参加したりする人もいますが、そうした環境を整えること自体に手間と時間がかかります。また、情報の質がまちまちで、逆に不安を増幅させてしまうケースもあります。
大手予備校が提供している「サポート環境」──講師への質問制度、学習カウンセリング、受講生同士の交流コミュニティなど──は、単なる“学習指導”にとどまらず、こうした孤独の緩和という側面でも非常に大きな価値を持っています。
時間の使い方と心のケアは、努力ではどうにもならない“構造的な壁”を含んでいます。独学で限界を感じたなら、それはあなたの意志の弱さではなく、「ひとりで抱えるには荷が重い仕組み」だったからです。だからこそ、仕組みそのものを見直すことが、次への一歩につながります。
第2部|来年こそ合格するために──リベンジ成功への具体的ステップ
2.1 まずは心を整え、冷静な自己分析から始めよう
行政書士試験に不合格だった直後は、悔しさや自己嫌悪に押しつぶされそうになるものです。「これだけ頑張ったのに」「もう一年やるなんて無理かも」と、再挑戦への気力すら失われる瞬間もあるでしょう。
しかし、その気持ちを無理に否定する必要はありません。落ち込むのは自然な反応です。大切なのは、感情に支配されるのではなく、そこからどう立ち直るかという“姿勢”です。
不合格という現実を、攻める材料に変える
まず最初に必要なのは、「不合格の自分」を冷静に見つめ直すことです。これは決して自分を責めることではなく、「何が足りなかったのか」を客観的に見つける作業です。
行政書士試験は合格率10%前後という厳しい試験であり、不合格という結果は決して珍しいことではありません。努力が実を結ばなかったとしても、それは能力の否定ではなく、“戦略や方法のどこかに改善点があった”というだけのことです。
だからこそ、自分自身を否定するのではなく、「課題の洗い出し」として事実を受け止めることが、リベンジ成功への第一歩になります。
得点通知書を“学習カルテ”として活用する
不合格になった際に送付される「成績通知書」は、単なる結果ではなく、極めて重要な分析ツールです。この通知書には、法令等科目と一般知識等科目の得点、記述式の得点などが科目別に記載されており、自身の弱点を可視化できます。
次のような観点で分析してみましょう:
- 足切りはなかったか?
一般知識等科目が24点未満だと、それだけで不合格となります。ここでつまずいていないかを確認しましょう。 - 主要科目(行政法・民法)で点が取れていたか?
配点の大きい科目で失点していた場合は、戦略的な立て直しが必要です。 - 択一式と記述式の得点バランスは?
択一が160点以上あっても、記述式で点が取れていなければ、記述対策の強化が必要です。 - 得点の偏りがないか?
ある特定の分野だけが極端に低かった場合、その領域を重点的に補強すべきです。
このようなデータ分析を通して、「感覚的な反省」ではなく「根拠に基づいた戦略立案」へと変換していくことが、リベンジ合格の鍵となります。
不合格は、決して終わりではありません。むしろ、それまでの努力と経験を活かし、「より強い戦略」を構築できるチャンスです。まずは心を整え、次にすべきことを冷静に見極める。このプロセスこそが、合格への再スタートになります。
2.2 学び直すなら、やり方も変える──計画と環境の“再設計”が合格への近道
不合格の原因が見えてきたら、次にやるべきは「学習計画」と「学習環境」の見直しです。前年と同じやり方を繰り返しても、同じ結果になる可能性が高い。だからこそ、“ゼロベース”でスケジュールと学習環境を再構築することが、合格への道を開きます。
再受験組に最適な学習スケジュールとは?
一度受験を経験したことで、基礎的な知識や出題傾向に対する“感覚”は身についています。しかし同時に、知識の抜け落ちや偏り、曖昧な理解が残っていることも少なくありません。
そのため、再挑戦の学習計画は「前年の焼き直し」ではなく、次のような段階的アプローチが理想です:
- スタート期(試験終了直後〜2月)
→ 全科目をざっくりと通読し、忘れている箇所や曖昧な点を洗い出します。特に前年に苦手だった分野には時間を多めに確保。 - 中期(3月〜8月)
→ 本格的なアウトプット期。過去問や予想問題集を用い、「なぜその選択肢が正解か」を説明できるレベルまで掘り下げます。記述式の練習もこの時期から着手。 - 直前期(9月〜試験当日)
→ 模試を活用して本番形式でシミュレーション。苦手分野の絞り込みと記述の強化に注力。精神面の調整も忘れずに。
再挑戦でも、必要な学習時間は800〜1000時間が目安です。「一度やったから少なくて大丈夫」と思わず、初学者並みの学習量を確保する覚悟が必要です。
独学を続ける場合の“落とし穴”と対策
「通信講座は使わず、今回も独学で行く」という判断もありますが、独学ならではの課題を明確に認識したうえで対策を講じることが不可欠です。
以下は、独学継続時に特に注意すべきポイントです:
- 法改正への対応
→ 最新の法改正情報を自主的に収集・反映する手間と正確さが求められます。定期的に官報・予備校サイト・有力講師のSNSなどをチェックする習慣が必須。 - 学習のペース管理
→ 自分で進捗管理できないと、学習リズムが乱れます。スプレッドシートや学習アプリなどで「可視化」して、自己管理を徹底。 - メンタルとモチベーション
→ 孤独な学習環境で意欲が落ちないよう、SNSの学習コミュニティやStudyplusなどの共有アプリで仲間とゆるやかに繋がるのも一つの方法です。
再挑戦におすすめの教材ラインナップ
前年と同じ教材に加えて、以下のような“補強教材”の導入を検討しましょう:
- 判例付き六法(例:有斐閣『判例六法』など)
→ 条文の背景にある判例を体系的に理解でき、記述式対策にも有効。 - 重要判例集(例:TACやLECの判例解説本)
→ 特に憲法・行政法の深掘りに有効。記述でも問われやすい論点を整理。 - 記述式対策問題集(例:合格革命シリーズなど)
→ 40字で要点をまとめるトレーニングに特化。早期から着手すべき教材。
これらをどう使いこなすかが、合否の分かれ目になります。教材を「集める」のではなく、「戦略的に使いこなす」意識が重要です。
独学での再挑戦にはリスクと手間が伴いますが、それを認識したうえで戦略的に対応できれば、合格は十分に現実的です。環境の再構築は、「努力の質」を変えることに他なりません。
2.3 通信講座という選択肢──「時間」と「確実性」を買うという戦略的判断
独学での再挑戦に限界を感じたとき、次に検討すべきは「通信講座」の活用です。ただし、これは決して「楽をするため」の選択ではありません。むしろ、限られた時間を最大限に活かし、合格の確率を高めるための“合理的な投資”です。
とりわけ再受験生(リベンジ組)にとって、通信講座は「失敗の原因をピンポイントで補強する」ための有効なツールとなります。
リベンジ組向けカリキュラムの特徴と選び方
大手予備校では、受験経験者を対象とした「中上級者向けコース」や「再受験専用カリキュラム」が用意されています。初学者向けとは異なり、以下のような“弱点克服”に特化した設計がなされています。
| 予備校 | コース名 | 特徴 | 向いているタイプ |
|---|---|---|---|
| アガルート | 中上級総合カリキュラム | 司法書士・司法試験レベルの応用問題を交えた演習重視 | 思考力・応用力を鍛えたい人 |
| 伊藤塾 | 上級コース | 制度趣旨・条文の背景から理解を深める構成 | 理解型の学習を重視する人 |
| LEC | 横溝プレミアム合格塾 | ライブ感と演習のバランスに優れ、孤独対策にも効果的 | インプット・アウトプットのバランスが課題の人 |
| TAC | 答練本科生S | スーパー答練でアウトプット中心の実力強化 | 問題演習量を増やしたい人 |
「自分がなぜ落ちたのか」という分析結果に応じて、最も合致する講座を“処方箋”として選ぶことが重要です。
法改正・出題傾向・学習ペース──“仕組み”に任せて効率アップ
独学の最大のリスクは、「すべて自分でやらなければならない」ことです。法改正の確認、出題傾向の分析、進捗管理……すべてを自分で調査・判断・管理するには、時間もエネルギーもかかります。
通信講座を活用すれば、以下のような点が“自動化”され、学習そのものに集中できます:
- 最新の法改正情報が講義や教材に反映される
- 出題傾向を踏まえた対策がカリキュラムに組み込まれている
- スケジュールが事前に設計されており、迷いなく学習できる
こうした「仕組みの整った環境」は、特に時間の限られた社会人受験生にとっては、圧倒的なアドバンテージとなります。
孤独から抜け出す──学習仲間と講師による“支援のある独学”
長期戦である行政書士試験では、「学び続ける力」が合否を分けます。特に再挑戦では、精神的な消耗も大きくなりがちです。
通信講座には、以下のような“孤独を軽減する仕組み”が整っています:
- 講師への質問制度や個別カウンセリング
- 受講生同士の交流(オンライン・SNS・Zoomゼミなど)
- 定期的な模試や答練でのフィードバック
「誰かとつながっている」「見守られている」という安心感は、学習を継続する上での強力な支えとなります。特に一度挫折を経験した受験生にとって、この支援体制は非常に心強いものとなるでしょう。
通信講座を使うことは、「自分の意志が弱いから」ではありません。それは、合格という結果に向けて“最短距離で進むための仕組み”を導入するという、戦略的かつ実務的な選択です。
「時間」「確実性」「継続性」──この3つを補完してくれる環境に、自分の再挑戦を乗せること。それは、勝つための合理的な判断です。
結論|「不合格の理由」を武器に変え、次の試験で確実に合格をつかむ
行政書士試験で不合格になることは、決してあなたの能力や努力を否定するものではありません。実際、合格率が10%台という試験構造上、多くの受験生が一度はその壁に跳ね返されています。
しかし、不合格には必ず「理由」があります。
- インプットばかりでアウトプットが足りなかった
- 過去問の使い方が浅かった
- 足切り・記述式の対策が不十分だった
- 丸暗記に偏り、法的思考力が育っていなかった
- 教材を分散させて学習効率を落としていた
- 法改正情報を取りこぼしていた
- 無理な学習計画が崩れてしまった
- 孤独な環境でモチベーションが保てなかった
こうした敗因は、「自分に合っていなかった方法を選んでいた」というだけのことです。だからこそ、それを正確に見極め、修正することで、次の挑戦はまったく違う結果になる可能性を秘めています。
重要なのは、“前年の経験”を「失敗」として終わらせるのではなく、「合格のための分析データ」として活かすこと。自分の得点通知書や学習記録と向き合い、必要であれば通信講座という仕組みも活用しながら、自分に最適な戦略を練り直してください。
そして何より、もう一度チャレンジするあなた自身を誇りに思ってください。行政書士試験は「戦略と継続」で必ず突破できます。
不合格という経験があったからこそ、次はもっと強く、もっと賢くなれる。そう信じて、一歩ずつ前に進んでいきましょう。

行政書士試験徹底解説
行政書士試験の完全攻略ガイド|ゼロから始める社会人のための難易度・勉強法・合格ロードマップ