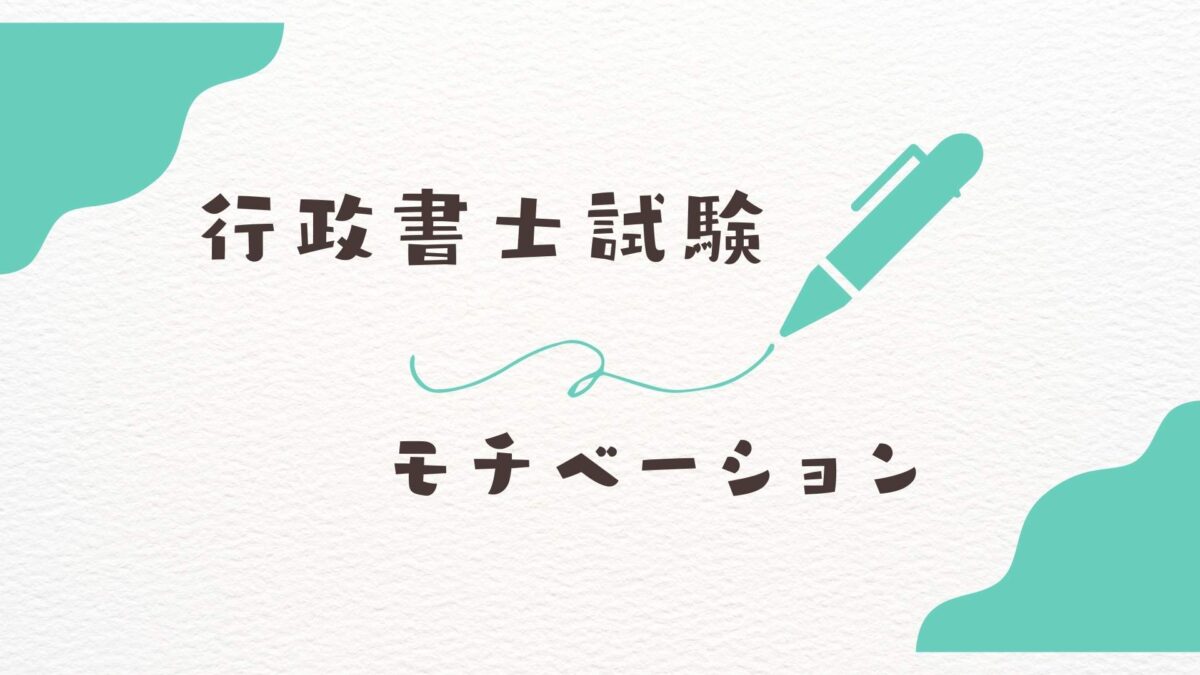「学歴が高ければ合格しやすい」は本当か?
「有名大学を卒業している」「法学部出身で法律には詳しい」——
そんな高学歴の方が、行政書士試験に挑戦することは珍しくありません。
ところが実際には、こうした“優秀層”が思わぬ不合格を喫してしまうケースも、決して少なくないのです。
彼らの失敗は、決して「努力不足」や「運が悪かった」といった単純な理由では片づけられません。
むしろ、学歴や過去の成功体験そのものが、行政書士試験における“落とし穴”になっている場合があります。
本記事では、高学歴者が行政書士試験に不合格となる背景にある、心理的バイアス・戦略的誤り・試験制度との適応ミスといった構造的要因を、現役行政書士の視点から徹底的に分析します。
「なぜ学力があるのに合格できないのか?」
その問いに明確な答えを出すことで、どんなバックグラウンドの方でも、合格に向けた“正しい戦い方”を選べるようになることを、本稿の目的としています。
第1章|高学歴でも陥る「3つの見えない落とし穴」
高学歴の受験生が行政書士試験で思わぬ不合格に見舞われる背景には、「勉強量」や「知識量」では説明できない、構造的な問題が潜んでいます。
それは、学歴に裏打ちされた成功体験が生む「思考の癖」や「学習アプローチ」が、行政書士試験という特殊な試験環境に噛み合っていないことに起因しています。
本章では、その代表的な3つの“見えない罠”──心理的、戦略的、そして環境的な要因について解説します。
1.1 心理的な落とし穴:過去の成功が生む「認知バイアス」
高学歴者にとって、これまでの学業経験は「自分のやり方は間違っていない」という強い信念につながりがちです。
しかし行政書士試験においては、この信念が逆に「過信」となり、次のような心理的バイアスを引き起こします。
- ダニング=クルーガー効果:知識が中途半端な段階で「理解している」と思い込み、本質的な学習を避けてしまう。
- 正常性バイアス:模試での低得点を「たまたま」と受け流し、根本的な学習戦略の見直しをしない。
- 自己流の学習法への固執:「講師のアドバイスよりも自分の方が正しい」という思い込みが、非効率なやり方を継続させてしまう。
このような思考のクセは、行政書士試験のように「得点力」で評価される実務的試験との相性が悪く、失点につながるリスクを高めてしまいます。
1.2 戦略的な落とし穴:学問的アプローチの“逆効果”
大学での学習では、「深い理解」「理論的思考」「多角的視点」が重視されます。ところが、行政書士試験ではこれらが必ずしも得点に結びつくとは限りません。
高学歴者がやりがちな失敗には、以下のような傾向があります。
- インプット偏重:講義視聴やテキスト読解に時間をかけすぎて、過去問演習(アウトプット)が後回しになる。
- 「理解」信仰:本質的な理解を優先し、「条文や判例の暗記は非知的」と軽視してしまう。
- 試験分析の軽視:「法律を学んでいれば解けるはず」と考え、出題傾向やひっかけパターンの研究を怠る。
これらは、「努力の方向性」がずれていることに他なりません。行政書士試験は、知識の“量”ではなく“使い方”が問われる試験なのです。
1.3 環境的な落とし穴:行政書士試験の「特殊なルール」に対する認識不足
行政書士試験には、大学受験や他の資格試験とは異なる“独特の構造”があります。
この試験制度の特性を理解していないと、いくら学力があっても不合格になる可能性が高くなります。
代表的な特徴は以下のとおりです:
- 絶対評価(6割=180点で合格):他人との競争ではなく、自己完結型の試験。だからこそ油断や完璧主義が致命傷になる。
- 配点の偏り:行政法・民法での得点が合否を左右する一方、商法や憲法ばかり勉強しても得点に直結しにくい。
- 一般知識の“足切り”:法令科目で高得点を取っていても、一般知識で24点未満だと問答無用で不合格。
大学での知識や勉強法だけでは対応できない「試験独自のクセ」に早い段階で適応することが、合格へのカギとなります。
第2章|プライドと認知バイアスが学習を阻むメカニズム
行政書士試験において、高学歴者の不合格を引き起こす最大の要因は、知識や能力の不足ではありません。
むしろ、過去の成功体験によって形成された“思考パターン”や“心理的なクセ”が、試験対策にブレーキをかけているケースが非常に多いのです。
この章では、「認知バイアス」「プライド」「完璧主義」「失敗への脆さ」といった心理的要素が、どのように学習行動に影響を与えるのかを、具体的に見ていきます。
2.1 過信の罠──「ダニング=クルーガー効果」がもたらす盲点
高学歴者がつまずく原因のひとつが、「自分はできている」という過信です。
特に法学部出身者が、「民法の基礎は理解している」「講義内容は一通り知っている」と思い込んでしまうことで、必要な演習量を確保しないまま本番を迎えてしまうケースは少なくありません。
これは心理学でいう「ダニング=クルーガー効果」に該当します。
この現象では、能力が未熟であるほど、自分の力量を正しく認識できずに過大評価してしまいます。
この過信が生む学習の弊害:
- 過去問演習の重要性を軽視し、インプット作業ばかりに偏る
- 模試の低得点を「たまたま」と楽観的に解釈し、対策を打たない
- 自分のやり方を過信し、他者からの助言に耳を貸さなくなる
このような心理状態では、本質的な改善ができず、試験本番でも同じ過ちを繰り返してしまいます。
2.2 プライドが妨げる「アンラーニング(学習棄却)」
高学歴者ほど、自分のやり方に強い信念を持ちやすい傾向があります。
その背景には、「これまでそのやり方で成功してきた」という体験があり、それを否定することが自己否定に感じられてしまうのです。
しかし、行政書士試験では、過去の成功体験を一度リセットし、ゼロベースで新しい学習法を受け入れる必要があります。
この“思考の上書き”こそが「アンラーニング」です。
アンラーニングが困難になると、以下のような悪循環が生まれます:
- 講師の助言を無視し、「自分のやり方」で失敗する
- インプット中心の学習を正当化し、演習不足のまま突き進む
- 模試の結果が悪くても「教材が悪い」「自分に合っていない」と外部要因のせいにする
この状態では、「どこをどう直すべきか」という視点が失われ、学習の改善サイクルが停止します。
2.3 完璧主義が引き起こす“非効率”な努力
行政書士試験は、300点満点中180点(=6割)を超えれば合格できる「絶対評価」の試験です。
にもかかわらず、高学歴者ほど「すべての論点を完璧に理解しなければならない」と考えがちです。
このような完璧主義は、一見すると向上心の表れに見えますが、試験戦略としては非常に非効率です。
完璧主義が陥る主な落とし穴:
- 出題可能性が低いマイナー論点に何時間も費やす
- 一つの科目にこだわりすぎて、全体の学習進捗が滞る
- 本試験で“捨て問”に固執し、時間を浪費する
行政書士試験は「すべてを理解する試験」ではなく、「限られた時間と知識で最大限の得点を取る試験」であるという視点が欠かせません。
2.4 失敗への耐性の低さと「心理的防衛機制」
これまでの人生で「失敗することが少なかった」という経験は、裏を返せば「失敗に慣れていない」ことを意味します。
模試の点数が伸び悩んだり、覚えた知識が定着しなかったりといった“つまずき”に直面したとき、自分を守るために働くのが「心理的防衛機制」です。
主な防衛反応の例:
- 合理化:「今回は問題が難しかっただけ」と失点の原因を自分以外に求める
- 否認:「本番ではきっと大丈夫」と根拠のない楽観に逃げる
- 無力感:「どうせやっても意味がない」と挑戦を放棄する(学習性無力感)
このような心の反応は自然なものですが、学習においては冷静な自己分析と軌道修正の妨げになります。
「模試の点数は学力ではなく、戦略の指標だ」と捉えることができるかどうかが、合否の分かれ目となります。
表1|行政書士試験で陥りやすい「認知バイアス」一覧とその具体例
| 認知バイアス名 | 定義 | 行政書士試験での典型例 |
|---|---|---|
| ダニング=クルーガー効果 | 知識や能力が乏しい人ほど、自分の実力を正しく評価できず、過信しやすい心理傾向 | 法学部出身者が「基礎はできている」と思い込み、過去問演習を軽視してしまう |
| 確証バイアス | 自分の信じたい考えや仮説に合う情報ばかり集め、反証する情報を無視する傾向 | 「理解が大事で暗記は不要」と思い込み、講師の指示する重要条文の丸暗記を軽視してしまう |
| 正常性バイアス | 不都合な現実を無視し、「自分は大丈夫」と根拠なく安心しようとする心理作用 | 模試で何度も基準点に届かなくても、「本番は何とかなる」と学習方針を見直さない |
| 完璧主義 | すべてを完璧にこなそうとするあまり、効率の悪い学習や過度な自己批判に陥る傾向 | 商法や会社法など配点の低い科目に何週間も費やし、行政法・民法の演習時間が不足する |
第3章|ズレた努力では報われない:高学歴者が陥る戦略ミスの正体
行政書士試験では、「どれだけ勉強したか」よりも、「どのように勉強したか」が結果を左右します。
高学歴者の多くは、知的能力には長けているものの、その努力の“方向性”が試験の特性とズレているために不合格となるケースが少なくありません。
この章では、特に多く見られる3つの戦略的欠陥——インプット偏重、試験構造の軽視、「理解」信仰による暗記の軽視——について解説します。
3.1 「わかったつもり」が危険信号──インプット偏重とアウトプット不足
高学歴の受験生は、講義を丁寧に聴き、テキストを読み込み、ノートをまとめるといった“インプット型”の学習に長けています。
ところが、行政書士試験では、インプットだけでは合格点に届きません。
重要なのは、知識を「理解している」ことではなく、「試験問題で使いこなせる」こと。
つまり、過去問を解く=アウトプットによって、実戦での処理能力を鍛えることが不可欠なのです。
失敗例としてよくあるのが:
- テキストを何度も読み直すが、問題演習を後回しにしてしまう
- 「覚える前にまず理解を」と考えすぎて手が止まる
- 模試で点が取れないが、原因分析をせず講義に戻る
これは、知識を安全なインプットの世界に留めておきたいという「回避的心理」でもあります。
アウトプットには失敗が伴うからこそ、苦手意識が強い人ほど避けがちなのです。
3.2 科目の勉強ではなく「試験の研究」を──構造理解の欠如
高学歴者の中には、「法律を深く理解していれば、どんな問題にも対応できる」と信じて疑わない人がいます。
しかし行政書士試験は、“法律の知識を問う試験”であると同時に、“出題形式という構造を攻略するゲーム”でもあります。
試験分析の軽視がもたらす問題:
- 頻出論点や出題パターンの分析をせず、手広く浅く学習してしまう
- 「ひっかけ」選択肢の傾向を知らずに、毎回同じミスを繰り返す
- 配点や時間配分の重要性を理解せず、戦略的に動けない
合格者の多くは、過去問を“知識の確認ツール”ではなく、“出題者の意図を読み解く設計図”として活用しています。
「どの条文・判例が、どのような聞かれ方をするのか」まで分析できて初めて、本番での得点力に変わるのです。
試験とは「正解を当てる技術」を試す場であり、「理解の深さ」を競う講義ではありません。
3.3 「理解こそすべて」の罠──暗記を軽視してはいけない理由
大学教育では、「理解力」「論理的思考力」「多面的な議論」が重視され、丸暗記はしばしば“知的でない”とみなされがちです。
しかし行政書士試験においては、一定量の“精度の高い記憶”がなければ、論理的判断すら成立しません。
誤った「理解重視主義」の典型例:
- 判例の「結論」だけ理解して「理由付け」や「要件」の記憶を怠る
- 「何となく分かった気がする」状態で満足し、精緻な復習をしない
- 「暗記より思考力が大事」と唱えながら、選択肢の読み比べに対応できない
法律の世界では、条文の定義や要件、判例のロジックなどを一言一句正確に覚えることが前提です。
それらが“弾薬”となって、法的思考という“エンジン”を動かします。
「理解」と「暗記」はどちらか一方ではなく、相互に支え合う存在であることを忘れてはいけません。
第4章|行政書士試験という“特殊なフィールド”に気づかないまま戦っていないか?
行政書士試験で高学歴者がつまずく大きな理由のひとつが、「この試験がどのような性質を持っているか」を正しく理解していないことです。
大学での学びや他の試験の感覚のまま臨んでしまうと、見えないルール違反を繰り返し、気づけば不合格という事態に陥りかねません。
この章では、行政書士試験が持つ3つの独自構造──「教育との断絶」「絶対評価の罠」「得点構造の歪み」について解説します。
4.1 大学での学びと試験対策は“まったく別の競技”
法学部での学習と、行政書士試験の受験勉強は、目的も方法も“完全に別物”です。
大学では多様な学説や議論が奨励されますが、試験では「通説+判例=正解」であり、明確な知識とその適用力が求められます。
違いを簡潔に整理すると以下のとおりです:
| 観点 | 大学の法学教育 | 行政書士試験 |
|---|---|---|
| 目的 | 理論の探究と学術的訓練 | 合格ライン(180点)突破 |
| 正解の基準 | 多様な見解や教授の解釈 | 判例・通説・条文の文言に基づく明確な正答 |
| 評価方法 | 相対評価(単位取得が前提) | 絶対評価(基準点に満たなければ不合格) |
| 曖昧さの扱い | 法の本質として扱い、議論対象となる | 得点の障害となるため排除される |
法学的素養があるほど「深く理解すれば対応できる」と思い込みがちですが、試験では“出題の型”に合わせた正確な処理力がすべてです。
4.2 「絶対評価」の試験が引き起こす2つの罠
行政書士試験は、180点以上(300点満点)を取れば全員が合格できる「絶対評価」制度を採用しています。
一見するとフェアな制度に見えますが、心理的には大きな落とし穴が潜んでいます。
失敗パターンは2つに分かれます:
- 油断型:「6割でいいなら余裕」と誤認し、学習密度が上がらない
- 完璧主義型:「確実に合格したい」と全範囲を完璧にしようとして非効率に
さらに、絶対評価ゆえの“誤った自己診断”も問題です。
例えば「本試験で178点だった。あと1問で合格だった」と思いがちですが、実際には学習戦略全体がズレていた可能性があります。
「惜しい不合格」が“あと一歩”とは限らない──この認識が戦略修正の鍵になります。
4.3 配点と足切りという“構造的トラップ”
行政書士試験には、得点配分や試験制度において“見逃せないクセ”があります。
これを理解せずに学習を進めると、本人の得意分野に関係なく、不合格という結果につながってしまいます。
特に注意すべきポイントは以下の3点です:
- 行政法・民法の超高配点:この2科目だけで180点満点中188点が配点されており、ここを外すと他が得意でも合格はほぼ不可能。
- 一般知識の足切り制度:法令科目が満点でも、一般知識で24点未満(=6問未満)だと自動的に不合格。
- 法改正と最新判例の影響:法学部時代の知識がそのままでは通用しない。特に民法の大改正(2020年)以降は、旧知識が“誤答”につながることもある。
行政書士試験は、単に“得意分野を伸ばす”試験ではなく、“重要なポイントに時間を集中させ、落とし穴を避ける”ための戦略ゲームです。
配点構造や制度的トラップを踏まえた学習計画こそが、合格に直結する最短ルートになります。
第5章|戦略を変えれば結果が変わる:思考と行動を“合格仕様”にアップデートせよ
ここまでの分析で、高学歴者が行政書士試験に不合格となる主な要因は、知識や能力の不足ではなく、「過去の成功体験に基づく思考様式」が試験とズレていることにあるとわかりました。
この章では、そうした“ズレ”を修正し、合格に直結する思考法・行動戦略・学習手法へと転換するための具体策を提示します。
キーワードは「アンラーニング」「メタ認知」「自動化」「戦術化」です。
5.1 プライドを脱ぎ捨てろ──「アンラーニング」と素直さの実践
高学歴者にとって最大のブレーキは、「自分のやり方が正しいはず」というプライドです。
しかし行政書士試験では、その“過去の成功体験”がむしろ合格の障害になります。
まず必要なのは、「大学の学力」と「資格試験の得点力」は別物であると明確に認識すること。
そのうえで、信頼できる講師やカリキュラム(LEC、アガルート、伊藤塾など)を選んだら、「完全に従う」という姿勢を持つことが重要です。
講師が「これは理由なく暗記してください」と言えば、理由を求めずにそのまま覚える。
これこそが、本試験で得点するための“実務的な素直さ”であり、「アンラーニング=学習のやり直し」の第一歩なのです。
5.2 メタ認知能力を鍛える──自分の勉強の“司令塔”になる
学習の質を大きく左右するのが「メタ認知力」、つまり自分の学習状況を客観的に把握し、修正できる力です。
合格する受験生はこの能力が高く、「模試で点が取れない理由」を分析し、「次にどう動くか」を冷静に判断しています。
強化のための具体的手法:
- 学習記録をつける:勉強した内容・時間・理解度を簡単にメモ。主観的な「頑張った感」を排除する。
- YWTで振り返る:「やったこと(Y)」「わかったこと(W)」「次にやること(T)」を1行で整理。
- 自己対話の習慣:「今の自分はなぜ不安か」「なぜ講師の助言に反発しているのか」など、自分の内面を言語化する。
メタ認知とは、自分の“学習の経営者”になること。現状分析→仮説→行動→振り返りのサイクルを自力で回せる人が、合格に近づきます。
5.3 科学的に正しい“点の取り方”を身につける
努力の方向性を合格に最短化するには、「正しい戦術」に基づいた学習が不可欠です。
特に行政書士試験では、以下の3ステップを徹底するだけで、得点効率が劇的に変わります。
- 即アウトプット学習:テキストで1単元学んだら、すぐに対応する過去問を解く。
- 問題演習の“分析型学習”:正誤の確認だけでなく、「なぜ間違えたか」「他の選択肢がなぜ誤りか」まで言語化。
- ノートは1冊に集約:復習効率を上げるため、気づき・補足・記憶すべきポイントをすべて1冊に集める。
知識を「蓄える」だけでなく、「使いこなす」ための学習構造を、意識的に設計しましょう。
5.4 習慣と心理の力で“やる気”に頼らない仕組みを作る
行政書士試験は中長期戦です。合格する人は、「やる気があるから勉強できる」のではなく、「やる気がなくても動ける仕組み」を構築しています。
おすすめの心理戦略と習慣化テクニック:
- If-Thenプランニング:「もし○○したら、△△する」と行動ルールを明文化(例:夕食後に必ず30分学習)。
- スモールステップの徹底:「2時間勉強する」ではなく「5分だけテキストを開く」から始める。
- “できた自分”を肯定する:結果よりも「今日も行動できた」ことを自分で褒める。
「継続の才能」は生まれつきではなく、設計の問題です。心理と習慣の力を味方にすれば、勉強は“自動化”できます。
5.5 合格から逆算する“戦略的学習スケジュール”の立て方
行政書士試験対策は、単なるToDoリストではなく、「配点に応じた時間配分」という“投資計画”として設計すべきです。
以下は、一般的な1年合格モデルの例です:
| フェーズ | 時期(目安) | 主な目的 | 重点科目 | 推奨行動 |
|---|---|---|---|---|
| 基礎構築期 | 11月〜4月 | 法令科目の全体像と基礎知識の定着 | 民法・行政法・憲法 | テキスト+論点別過去問で反復。完璧より7割理解を優先。 |
| 応用強化期 | 5月〜8月 | 知識の反復と記述・一般知識対策の開始 | 民法・行政法+一般知識 | 演習量を増やし、模試も活用。足切り対策をこの時期から着手。 |
| 直前期 | 9月〜本試験 | 得点力最大化と弱点補強 | 全科目(行政法優先) | 年度別過去問の時間演習。復習ノートを仕上げる。新論点は追わない。 |
学習時間の多さではなく、「どこに・どれだけ」かけるかが合否を分けます。
結論|行政書士試験とは「自己をマネジメントできる人」が突破できる試験である
行政書士試験は、学歴や学問的な理解力の有無によって合否が決まる試験ではありません。
この試験が本当に問うているのは、「自分自身を客観的に分析し、目的達成のために最適な戦略を組み立て、淡々と実行できるかどうか」という“自己マネジメント能力”です。
高学歴者であっても、不合格に終わる人は少なくありません。
しかしそれは能力が足りなかったのではなく、試験という「ゲームのルール」に合わせて、自分の学習スタイルを最適化できなかったことが原因です。
つまり、行政書士試験とは:
- 自分の思い込みや過信を手放し、
- 客観的なデータと構造分析に基づいて戦略を立て、
- 精度の高い記憶と実戦的な処理力を養成し、
- 限られた時間とリソースを「得点化」に集中投下し、
- 継続可能な習慣と心理設計でやり抜く
──そんな、“戦略的に自分を運営する力”がそのまま試される試験なのです。
だからこそ、学歴や肩書に関係なく、今この瞬間から「試験に最適化された自分」にアップデートすることが、合格への最短ルートになります。
成功の鍵は、才能ではなく、自己の“経営能力”にあります。

行政書士試験徹底解説
行政書士試験の完全攻略ガイド|ゼロから始める社会人のための難易度・勉強法・合格ロードマップ