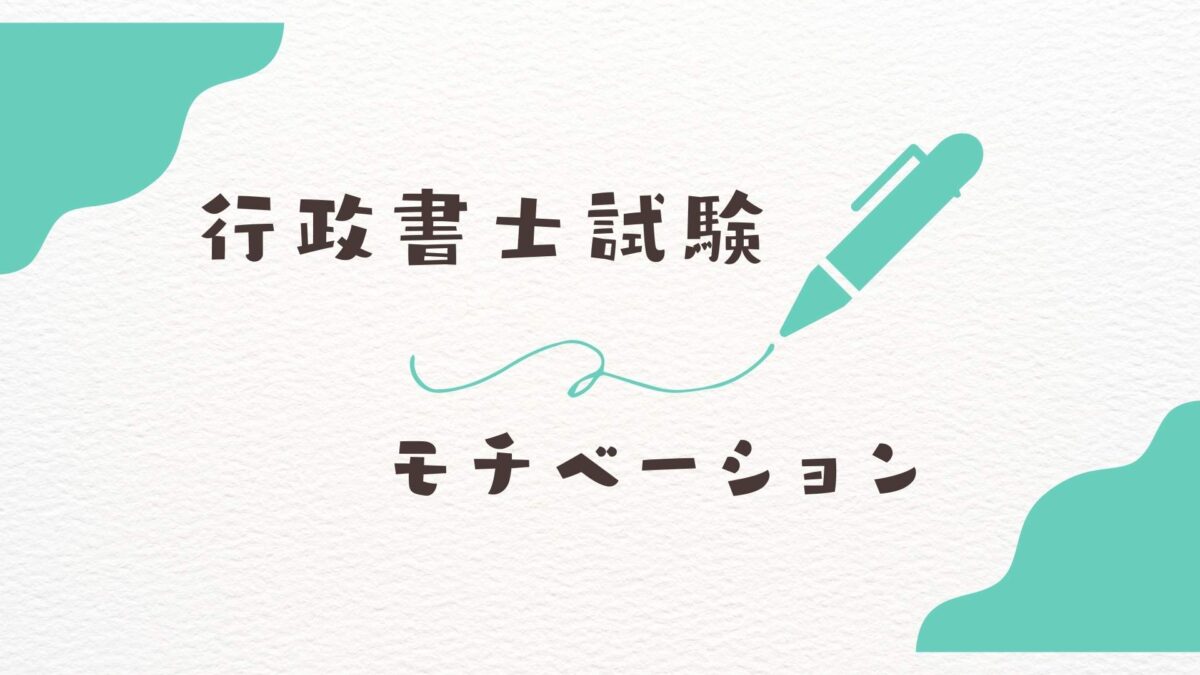直前期の不安を“合格への確信”に変えるために
行政書士試験が目前に迫る直前期——
多くの受験生が「ここまで頑張ったのに模試の点が伸びない」「何から手をつけていいか分からない」「合格できる気がしない」といった漠然とした不安に直面します。
これは、あなた一人に限った悩みではありません。
むしろ、最終的に合格を勝ち取った人の多くが、同じような心の揺れを経験しています。つまり、この時期の不安や焦りは、あなたが真剣に試験に向き合ってきた“証”なのです。
とはいえ、不安に振り回されていては、本来の力を発揮できません。
大切なのは、直前期を「戦略的に過ごす」こと。どんなに努力してきたとしても、この最終フェーズでの立ち回り次第で、合否は大きく分かれます。
本記事では、次の3つの柱に沿って、行政書士試験直前期の過ごし方を体系的に解説していきます。
- 【1ヶ月前】知識を得点力に変える“基盤固め”
- 【1週間前】体調・メンタルも含めた“仕上げ”
- 【前日】本番で実力を出し切る“整える日”
これらの指針は、予備校講師や合格者の実践例だけでなく、記憶の定着や集中力に関する脳科学・心理学の知見にもとづいています。
読み終えるころには、焦燥感は「やるべきこと」に明確化され、不安は「確かな準備」へと昇華しているはずです。
あなたが試験当日、自信を持って着席できるように──本記事がその後押しとなることを願っています。
試験1ヶ月前:得点につながる“完成度”を高める時期
この時期に取り組むべき学習法とは?
試験1ヶ月前は、新たな知識を追い求める時期ではありません。
この段階で最も重要なのは、これまで積み重ねてきた知識を、プレッシャーのかかる本番環境でも確実に得点できる「実戦レベル」へと引き上げることです。
- 使い慣れた教材の“やり込み”が最優先
- この時期に最も重視すべき原則は、「新しい教材には手を出さない」こと。焦りから別の教材に手を伸ばすと、表現や論点の違いに混乱し、自信を失う原因になります。
- 大切なのは、新しい教材を7割理解することではなく、「今まで使ってきた教材を100%使いこなせる」状態に仕上げることです。
- 問題演習を中心とした反復学習
- テキストの読み返しに偏らず、問題演習を起点とした学習に切り替えましょう。特に、肢別式の過去問集(例:「合格革命 肢別過去問」)を徹底的に回すことが効果的です。
- 加えて、「間違いノート」や「苦手論点リスト」を活用して、ミスの原因を分析し、条文や判例をもとに説明できるレベルまで理解を深めていく“アクティブリコール”を重ねることが、記憶の定着に直結します。
- 情報の一元化で“最強の1冊”を作る
- 気づきや弱点の補足情報は、使い慣れた基本書にどんどん書き込みましょう。
- ページ番号・模試解説・補足条文などを集約することで、知識が有機的につながった「本番直前に頼れる1冊」が完成します。
- 科目ごとの優先順位と時間配分の最終調整
- 時間の使い方にも明確な戦略を。
- 民法・行政法といった高配点科目に重点を置きつつ、商法・会社法は頻出テーマ(例:会社設立、商法総則)に的を絞った対策に留めるなど、コスパ重視の学習が重要です。
- 模試は“診断ツール”として徹底活用
- 模擬試験の点数に一喜一憂する必要はありません。
- 大切なのは、ミスした問題の分析から「自分の弱点」を特定し、基本テキストや過去問に立ち返って補強するというサイクルを回すことです。
- 特に、全体の正答率が高い問題を落とした場合は、致命的な抜け漏れの可能性があるため、必ず潰しておきましょう。
この時期にやってはいけないこと
- 新しい教材に手を出す
- 直前期に新たな教材に手をつけるのは、学習効率を下げる最大のリスクです。
- これは「何か大事なことを見逃しているのでは?」という不安が原因ですが、知識体系のズレを生み出し、むしろ不安を助長させる結果になります。
- 唯一の例外として、信頼している予備校が提供する「最終チェック講座」など、要点整理に特化した講座であれば、これまでの学習の補完として有効です。
- 理解を伴わない“丸暗記”に頼る
- 焦りから、解説や選択肢をそのまま暗記するような学習に走りがちですが、これは非常に危険です。
- 出題形式が少しでも変われば対応できず、「知っていたはずなのに解けなかった」という事態に直結します。
- 条文や判例の背景、論点の根拠を理解することが、最後までブレない得点力に変わります。
- 他人と比較して自信を失う
- SNSや掲示板で他人の模試の点数や学習時間を見て焦る——これは直前期に最も避けたい精神的消耗です。大切なのは「昨日の自分と比べてどうか」です。
- 本番では、完璧な受験生よりも「不安と共に歩きながら最後までやり切った人」が合格を手にしています。
試験1週間前:知識を“実戦仕様”に仕上げ、心身を万全に整える
学習の最終調整で「取りこぼしゼロ」を目指す
この1週間で新しいことを学ぶ必要はありません。
むしろ、知識の精度と取り出しスピードを高めることが、合格への直結ルートとなります。
- Aランク論点の総仕上げ
- 合格者が共通して取り組んでいるのが、「Aランク論点の総点検」。
- 基本テキストや一元化ノートを使い、「代理権の濫用」など重要項目を見出しだけで想起し、自分の言葉で要件・効果・判例を説明してみましょう。
- この“アクティブリコール”が、知識を「使える形」に変えます。
- 条文素読は「確認と慣れ」が目的
- この段階での条文読解は、あくまで文言への感覚を再確認する作業です。
- 民法・行政法・憲法を中心に、「条文の構造」や「どこに何が書かれているか」を感覚で掴み直しましょう。
- 目次を見て体系を意識しながら、音読や書き込み済みの六法の活用が効果的です。
- 一般知識対策:足切りを“回避する”ためのミニマル戦略
- 足切り回避を最優先に、次の3段階で取り組みます:
- 第一優先:文章理解
3問すべてを取りに行くつもりで、毎日1~2問解いて感覚を維持。 - 第二優先:情報通信・個人情報保護
法律や用語ベースで出題されるため対策しやすく、得点源にしやすい分野。 - 第三優先:政治・経済・社会
費用対効果が低いため、1~2問の“ラッキーパンチ”狙い。軽く時事確認をする程度でOK。
- 第一優先:文章理解
- 足切り回避を最優先に、次の3段階で取り組みます:
生活・メンタルの仕上げも“戦略的”に整える
学力が十分でも、本番で実力を発揮できなければ意味がありません。
心身の状態を試験当日にピークへ持っていく準備を、1週間前から始めましょう。
- まる1日、本番を再現するリハーサル
- 試験当日のスケジュール通りに起床し、午後1時から3時間、実際の模試や過去問を解いてみましょう。
- 当日の朝食・昼食のタイミング、移動手段、会場入り時間なども含めて再現することで、試験当日のイメージが明確になります。
- 緊張コントロールのための3つのセルフケア
- 漸進的筋弛緩法:体の各部位を順番に「力を入れる→抜く」を繰り返して緊張をほぐす方法。
- ボックス呼吸:「4秒吸う→4秒止める→4秒吐く→4秒止める」を繰り返し、自律神経を安定。
- 軽い有酸素運動:散歩などでエンドルフィンを放出し、不安やストレスを軽減。
- 集中力と記憶力を支える食事のコツ
- 主食は玄米などの複合炭水化物で、持続的な集中力を確保
- DHA豊富な青魚(サバ・鮭)で記憶力を強化
- 発酵食品(ヨーグルト等)で腸内環境を整え、脳機能を間接的にサポート
- 水分はこまめに補給し、軽い脱水による集中力低下を防ぐ
この時期に避けたいNG行動
- 難問に固執して時間を失う
- このタイミングで歯が立たない問題は、多くの受験生にとっても「捨て問」です。
- 合格に必要なのは、「基本問題で確実に点を取る力」です。割り切りが合否を分けます。
- スマホやSNSで“脳の処理能力”を削る
- 試験直前の貴重な時間に、SNSで他人と比較して不安を増やすのはもったいない。
- 通知や情報の多さが集中力を奪うため、スマホは物理的に手元から離しておくのが正解です。
- カフェイン・栄養ドリンクの過剰摂取
- 午後のカフェイン摂取は、睡眠の質を悪化させ、記憶定着を妨げます。
- 朝の一杯はOKですが、午後はハーブティーや白湯などに切り替えましょう。
- 栄養ドリンクに頼りすぎるのも逆効果です。
試験前日:実力を“出し切る準備”を整える1日
本番に向けて「整える」ためにやるべきこと
試験前日は、これまでの努力を信じて、心と身体を整える1日です。
新たな知識のインプットよりも、安心感・安定感を得る行動に集中しましょう。
- 持ち物・ルート・時間管理の最終チェック
- 「当日焦らないための準備」は、前日のうちにすべて済ませておくのが鉄則です。
- 持ち物チェックリストの作成:受験票・筆記用具・腕時計・昼食・防寒具など、忘れ物がないよう一覧化して確認。
- 交通手段・会場ルートの確認:電車の時刻・乗換・万一の代替手段まで把握。Googleマップで「当日同時刻」の所要時間もチェック。
- 試験に不要な物は入れない:スマホや六法など、試験中使えないものは別管理。持ち込み禁止物もあらかじめチェック。
- 「当日焦らないための準備」は、前日のうちにすべて済ませておくのが鉄則です。
- 軽めの復習で「知っている」という感覚を再確認
- この段階での学習は、“お守り”のような役割でOKです。
- 「間違いノート」や「一元化ノート」をパラパラと見直し、「ああ、これは大丈夫」という感覚を積み重ねましょう。
- 時間は15〜30分程度。目と頭を休ませることの方が大切です。
- この段階での学習は、“お守り”のような役割でOKです。
- リラックスして眠りにつくためのルーティンを作る
- 前日は、寝つきを良くするための“入眠の準備”も重要な戦略です。
- ぬるめのお風呂に浸かる(就寝1〜2時間前):深部体温を下げることで自然な眠気を誘発。
- ブルーライトを避ける:スマホやPCの使用は極力控え、紙の本や音楽で気持ちを落ち着けましょう。
- 眠れないときは無理に寝ようとしない:一度ベッドを離れて、薄暗い部屋でリラックスする時間を。
- 前日は、寝つきを良くするための“入眠の準備”も重要な戦略です。
試験前日に避けるべき行動
- 深夜までの追い込み学習は逆効果
- 前日に詰め込んだ知識は定着しづらく、むしろ睡眠の質を悪化させ、当日の集中力を奪います。
- 今さら1点を積み増すより、「持っている力を出せる状態」に整えるほうが、合格可能性は高まります。
- ゲン担ぎや“非日常”でリズムを崩さない
- 「験担ぎ」は、気持ちを整える程度ならOKです。
- しかし、いつもと違うレストランで外食したり、慣れない行動をしたりすると、かえって心身に負担をかける恐れがあります。
普段通りの生活リズムを維持し、静かに自分の状態を整える——
これが、試験前日にすべきもっとも賢い行動です。
まとめ|最後に問われるのは「知識」よりも「整える力」
ここまで積み上げてきたあなたの努力は、確実に本番での力になります。
試験直前期に大切なのは、「まだ何かを覚えなければ」という焦燥感に駆られるのではなく、すでに持っている知識とコンディションを“本番仕様”に最適化することです。
直前期は、学力を伸ばすフェーズではありません。
むしろ、これまで学んだことを確実に取り出せる状態に整えるための最終調整の期間です。
焦らず、無理をせず、これまでの自分を信じてください。
不安があっても構いません。不安とともに歩きながらも、淡々とやるべきことをこなしてきたあなたには、十分に合格の力があります。
試験当日、自分の席に静かに腰を下ろし、問題文を読み、迷いなくマークを塗る。
その姿を、どうかあなた自身が一番信じてあげてください。
あなたの努力が、最高のかたちで実を結ぶことを、心から願っています。

行政書士試験徹底解説
行政書士試験の完全攻略ガイド|ゼロから始める社会人のための難易度・勉強法・合格ロードマップ