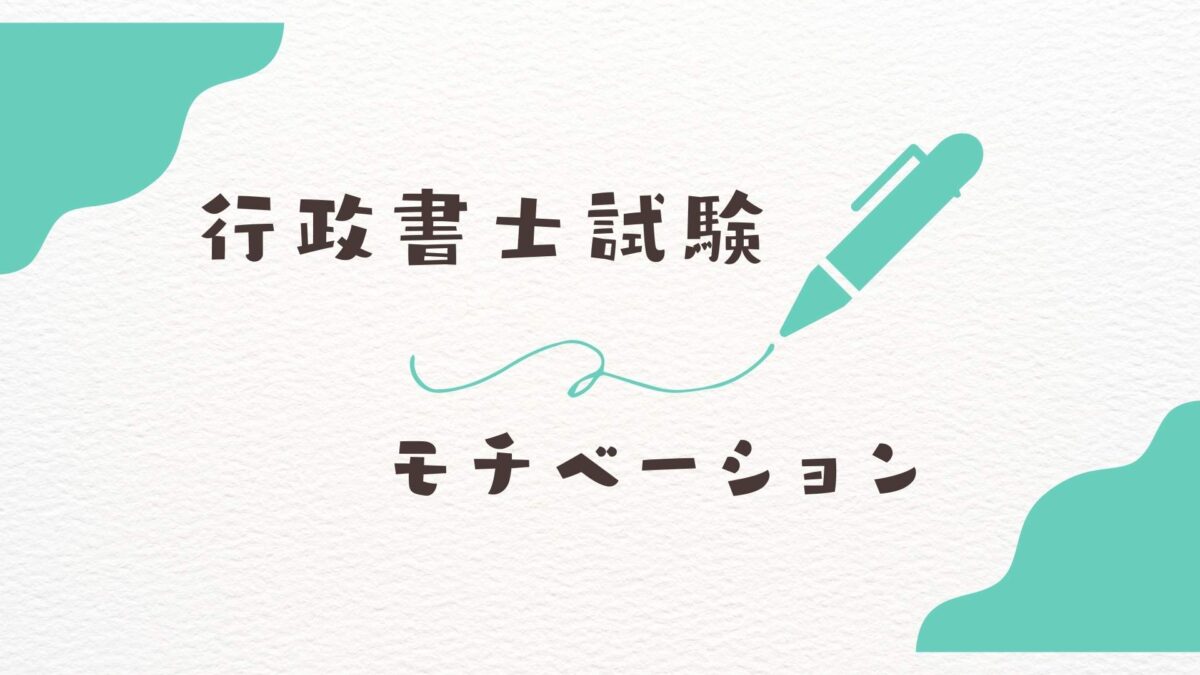「無理かも…」から「やれるかも!」へ──家事・育児と試験勉強の両立に挑むあなたへ
「行政書士として新しいキャリアを築きたい」——そう強く願ってはいても、目の前には尽きることのない家事や、予測のつかない子どもの世話が立ちはだかる。ようやく時間ができたと思った矢先に、また別のタスクが割り込んでくる。気づけば、「こんな生活の中で、本当に合格なんて目指せるのだろうか」と不安がよぎり、勉強に向かう気力すら削られてしまう……。
そんなふうに感じたことがあるのなら、あなたは決して一人ではありません。実際、多くの主婦・主夫受験生が、同じ壁に直面し、悩み、そしてそれを乗り越えてきました。
このページは、そうした「両立の壁」にぶつかりながらも合格を手にした先輩たちの工夫と、専門家の見地や実証データに基づいた“現実的かつ実践的”なノウハウを集めた、あなたのための「両立戦略ガイド」です。
本稿で扱うのは、単なる時間管理術ではありません。
・限られた時間をどう生み出すか
・心の持ち方をどう整えるか
・家族との関係をどう味方につけるか
といった、「生活そのものを設計し直す」視点からのアプローチを提示します。
読み終える頃には、「自分にもできるかもしれない」という確かな手応えと、新しいスタートを切るためのモチベーションを、きっと取り戻しているはずです。
行政書士という専門職の未来は、家庭との両立の先にこそ拓けています。この記事が、その一歩を踏み出すきっかけとなれば幸いです。
第1章 両立が“難しすぎる”のには理由がある──3つの見えない壁を言語化する
1.1 「自分の時間」が奪われる仕組み──予測不能な“時間泥棒”との闘い
行政書士試験の学習において、最も深刻な課題のひとつが「まとまった勉強時間の確保ができない」ことです。しかしこれは、単なる“忙しさ”の問題ではありません。
家事や育児は、突発的な対応が常に求められる業務であり、時間管理の前提となる「計画通りに進められること」が成り立ちません。
例えば、6歳未満の子どもがいる家庭では、母親が1日に約4.4時間を家事・育児に充てているのに対し、父親は平均で37分という統計(内閣府調査)もあります。これにより、特に女性の受験生が「学習に集中できる環境」を物理的に確保しにくい構造が浮き彫りになります。
さらに、子どもの急な発熱、機嫌の波、呼び出しなどにより、「今日はこの時間に勉強しよう」と立てた計画が次々に崩される現実が続くと、
「どうせ無理になるなら最初から計画しても意味がない」
という無力感に支配され、学習習慣の維持すら困難になります。
また、「常時接続」状態の精神的負荷、いわゆる“メンタルロード”も大きな障害です。献立の計画や育児イベントの管理、健康チェック、買い物の段取りなど、目に見えない「思考負荷」が常に脳を占拠しているため、ようやく時間ができても「もう何もしたくない」という状態になりがちです。
1.2 「ちゃんとやらなきゃ」が自分を追い込む──完璧主義のワナ
もうひとつの大きな壁は、「自分に課している期待値の高さ」です。
特に育児中の受験生は、「勉強している=家族を犠牲にしている」という罪悪感を抱きやすく、それを補おうとして“完璧な家事・育児”を目指してしまう傾向があります。
この完璧主義は、勉強にも、家庭生活にも悪循環をもたらします。
疲労が蓄積して勉強の効率は下がり、結果が出ないことでさらに自己否定感が強まり、「私はどっちも中途半端」と思い詰めてしまうことすらあります。
さらには、その罪悪感の裏に「本当は誰かにもっと助けてほしい」「自分ばかりが我慢している」という抑圧された感情が隠れている場合もあります。そうした感情を外に出せず、「全部自分の努力でなんとかしなければ」と自分にプレッシャーをかけ続けることで、心身が限界を迎えてしまうことも少なくありません。
1.3 「わかってくれる人がいない」──孤独がモチベーションを削る
勉強そのものよりも、最も多くの受験生の心を蝕むのが「孤独感」です。
特に、子育て中で家庭にいる時間が長くなる専業主婦(主夫)の場合、「同じように資格を目指している仲間がいない」「誰にも努力を見てもらえない」といった状況に直面しやすくなります。
SNSなどで他人の学習進捗を見ると、「自分だけが取り残されているのでは」という焦りも生じ、メンタルが不安定になる要因にもなり得ます。
この孤立感は、単に“寂しい”という感情にとどまらず、「誰にも相談できない」「共感されない」という現実的な問題に発展します。
結果として、「自分で抱え込むしかない」「こんなに苦しいのは自分だけかも」と思い詰めてしまい、モチベーションの維持が困難になります。
この3つの「見えない壁」は、あなたの努力不足ではなく、構造的な問題に起因するものです。
まずは「なぜ両立がこれほど難しいのか」を冷静に理解し、「自分を責める必要はない」と気づくことが、長く続けるうえで最も重要な出発点になります。
第2章 合格への近道は「戦わないこと」から始まる──両立を叶える実践テクニック
2.1 「やらないこと」を決めることが、最も効果的な時間術
両立において、「どう時間を作るか」ではなく、「何を手放すか」が鍵になります。
限られたリソースで戦うには、“全部やる”という発想そのものを捨てる必要があります。
やめることリストの作成
まずは、日々の家事・用事を書き出して、「やめても困らないこと」「頻度を減らせること」「外部化できること」に分類してみましょう。
- 床掃除は週1回に減らす
- 洗濯物のアイロンがけは最低限に
- 食事はミールキットで時短する など
これは“手抜き”ではなく、“合格を最優先に据えた合理的な選択”です。
時短家電で物理的な時間を創出する
今や家事は「手でやるもの」ではなく「仕組みに任せるもの」です。特に以下の3つは、受験生にとっての“時間創出マシン”とも言えます。
- 食洗機:1日20〜30分、月10時間以上の勉強時間を捻出
- ロボット掃除機:掃除の手間だけでなく、精神的負担も軽減
- ドラム式洗濯乾燥機:天気に左右されず、干す・取り込む手間ゼロ
料理を「毎回ゼロから作らない」発想に
- ミールキット(冷凍・下処理済)
- 週末の作り置き
- 電気圧力鍋やホットクックなどの自動調理家電
を活用すれば、日々の「献立を考える・買い物に行く・調理する」という一連の負担を丸ごと軽減できます。
2.2 「スキマ時間」こそ最大の武器──細切れ時間を積み上げる勉強法
1時間まとまった学習時間が取れなくても、2分×30回で1時間に到達できます。
この“モジュール型学習”こそが、主婦(主夫)受験生の現実に合ったスタイルです。
耳を使えば“ながら学習”ができる
通勤・調理・洗濯・寝かしつけなど、手がふさがっていても耳は空いています。
講義音声や自分の録音を流せば、「死に時間」がすべて学習時間に変わります。
一問一答アプリの活用
スキマ時間でも成果を出すには、「反復・即答型」の形式が最適です。
スマホアプリや単語カードを使い、過去問や重要語句を“短時間で何度も”繰り返すことが記憶定着に効果的です。
デジタル講座の強みを最大限に使う
スマホ1台で学べる通信講座(例:スタディング)は、
・講義が数分単位に分かれている
・進捗管理がしやすい
といった利点があり、両立受験生との相性は抜群です。
「朝活・夜活」は前提条件で変える
- 朝は「前夜の準備」で成功率が決まる
→ テキストを開いておく、筆記用具を置いておく - 夜は「記憶の定着タイム」だが、睡眠は最優先
→ 復習や暗記系を行い、就寝は必ず6時間以上確保
2.3 家族を“応援団”に変える──協力を引き出す伝え方の技術
合格は、あなた一人の目標ではなく、「家族全体の未来を豊かにするプロジェクト」です。
協力を得るためには、“お願い”ではなく“戦略的コミュニケーション”が必要です。
「いつ・何を・どうしてほしいか」を明確に
→ ×「もっと手伝って」
→ 〇「平日夜8時〜9時だけ、子どもの寝かしつけをお願いできる?」
具体的で行動可能な依頼は、相手の理解と行動を引き出します。
「あなた」ではなく「私」を主語に伝える
→ ×「あなたが洗い物してくれないから…」
→ 〇「勉強後に洗い物が残ってると、すごく疲れてしまうの」
Iメッセージ(自分の感情や困りごとを伝える)を使うことで、非難ではなく共感を生みやすくなります。
協力=家族の利益であることを伝える
「今試験に集中できれば、来年からもっと柔軟に働けるようになる」
「収入が安定すれば、子どもにも良い環境を用意できる」
といった“共通の未来像”を共有することで、協力の納得感が高まります。
感謝は必ず“言葉で”伝える
どれだけ小さな協力でも、「ありがとう」は最強の報酬です。
感謝を伝えることで、相手の「また手伝おう」という気持ちが育ちます。
家事を“見える化”するツールも活用
アプリやホワイトボードで家事分担を可視化すれば、「気づかなかった」「忘れてた」も防げます。
特に「名もなき家事(在庫管理、行事確認など)」の共有が、理解と協力を生み出す鍵です。
“もっと頑張る”のではなく、“戦略的に頑張らないこと”が合格への近道。
次章では、心が折れそうになったときの「立て直し方」について、より具体的に見ていきます。
第3章 心が折れそうな時に読む章──学習継続を支える「メンタル回復戦略」
3.1 「休むことはサボりじゃない」──休息も学習計画の一部に組み込む
「頑張り続けないと合格できない」と思い詰めていませんか?
でも、脳科学的に見ても、記憶の定着や集中力の維持には“意図的な休息”が不可欠です。
休む=学習効率を最大化する「戦略的行動」
疲労が限界まで蓄積した状態での勉強は、効率が著しく低下します。
むしろ、休息や睡眠を挟むことで脳が情報を整理し、学習内容が長期記憶として定着するという研究結果もあります。
自分の限界に気づくための「セルフチェック」
以下に複数当てはまる場合は、バーンアウト(燃え尽き症候群)の初期サインかもしれません:
- 朝から疲労感が抜けない
- 好きなことにも興味が持てなくなった
- 他人と話すのが億劫
- 些細なことでイライラ、または涙が出る
- 集中力が落ち、ケアレスミスが増えた
- 外出が億劫で引きこもりがちになる
該当する方は、「休むこと」に対して罪悪感を抱かず、まずは立ち止まることを自分に許してあげましょう。
「休み方」にもコツがある
- 休憩を予定に組み込む:カレンダーに「休息日」と明記し、学習と同じように優先順位を与える。
- 15〜20分の戦略的仮眠(パワーナップ):午後の集中力をリセットできる強力な回復法。
- 思考を止める活動に没頭:散歩、音楽、温かい飲み物など、SNS以外の“脱・勉強モード”を意識して。
3.2 「やる気ゼロ」から立ち上がる──再点火のための3つのスイッチ
学習において、モチベーションが下がるのは自然なことです。
そんなときに“無理やり気合を入れる”のではなく、小さな再起動ボタンを押すような3つの方法があります。
スイッチ①:目標を極限まで細かく分解する
「合格する」という大目標が重荷に感じたら、「今日テキストを1ページだけ読む」「5問だけ過去問を解く」といった“小さな達成”にフォーカスを。
成功体験の積み重ねが、意欲の再構築につながります。
スイッチ②:「なぜこの資格を目指したか」を思い出す
- 在宅で行政書士事務所を開きたい
- 家計を支えたい
- 専門性で自信を持ちたい
──あのとき描いた理想像を思い出すことは、原点に立ち返る最もシンプルかつ強力な方法です。
スイッチ③:「仲間がいる」と知る
Twitterの「#勉強垢」やLINEのオープンチャットなど、同じ境遇で頑張っている仲間の存在は大きな励みになります。
孤独感を手放せた瞬間、あなたの学習は“個人戦”から“チーム戦”へと切り替わります。
3.3 一人で抱え込まない──“つながり”が学習を支える
精神的な落ち込みは、孤独と密接に結びついています。
「誰にも相談できない」「自分だけが頑張っている」という感覚は、メンタルを消耗させ、学習継続の大きな障害になります。
共感と励ましのある場所にアクセスする
- SNSや資格専用フォーラムで「今日ここまでやった」とつぶやくだけでも、気持ちは変わります。
- オンライン勉強会、オープンチャット、Discordサーバーなど、自分に合った“安心できる空間”を探してみましょう。
家族やパートナーにも正直に話す
「実は、ちょっとしんどい」
この一言がきっかけで、思いがけない協力や配慮を得られることも少なくありません。
限界に見えるときこそ、立ち止まる勇気を。
合格とは「最後まで学習を続けた人」が手にするもの。
そのための“心の技術”もまた、合格戦略の一部です。
第4章 「お金をかける=ズル」じゃない──外部サービスを“合格資源”に変える発想
4.1 家事・育児支援サービスを「戦略的に使う」という選択肢
「全部自分でやらないと」という思い込みが、合格を遠ざけているかもしれません。
限られた時間の中で結果を出すには、“頼れるものには頼る”という発想転換が不可欠です。外部サービスの活用は、贅沢でも逃げでもなく、未来への投資です。
家事代行サービス:苦手・時間食いタスクをプロに任せる
- 相場:1時間あたり3,000〜4,500円前後(2時間~)+交通費
- メリット:掃除や水回りなど、心身の負担が大きい家事を丸ごとアウトソーシング
- おすすめの使い方:週末のまとめ掃除タイムを学習時間に転換
一時保育:数時間でも集中できる“静かな時間”を確保
- 相場:認可園で1日2,000〜5,000円、認可外は6,000〜15,000円程度
- メリット:模試や苦手分野の集中演習など、ここ一番の学習に最適
- 注意点:事前登録や予約制限に注意。地域差が大きいため早めの確認を
ファミリー・サポート・センター:地域密着で柔軟な対応が魅力
- 相場:1時間800〜1,000円程度
- 特徴:保育園の送迎や短時間の預かりなどに対応
- 活用例:「保育園のお迎えに間に合わない」「通院中に子どもを見てほしい」などスポットニーズに強い
ネットスーパー:買い物時間を“ゼロ”に
- 相場:配送料100円〜550円前後
- メリット:買い出しの時間と労力を丸ごと節約でき、子連れの負担も軽減
- 特典情報:子育て世帯向けに送料半額などの優待があるサービスも(例:イトーヨーカドー)
4.2 「時間を買う」という発想が、合格への差を生む
「お金を使うことに抵抗がある」
これは非常に自然な感覚ですが、合格という“結果”を最短で得るためには、費用対効果の視点が重要です。
外注コスト=“合格に近づく投資”と考える
たとえば、家事代行に1回6,000円を支払って2時間の学習時間を確保できるとします。
この2時間が「苦手科目の穴埋め」や「記述式の答案練習」に使えたなら、それは単なる支出ではなく、“合格可能性を高める自己投資”です。
「削るのは支出でなく、“ストレス”」
子育て・家事・勉強を全部自力でやろうとすると、どこかで無理が生じます。
外部リソースを活用すれば、時間だけでなく精神的な余裕も確保できます。
それにより、学習により深く集中でき、質の高いアウトプットが可能になります。
「全部やらない」から、試験に“勝てる”
行政書士試験は、幅広い法令知識を問われる長期戦です。
戦略的に時間と体力を配分し、やるべきことに集中する姿勢こそ、合格に不可欠なスキルです。
言い換えれば、「自分で全部抱え込まない力」も、合格者に共通する大事な資質なのです。
「お金をかけること=楽をしてズルをしている」と感じる必要はありません。
むしろ、“限られた時間とエネルギーを、合格に最も直結する場所に集中投下する”という思考が、合格者の共通点です。
第5章 合格者の“リアルな声”に学ぶ──両立を乗り越えた人たちの成功の鍵
5.1 育児と仕事を両立しながら一発合格──本気でやると決めた“その瞬間”から動き出した
4人の子どもを育てながら、仕事と並行して行政書士試験に挑み、見事一発合格を果たした受験生がいます。
彼女の言葉は、あらゆる迷いや言い訳を打ち消す、強い力を持っていました。
「自分が『やろう』と決めたときが、自分にとっての“その時”なんです。」
年齢でも、環境でも、時間の余裕でもない。
「やる」と腹をくくった瞬間に、人は変われる。
彼女のエピソードは、まさにそのことを体現しています。
忙しさを理由に夢をあきらめそうになっている方にとって、
「自分の“今”こそがベストタイミングかもしれない」と思わせてくれる実話です。
5.2 協力し合える家庭があったからこそ──“チーム”で合格を目指したケース
ある合格者のご家庭では、試験直前の追い込み期に夫がほとんどの家事・育児を引き受けてくれたそうです。
これは単なる「手伝い」ではなく、「合格というゴールを共有したチーム」としての行動でした。
「試験合格は、自分一人の努力ではなく、家族みんなで掴んだ結果です。」
家庭の中で“応援団”を作るには、STEP3でも紹介したように
- 具体的な協力のお願い
- 感謝を言葉で伝える
- 成果を共有する
といった地道なコミュニケーションが欠かせません。
合格の裏には、支えてくれる存在への信頼と、チームとしての連携があります。
それは、資格取得後の“独立開業”という次のステージにおいても、大きな基盤になります。
5.3 自分を信じて踏み出したからこそ──資格が人生を変える“きっかけ”になる
「自分にはキャリアらしいキャリアがない」
「子育てでブランクがある」
「資格を取っても、どう活かせるか分からない」
そんな不安を抱えながら、資格取得を決意した主婦(主夫)も少なくありません。
ある合格者は、こう語っています。
「“何もない”から始めたからこそ、資格が私の“新しい土台”になったんです。」
行政書士という資格は、単なる知識の証明ではなく、「自分の未来を自分で切り拓く力」そのものです。
それは、自宅開業や在宅ワークという柔軟な働き方にも直結し、
- 月に1〜2件の受任でも安定収入につながる
- 家庭の事情に合わせて仕事量を調整できる
という現実的なメリットを生み出します。
あなたが今、少しでも「変わりたい」と思っているなら、
その気持ちこそが“第一歩”です。
資格取得は、あなたの「できる」を証明する最高の手段になります。
合格者たちの体験談には、共通して一つの力が宿っています。
それは、「現実と向き合いながらも、未来を信じた力」です。
迷いながらでも、止まりそうになっても、一歩ずつ前に進んだ人が、最終的に“その景色”を見ています。
まとめ 時間・メンタル・協力体制──両立を可能にする“3つの戦略軸”
行政書士試験と家事・育児を両立するという挑戦は、誰にとっても簡単なことではありません。
それでも、「両立は可能か?」という問いに、明確に「YES」と答えられる人たちが実在します。
本記事でお伝えしたことは、単なる精神論ではなく、具体的かつ実践的な戦略です。
改めて、合格のために必要な3つの柱を整理しましょう。
1. 時間の主導権を取り戻す
「やらないこと」を明確にし、時短家電や外部サービスを積極的に活用することで、
物理的に“学習時間”を捻出する。これは最優先の戦術です。
2. 心のセルフマネジメントを身につける
罪悪感や焦り、完璧主義という見えないストレスに対し、
「休むことも戦略」「小さな目標で再起動」「仲間とつながる」などのメンタル技術で対応する。
3. 家族を“共闘パートナー”にする
「手伝ってもらう」ではなく、「一緒に目標を実現するチーム」として、
協力体制を構築し、家庭内の負担と支援を見える化する。
行政書士という専門職は、時間や働き方を自分で設計できる自由度の高い資格です。
だからこそ、試験に向かうこの過程そのものが、
「自分で未来を切り拓く力」を育てる第一歩になります。
今日からできる小さな行動を、一つだけでも実行に移してみてください。
あなたの“合格に向かう歩み”を、私たちは心から応援しています。

行政書士試験徹底解説
行政書士試験の完全攻略ガイド|ゼロから始める社会人のための難易度・勉強法・合格ロードマップ