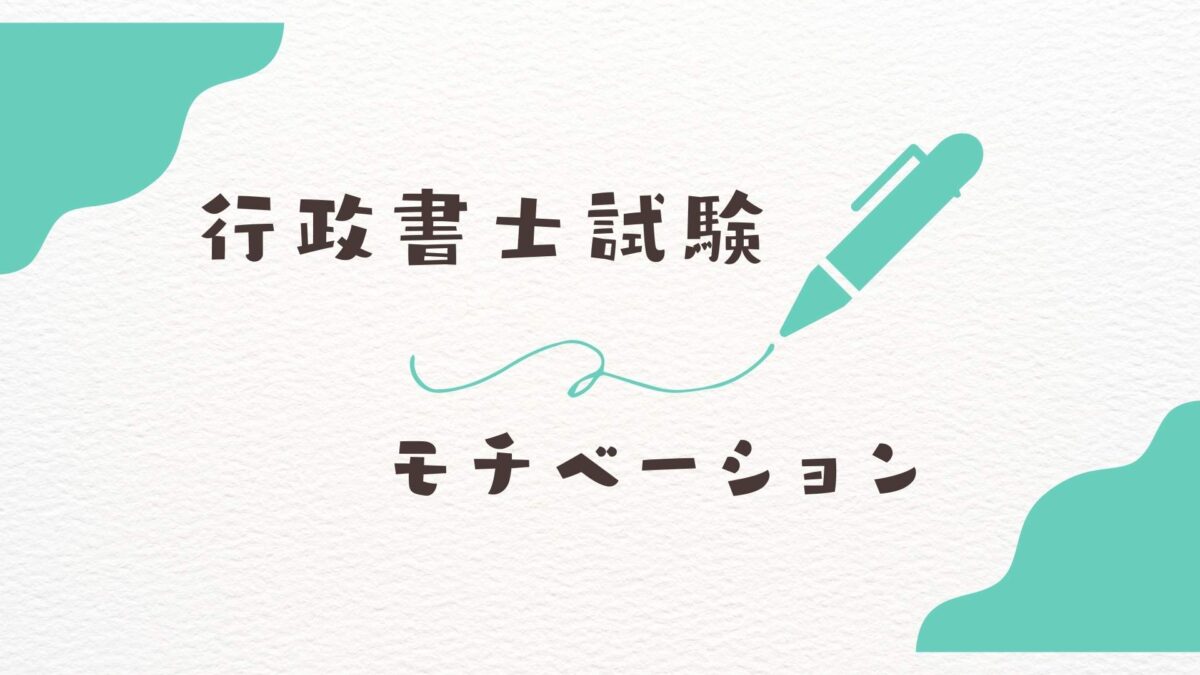1日は24時間──合否を分けるのは「時間の使い方」
「仕事が忙しくて勉強する時間がない」「子育てや家事に追われて机に向かえない」──そんな悩みを抱える社会人や主婦(夫)の方へ、まずお伝えしたいことがあります。
行政書士試験に合格する人の多くも、実はあなたと同じように限られた時間の中で努力を続けています。特別な時間があるわけでも、生活が楽なわけでもありません。
筆者である私は、フルタイム勤務と子育てを両立しながら、2年間の独学で行政書士試験に合格しました。しかし、合格の喜び以上に感じたのは、「もっと効率的な方法を知っていれば、あの時間を取り戻せたかもしれない」という後悔でした。
この記事では、そんな私の実体験をもとに、「限られた時間を、どう使えば合格に近づけるか?」を徹底的に掘り下げていきます。
机に向かえない日でも、スキマ時間で差をつける方法。
疲れていても、効率よく集中できる時間術。
そして、2年の遠回りを経て辿り着いた“最短ルート”とは何か。
行政書士試験合格に向けて、本当に必要な「時間の使い方」を一緒に見直していきましょう。
第1章 行政書士試験に必要な学習時間──“1000時間”という現実
行政書士試験に合格するためには、法律初学者であっても避けて通れない「一定量の学習時間」が必要です。
一般的に、独学で合格を目指す場合の目安とされる学習時間は、800時間から1000時間。これは複数の予備校や合格者の体験談から導かれた、現実的な数値です。
では、この1000時間という学習量を、1年間でどのように積み重ねればよいのでしょうか。
▶ 試算してみると…
- 1年=365日
- 1000時間 ÷ 365日 ≒ 1日あたり約2.7時間
つまり、平日は2〜3時間、休日は5〜6時間程度の学習時間を確保する必要があります。
この数字だけを見ると、「そんな時間、毎日取れない…」と感じる方も多いかもしれません。実際、社会人や子育て中の方にとっては、毎日安定して2時間以上の勉強時間を確保するのは至難の業です。
しかし、合格者の多くはこの「時間の壁」を創意工夫で乗り越えています。
彼らは、スキマ時間を積み重ね、休日の時間を戦略的に使い、生活の中に“学習時間”を織り込む工夫をしています。
この章では、まず「どれくらいの学習時間が必要なのか?」という現実をしっかりと把握し、次章以降で「それをどうやって捻出するか?」の具体的戦略に入っていきます。
時間は誰にとっても平等です。そして、その使い方次第で合格はぐっと近づきます。
第2章 【実例公開】社会人合格者の1日スケジュール
日々の忙しさに追われながらも合格をつかんだ社会人・主婦(夫)の受験生たちは、どのように時間をやりくりしていたのでしょうか?
ここでは、複数の合格者の体験をもとに、再現性の高いスケジュールモデルを3つに分類し、それぞれの特徴と向き不向きを解説します。さらに、実際に使える「理想的1日スケジュール」の合成モデルもご紹介します。
あなた自身の生活に合った学習スタイルを見つける参考にしてください。
2.1 平日:朝活型・夜型・ハイブリッド型の3スタイル
平日の学習時間をどう捻出するかは、多忙な受験生にとって最大の課題です。合格者の学習パターンは大きく3つに分類されます。
● 朝活型──脳が冴える“ゴールデンタイム”を活用
早朝の静かな時間に集中して学習するスタイルです。出勤前の1〜2時間を、講義視聴や条文の読み込みといったインプット学習にあてる受験生が多く見られます。
- メリット:疲労が少なく、集中力が高い時間帯を有効活用できる
- デメリット:早起きの習慣づけにややハードルがある
実際に、夜型から朝型へ切り替えたことで成績が伸びたという合格者も多数います。
● 夜型──家事・育児が落ち着いた後に“全集中”
夕食後〜就寝前の時間帯に学習するスタイルです。21時〜23時半の2〜3時間を確保するケースが多く、家庭が一段落してから取り組めるのが特長です。
- メリット:家事・育児の後でも時間を取りやすい
- デメリット:1日の疲れが蓄積しており、集中力が維持しづらい
筆者自身もこの夜型でスタートしましたが、疲労による非効率さに悩まされた経験があります。
● ハイブリッド型──スキマ時間を総動員する“現実的戦法”
「朝も夜も少しずつ」「通勤中や昼休みも学習に充てる」──そんな柔軟な学習スタイルが、ハイブリッド型です。子育て中・フルタイム勤務の方にとって、最も現実的で実践的な方法です。
- 例:朝活1h+通勤中1h+昼休み30分+帰宅後1.5h=合計4時間超
- 留意点:1日の中で思考モードを何度も切り替える「認知負荷」がかかる
この切り替えのストレスをいかに最小限に抑えるかが、成功のカギになります。
2.2 休日:学習×家族×休息を両立する戦略
休日は、まとまった学習時間を確保できる貴重な“戦略リソース”です。しかし同時に、家族との時間や休養も大切にしたい日でもあります。合格者たちはこのバランスをどう取っていたのでしょうか?
■ 戦略1:集中ブロックの確保
多くの合格者は、土日の午前・午後いずれかに5時間程度のまとまった学習時間を確保し、模試や記述問題の演習、条文の精読など、高負荷な課題に取り組んでいます。
■ 戦略2:意識的な休息と家族時間の設定
ある合格者は「週末は家族の時間」と明確にルール化し、それを前提に平日の学習スケジュールを逆算。これによりモチベーションも家庭の調和も保たれたといいます。
■ 分析:休日は「戦略的学習」、平日は「戦術的学習」
平日は細切れの時間を積み上げる“戦術”の連続ですが、休日は腰を据えて学ぶ“戦略”の時間。だからこそ、「何をどれだけやるか」を明確にしておかないと、かえって時間を持て余し、判断麻痺を起こしてしまうことも。
2.3 合成モデルで見る「勝てる1日」
以下は、複数の合格者の生活スタイルを組み合わせて作成した「モデルケース」です。あなた自身の生活と照らし合わせながら、具体的な学習スケジュールの参考にしてください。
| 時間帯 | 平日(朝活・ハイブリッド型) | 休日(集中・バランス型) |
|---|---|---|
| 06:00-07:00 | 起床、身支度、【学習①】テキスト精読(1h) | 起床、朝食 |
| 07:00-08:00 | 朝食、出勤準備 | 【学習①】重要論点の集中学習(2h) |
| 08:00-09:00 | 【学習②】通勤中:講義音声(0.5h) | — |
| 09:00-12:00 | 勤務 | 【学習②】過去問演習(3h) |
| 12:00-13:00 | 【学習③】昼休み:一問一答アプリ(0.5h) | 昼食・休憩 |
| 13:00-18:00 | 勤務 | 家族時間・外出 |
| 18:00-19:00 | 【学習④】帰宅中:講義動画(0.5h) | — |
| 19:00-21:00 | 家事・育児・夕食 | 家族時間・夕食 |
| 21:00-22:00 | 【学習⑤】復習・暗記(1h) | 【学習③】平日の復習・記憶定着(1h) |
| 22:00-23:00 | 入浴・自由時間 | 入浴・自由時間 |
| 23:00- | 就寝 | 就寝 |
- 平日合計:約3.5時間
- 休日合計:約6時間
このモデルは、断片的な時間の積み重ねで学習時間を確保していく「社会人受験生の現実」に寄り添った構成です。自分の生活リズムと照らし合わせ、無理のない形で組み込めるパーツから取り入れていくのがおすすめです。
第3章 スキマ時間を制する者が、試験を制す!
忙しい社会人や主婦(夫)にとって、1日まるごと勉強に充てられる時間はそう多くありません。だからこそ、合否を左右するのは「スキマ時間」をどう活かすかにかかっています。
たった5分でも、15分でも、積み重ねれば大きな差になります。実際、多くの合格者が「細切れ時間の使い方が勝敗を分けた」と語っています。
この章では、日常生活の中に潜むスキマ時間の“見える化”と、時間の長さに応じた最適な学習法を紹介します。
3.1 見逃しがちな「スキマ時間」完全リスト
「時間がない」と感じるときでも、実は使える時間は意外とあります。合格者たちが活用していたスキマ時間は、以下のような場面に散らばっていました。
【移動中】
- 通勤電車・バスの中
- 駅での待ち時間
- 徒歩移動中(音声学習)
【職場】
- 昼休み
- アポイントの合間
- 始業前・終業後の10分間
【家庭】
- 子どもの送迎の待ち時間
- 昼寝中や就寝後のひととき
- 料理や食器洗い中(音声講義)
- 入浴中やトイレ中
- 就寝前のベッドの中
これらはすべて「まとまった時間が取れない」人のための、貴重な学習リソースです。
ポイントは、「何をしようかな」と考える前に、即座に学習を始められる仕組みを用意しておくこと。そのための戦略が次項の「時間別タスク」です。
3.2 時間別タスク戦略──5分・15分・30分でできること
スキマ時間の効果は、「その時間の長さに合った学習内容を選べるか」で大きく変わります。合格者の多くは、スキマ時間ごとに“やること”を決めておく「マイクロ・タスク戦略」を実践していました。
■ 5分でできること(超短時間・低負荷)
- 一問一答アプリでアウトプット練習
- 昨日覚えた条文のキーワードを暗唱
- デジタル単語帳のチェック
▶ ポイント:新しい知識のインプットよりも、既に覚えた知識の想起・確認に使うと効果的。
■ 15分でできること(中負荷)
- 講義動画の視聴(1.5倍速なら1講義完結)
- 過去問を1〜2問解いて解説確認
- テキスト1セクションの読み込み
▶ ポイント:インプットとアウトプットをワンセットにできる最小単位。
■ 30分でできること(高負荷・重要)
- テキスト1チャプターの通読
- 小テストやミニ模試の実施
- 苦手分野の集中復習
▶ ポイント:体系的な理解や記述対策など、やや重めの学習に最適。昼休みや夜のまとまった時間に。
3.3 「スキマ時間攻略マトリクス」で学習効率を最大化
以下のマトリクスは、スキマ時間を最大限に活用するための「時間別×学習法」の具体例と、独学と通信講座の効率差をまとめたものです。
| 時間 | 推奨タスク | 独学の課題(ロス要因) | 通信講座の強み(時間創出) | 推奨ツール例 |
|---|---|---|---|---|
| 5分 | 一問一答、条文暗唱 | 「どこをやるか」悩む時間が発生 | 自動で弱点問題が出題され即開始可能 | 秒トレ、過去問アプリ、講座付属アプリ |
| 15分 | 講義動画(倍速)、過去問演習 | テキスト取り出しや動画選定に時間がかかる | スマホ一つで講義→演習が完結 | スタディング、ManaBun、アガルート |
| 30分 | チャプター学習、小テスト | 理解度が見えにくく手応えがない | 自動で復習提案、進捗管理も可能 | 各講座のeラーニング、LEC問題集アプリ |
■ このマトリクスが伝える本質
通信講座は単なる「教材提供サービス」ではありません。
スキマ時間に伴う「迷い」「準備」「判断」の時間的摩擦を極限まで排除し、学習に集中できる環境を用意してくれる“時間効率化ツール”です。
独学者が「どれをやろうか…」と5秒悩んでいる間に、講座受講者はすでに2問を解き終えている。
──その差が、最終的な合否につながっていくのです。
第4章 独学2年の私が悔やんだ“非効率な時間の罠”
ここでは、筆者である私が実際に体験した「独学2年間で陥った時間の落とし穴」を赤裸々に紹介します。
合格はできました。けれど、今振り返っても「もっと早く終わらせる方法があった」と強く思います。
この章は、これから独学を選ぶ方が同じ後悔をしないように、“気づき”と“ヒント”をお届けするための章です。
4.1 計画作成に膨大な時間がかかる
独学での最大の難関の一つが、「学習計画を自分で作る」ことでした。
何を・どの順番で・どれだけの時間をかけて学ぶべきか──
初学者の私には、最初のスケジューリングだけで数日かかりました。
しかも、いざ始めてみると「このやり方で本当にいいのか?」という迷いが常に付きまとい、数週間ごとに計画を立て直す羽目に。結果、計画ばかりを練って、学習が進まないという本末転倒な状況に…。
行政書士試験は科目数が多く、出題頻度にも偏りがあります。独学では、そうした戦略的配分の判断もすべて自己責任で行わなければならないのです。
4.2 教材選び・法改正情報の自力収集に疲弊
書店に行けば、行政書士関連のテキストや問題集がずらりと並んでいます。でも、「どれが自分に合うか」は、買ってみなければ分かりません。
私も複数の教材を試しては挫折を繰り返し、「これは違った…」というだけで何時間も浪費してしまいました。
さらに厄介なのが「法改正」対応です。
行政書士試験は法令科目が中心である以上、毎年のように実施される改正に敏感である必要があります。
独学では、官報や省庁のWebサイトから情報を拾い、自分の教材が対応しているかどうかを確認する手間が発生します。この作業だけで何時間も消えましたし、精神的にもかなり疲れました。
4.3 わからない箇所で思考停止──質問できない苦しみ
法律の世界には、ひとつ理解できない用語や概念があるだけで、先に進めなくなる場面が何度もあります。
私も、たった1つの民法の概念が理解できず、1週間以上同じページに留まり続けたことがありました。検索しても断片的な情報ばかりで、全体像がつかめない。そんな状態が続くと、勉強そのものが苦痛になります。
通信講座であれば、質問制度を使って専門家に聞くこともできますが、独学ではその手段がありません。誰にも聞けないまま、時間だけが過ぎていく──これが独学の“沈黙の罠”です。
4.4 モチベーション維持に消耗する毎日
「本当にこのやり方で合格できるのか?」
「もっと効率のいい勉強法があるんじゃないか?」
そんな不安を抱えながら、一人で机に向かい続けるのは、想像以上に消耗します。
勉強は進んでいるように見えて、実は本質的な学力は伸びていない──そんな「見せかけの勉強時間」が増えていたことに、後から気づきました。
【超重要】 独学は“時間コスト”が想像以上に高い
行政書士試験は、知識だけでなく「効率のよい戦略」が求められる試験です。
独学は自由な反面、すべてを自分で背負う必要があり、学習以外の部分にかかる“見えないコスト”が非常に大きい。
この章を読んで、同じ轍を踏まない人が一人でも増えれば、私の2年間の遠回りにも意味があったと思えます。
第5章 通信講座という“時間創出の武器”
これまで紹介してきた独学の課題──計画づくり、教材選び、情報収集、疑問の自己解決──は、どれも本来「学習」以外の部分で発生する“見えない時間コスト”でした。
通信講座は、そうした周辺の負担を大幅にカットし、「学ぶこと」そのものに集中できる環境を提供してくれます。
単なる「教材提供サービス」ではなく、まさに“時間を生み出すツール”としての価値があるのです。
5.1 カリキュラム最適化で「迷う時間」がゼロに
通信講座には、合格者の学習データをもとに構築された「最短ルートのカリキュラム」が用意されています。
- どの科目から着手すべきか
- 重要論点とそうでない論点の時間配分
- 過去問と講義をどうリンクさせるか
これらを一から自分で設計する必要がなく、「今日は何を勉強すればいいか」を迷う時間がゼロになります。
特に行政書士試験では、行政法・民法に多くの学習時間を確保する必要がありますが、こうした“配分の最適化”も自動的に済んでいるのが大きなメリットです。
5.2 スマホ学習でスキマ時間が“質の高い学び”に変わる
多くの通信講座は、スマートフォンを前提に設計されています。
- テキストの閲覧
- 講義動画の視聴(1.5〜2倍速対応)
- 過去問や一問一答の演習
これらすべてが、スマホ1台で完結します。
さらに、「理解度に応じて復習問題を自動出題」「苦手分野をAIが可視化」といった機能が搭載された講座も増えており、通勤時間や昼休みといったスキマ時間が、ただの“空き時間”から“成果の出る学習時間”へと進化します。
5.3 質問制度で停滞を一瞬で解決
独学者が苦しむ「わからないまま進めない」という事態。これを劇的に改善してくれるのが、通信講座の「質問サポート制度」です。
- 民法の抽象的な概念
- 行政手続法の条文の解釈
- 実務との関連性
こうした疑問を、講師や専門スタッフに直接質問できる環境は、独学にはない大きな強みです。
筆者も独学時代、たった一つの論点で1週間以上悩んだことがありましたが、今なら「講座なら10分で解決していた」と断言できます。
5.4 法改正も安心──最新情報を自動で受け取れる
行政書士試験において法改正は避けて通れません。
たとえば、行政手続法・行政不服審査法の改正や、民法の逐次的な見直しなど、出題に影響を与える重要トピックが毎年のように登場します。
通信講座では、こうした変更点を、
- 試験に影響があるかどうか
- どのように改正されたのか
- どの教材が対象になるのか
といった観点から、整理された解説付きで自動配信してくれるため、受講生は「調べる手間なく」「正確な知識を」「適切なタイミングで」受け取れます。
情報の信頼性・網羅性の面でも、講座側のサポートは大きな安心材料となります。
通信講座は“時短”だけでなく、“安心”と“再現性”も同時に手に入れる手段です。
あなたの限られた時間を、より有効に、より合格に直結させるための「時間投資」としての価値を、ぜひ再認識してみてください。
第6章 生活と勉強を両立させるライフハック集
行政書士試験は“長期戦”です。
学習計画や教材だけでなく、「いかに生活と調和させるか」が、継続と合格を左右する大きな要素となります。
この章では、家庭や仕事と両立しながら学び続けるための、実践的な「ライフハック=生活戦略術」を3つの観点からご紹介します。
6.1 家族の理解を得るための対話術
独学・通信講座を問わず、限られた時間で勉強を継続するには、「家族の協力」が不可欠です。特にパートナーや子どもとの関係性は、学習時間の確保だけでなく、精神的な安定にも直結します。
■ ポイント1:「なぜ勉強するのか」を言葉にして伝える
「資格を取ってどうしたいのか」「その先にどんな未来を描いているのか」を、感情も含めて率直に伝えましょう。「家族のためにもなる」という視点を加えると、理解を得やすくなります。
■ ポイント2:具体的な協力内容を提示する
「勉強に協力してほしい」ではなく、「週末の午前中は子どもの相手をお願いできると助かる」など、明確なお願いにすることで合意形成がしやすくなります。
■ ポイント3:数字や損得で説明する
特に男性パートナーに対しては、「講座に20万円かかるけれど、1年早く合格して収入が増える」というロジックも有効です。
■ ポイント4:小さな協力にも感謝を伝える
当然と思わず、こまめに「ありがとう」と言葉にすることで、家族のサポートは長期的に安定します。
6.2 「完璧主義」を手放すマインドセット
仕事も家庭も抱える中で、「毎日計画通りに完璧に進める」のは不可能です。
行政書士試験は180点以上で合格する絶対評価制。すべての論点を完璧に理解する必要はありません。
■ 実践法1:「今日は10分だけ」と決める
疲れている日やモチベーションが下がっている日は、「一問一答を5問だけ」「テキストを10分だけ読む」といった“ミニ目標”を設定することで、学習習慣を維持できます。
■ 実践法2:「休む勇気」を持つ
集中できない日は、思い切って休む選択も有効です。無理に続けて燃え尽きるより、リフレッシュして翌日に備えるほうが効率的です。
■ 実践法3:優先順位をつけて“捨てる”
出題頻度が低く、自分にとって理解が難しい論点は、思い切って後回しにする戦略も必要です。通信講座のカリキュラムは、この“メリハリ”をあらかじめ反映している点が強みです。
6.3 ポモドーロ・テクニックで集中力を最大化
時間が限られる社会人受験生にとって、「短時間でどれだけ集中できるか」は重要な課題です。そこで有効なのが、ポモドーロ・テクニックです。
■ 基本ルール:
- 25分間、1つの課題に集中(スマホ通知オフ)
- 5分間の休憩を取る
- これを1セットとし、4セットごとに長めの休憩(15〜30分)
■ 効果:
- 集中力の持続:時間に区切りがあることでダラダラ防止
- 疲労の軽減:こまめな休憩で脳の負担を分散
- 着手の心理的ハードルを下げる:「とりあえず25分だけ」で始められる
- 達成感が得られる:「1ポモドーロこなした」という成功体験が積み重なる
■ 応用:
- 通勤中15分→「0.5ポモドーロ」
- 昼休み30分→「1ポモドーロ+復習」
このテクニックは、スキマ時間の活用戦略とも相性が良く、生活に組み込めば学習の“OS(基本設計)”として機能します。
試験勉強を生活の「負担」にするか、「リズム」に変えるか──
それを左右するのが、こうしたライフハックの活用です。
おわりに:あなたの時間を「合格への投資資源」に変えるために
行政書士試験の合格をつかむ鍵は、「限られた時間を、いかに効率よく使うか」に尽きます。
学習時間そのものが合否を分けるのではありません。
時間を“どう捻出し、どう活かすか”という「時間戦略」の巧拙こそが、合格までの距離を大きく左右します。
この記事では、
- 平日・休日の学習スケジュールの工夫
- スキマ時間の使い方
- 独学の落とし穴とその克服策
- 通信講座を活用した時間効率の最大化
- 生活と勉強を両立させるライフハック
といった、多忙な社会人・主婦(夫)に向けた「実行可能な時間術」を実体験を交えて紹介してきました。
筆者自身、2年間の独学で合格しましたが、その過程では数え切れないほどの時間を、迷い・遠回り・不安に費やしてしまいました。
今だからこそ言えます。
「あなたには、同じような遠回りをしてほしくない」と。
あなたには、あなたに合った最短ルートを選ぶ自由があります。
そしてその第一歩は、「時間を味方につける」という意思決定です。
机に向かえる時間が少ないからこそ、方法は戦略的であるべきです。
何を使って、どう学ぶか。
その選択が、あなたの未来を形づくります。
さあ、合格というゴールに向けて、今日という一日を“投資”に変える一歩を踏み出しましょう。

行政書士試験徹底解説
行政書士試験の完全攻略ガイド|ゼロから始める社会人のための難易度・勉強法・合格ロードマップ