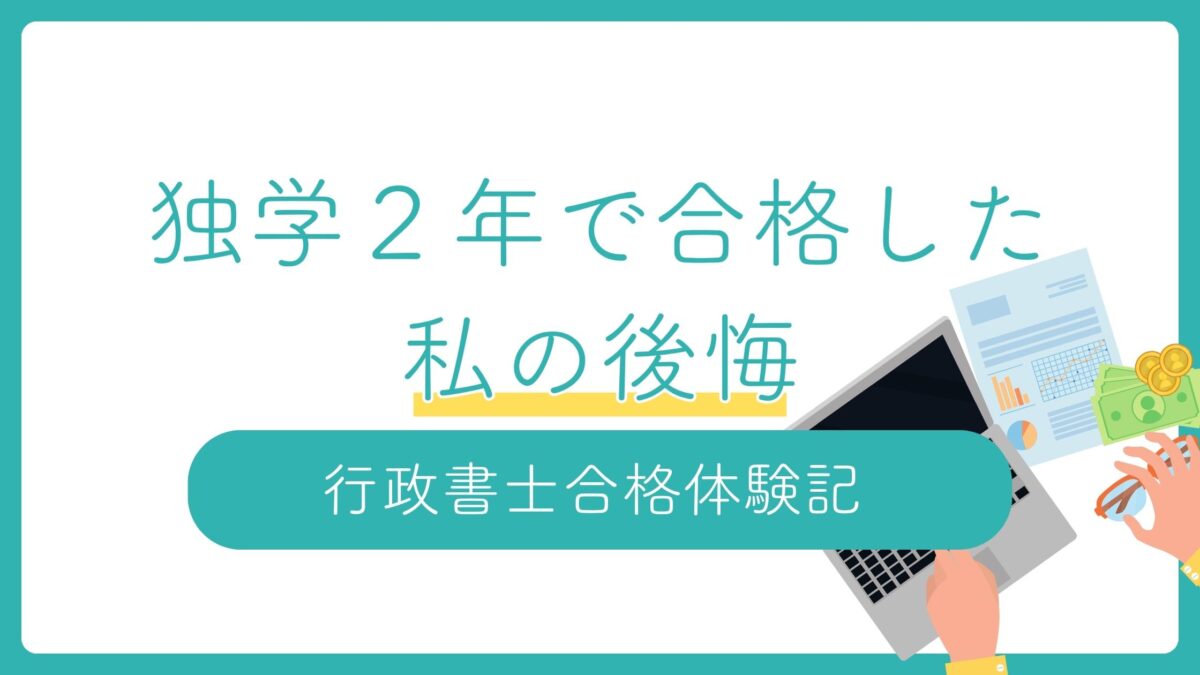第1章 2023年1月 不合格通知
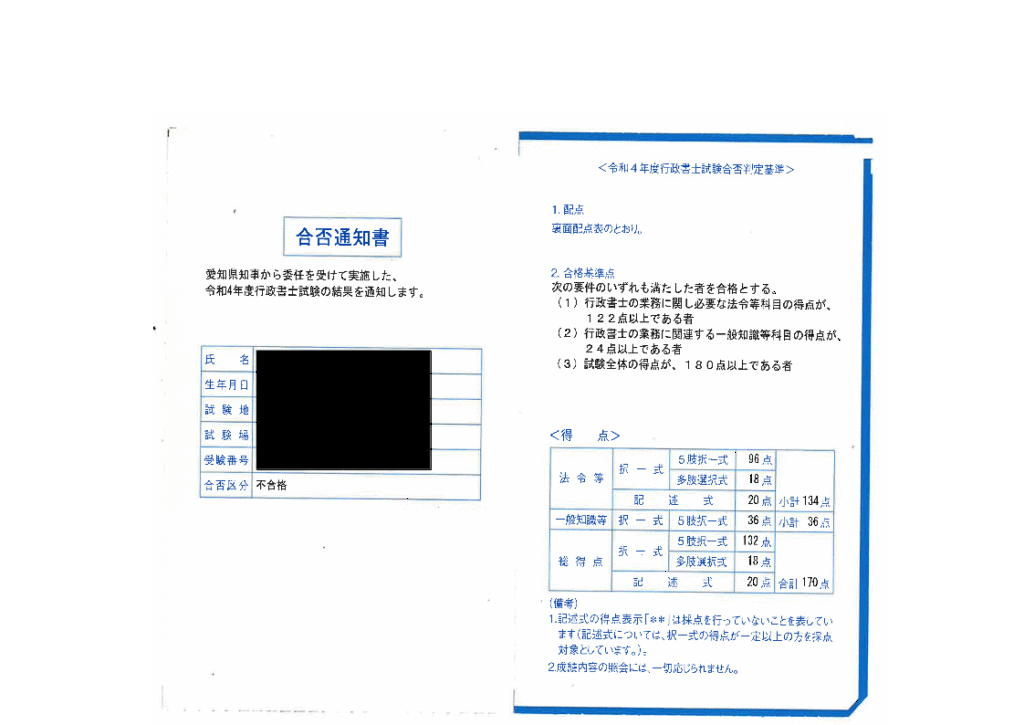
「あと10点・・・」
2023年1月25日、パソコンの画面越しに自分の受験番号がないことを確認。
そのしばらく後届いた合否通知はがきに印字された「不合格」の3文字。
「なんとなく自分なら受かるだろう」
「とりあえず過去問が解ければいいのだろう」
「だったら独学で十分だろう」
そんな根拠のない自信と無謀な計画が引き寄せた3文字の結果は、同時に強烈な悔しさと無力感まで運んできました。
「1年間、完全に無駄になった」
試験が終わって妻に「まあまあできた」なんて言っていた自分。
自己採点で記述抜き150点、「部分点でいけるかも…」と淡い期待を抱いていた自分。
そんな自分が恥ずかしくて、しかたなくなって。
「また家族に迷惑をかけてしまっていいのか」
「同じことをまた1年も続けられるのか」
「人生を変えるために頑張ったのに」
「自分には、無理なのかもしれない」
そうしてしばらくの間、何も手につかなくなったのが、2023年2月のことです。
第2章 何のために勉強するのか
2-1.当時の私のスペックと状況
1年目の受験当時の私は30代前半で、営業職の会社員であり、フルタイムで日中は仕事をしていました。
妻と3歳になる子供がいて、妻も仕事をしており、子供は保育園。
息子の迎は妻と一日交替で、17時半にタイムカードを押してから、保育園へ息子を迎えに行き、あわただしく夕食と入浴を済ませる。
夜22時、妻も子も寝静まってからが私の勉強時間。分厚いテキストを開いてそのまま眠気の限界までひたすら問題を解く。
ちなみに私の学歴は高卒で、当然法律の勉強などしたことがありません。
学歴がないというのは私の最大のコンプレックスで、私を行政書士試験に駆り立てた原因の一つです。
2-2. 何のために行政書士になるのか
そもそも行政書士試験を受けようと思ったきっかけは、コロナで世の中が一変したからでした。
外出制限、営業自粛、リモートワーク。
先の見えない恐れと不安定になっていく勤め先。
「このままではまずい、何かを変えなければいけない」
家族を守るため私が出した結論は、資格取得後すぐ独立可能な行政書士の資格取得でした。
2-3.一年目の勉強の仕方
とは言うものの、まだ子供も小さく、仕事を辞めるわけにもいかない。予備校は自宅から遠いし高いので現実的に通えない。ならば独学するしかない。独学ならお金もかからない。
もちろん今考えると大間違いなのですが、当時はよく調べもせずそんな単純な考え方で行動してしまいました。
「独学はコスパ最高」という賢明な選択をして節約できるのだと信じていました。
そう、実際には、最も長く最も苦痛に満ちた道を選んでいたのです。
1年目の私の独学の仕方といえばひどいものでした。とにかく過去問を解いてみる。わからなければテキストを読んでみる。ぶっちゃけ読んでも意味がわからない。わからないけど、とりあえずそのまま飲み込んでいればいつかわかるようになると信じて次へ進める。
つまり過去問とテキストをほとんど丸暗記しているに近い有様でした。
自分が今どこにいて、どこに向かっているのかすらわからない。
高卒であるという劣等感を抱えていた私の一部は、何かを証明するために、独力でやり遂げなければならない、そう信じこんでいました。それは自尊心を守るために無意識に築いた、あまりにも代償の大きい選択でした。
結局行政法も民法もあいまいで、会社法などほぼ頭に残っていない状態で迎えた2022年11月の試験本番当日。
何とか時間内に解ききって、記述もとにかく埋めて、あとは合格を信じて祈るのみでした。
その結果が不合格。
今振り返るとなんでこのやり方で170点も取れたのだろうかと不思議になります。
第3章 決意と反省のリベンジ
不合格通知を受け取ってからしばらくの間、私は行政書試験の勉強から離れて、本当に自分が行政書士になりたいのか改めて考えました
そして
「高卒の自分が人生を変えるには行政書士しかない。もう一度やってみよう。」
「なぜ失敗したのか分析し直してみよう。あと10点だったのだから、この1年で絶対に合格してやろう」
そうして、リベンジの決意をしました。
とはいえその後も私の独学は迷走していました。
テキストがわかりにくかったのではないかと思い、本屋ですべてのテキストを立ち読みしてみて一番わかりやすいそうなものを選び直し、問題集も買い直す。
はっきり言えることは、独学がコスパがいいなんて言うのはウソだということです。一部の天才的に賢い人を除いて、それは最も遠回りです。
私は少なくとも20時間以上は本屋とインターネットでの情報収集に浪費したと思います。
正しい地図(カリキュラム)があれば、決して踏み込む必要のない回り道です。
とにかくがむしゃらに、通勤時間や仕事の昼休憩やちょっとした空き時間はテキストを開いたりアプリで一問一答を解き、家に帰って子供や妻が寝た後の時間でひたすら問題集とテキストを開いて勉強を毎日毎日繰り返しました。
それだけ遠回りをしながら勉強して、やっと10月に受けた模試で200点を超えることができました。
でもそれも、正しい地図(カリキュラム)があれば、もっと早く・安心してその点数ににたどり着けたはずです。
第4章 合格と後悔
2023年11月の試験本番当日は、テキストも何も持たずに、ただ自分に「絶対できる。絶対にやれる。」そう言い聞かせながら会場に向かいました。
試験問題は順調に解くことができ、試験が終わった瞬間、「受かった」という感覚がありました。
翌日、予備校の解答速報で自己採点をした結果、記述抜きで174点。
間違いなく受かっていると確信できました。
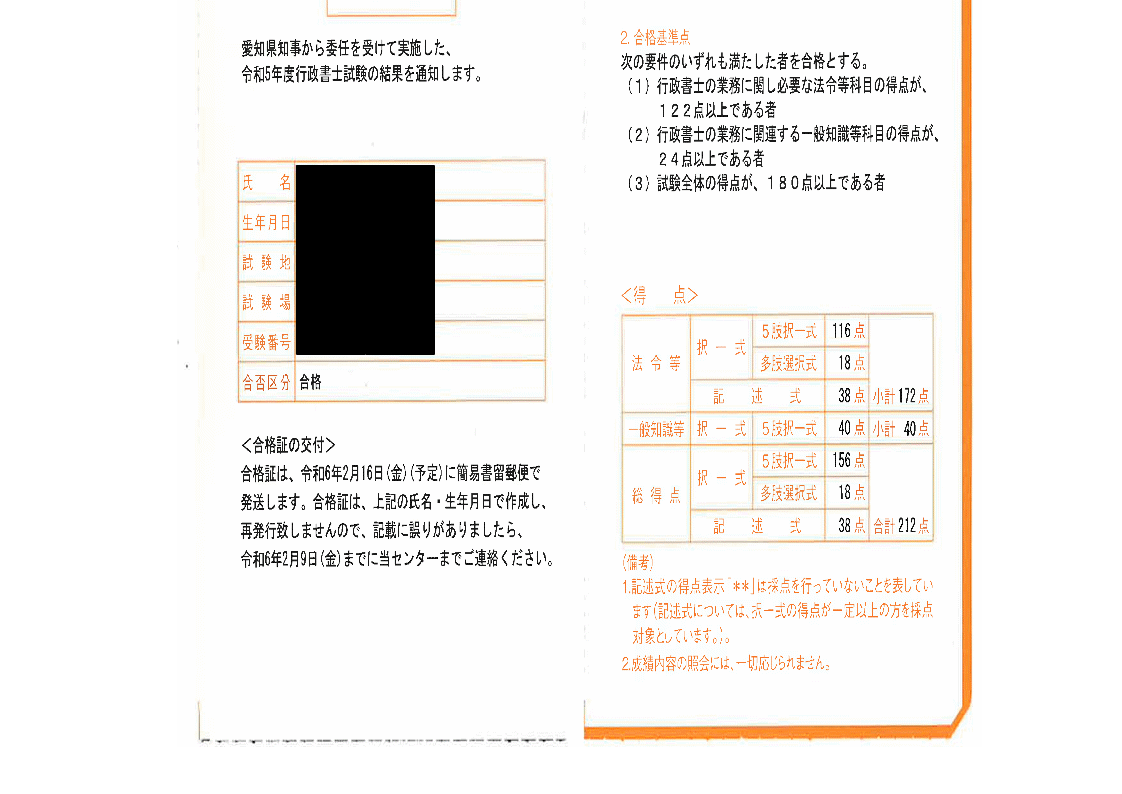
そして2024年1月31日、パソコンの画面越しに自分の番号が載っていることを確認。
そのしばらく後届いた合否通知のはがきに印字された「合格」の二文字。嬉しかった。そう、確かに嬉しかったのですが、同時に頭をよぎった言葉があります。
「やっと終わった」
「でも、もしかして」
「あと1年、合格を早められたのではないか?」
第5章 開業
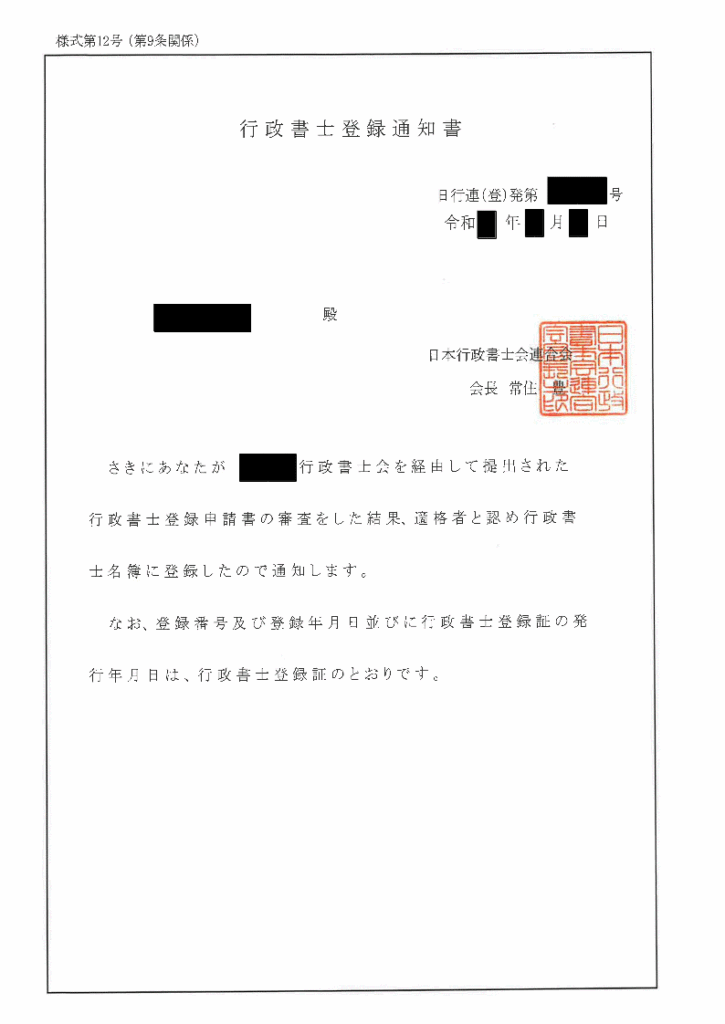
そのまま、行政書士として私は開業しました。
今は毎日が楽しいです。
自分の裁量で自由に働けることが、会社員と自営業の1番の違いで、そして、何より1番充実する部分だと思っています。
そして、実際、行政書士になって思ったことがあります。
それは、
「かなり人手不足ではないか?特に都市部を除けば30代以下は全くと言っていいほどいないのではないか?」
と、いうことです。
実際、私が所属する支部は都心から車で小1時間ほど離れたところですが、大半が60代以上の先生です。
田舎だからか、土地家屋調査士や司法書士との兼業の方がほとんどで、そもそも30代の行政書士はほぼいません。
だからたまに研修で同世代がいると、それだけで会話のきっかけになります。
ぜひこれを読んでいる行政書士受験生の方は、ぜひ最短ルートで合格し、行政書士になってください。
一緒に業界を盛り上げましょう。一緒にこの成長市場で働きましょう。

行政書士試験徹底解説
行政書士試験の完全攻略ガイド|ゼロから始める社会人のための難易度・勉強法・合格ロードマップ